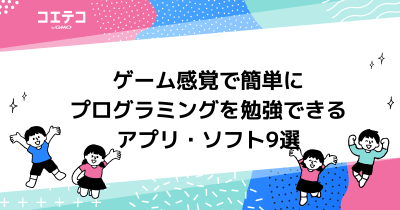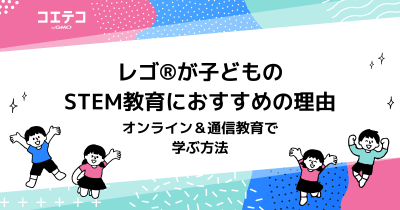【幼児~小学生向け】プログラミングおもちゃおすすめ9選を年代別に紹介
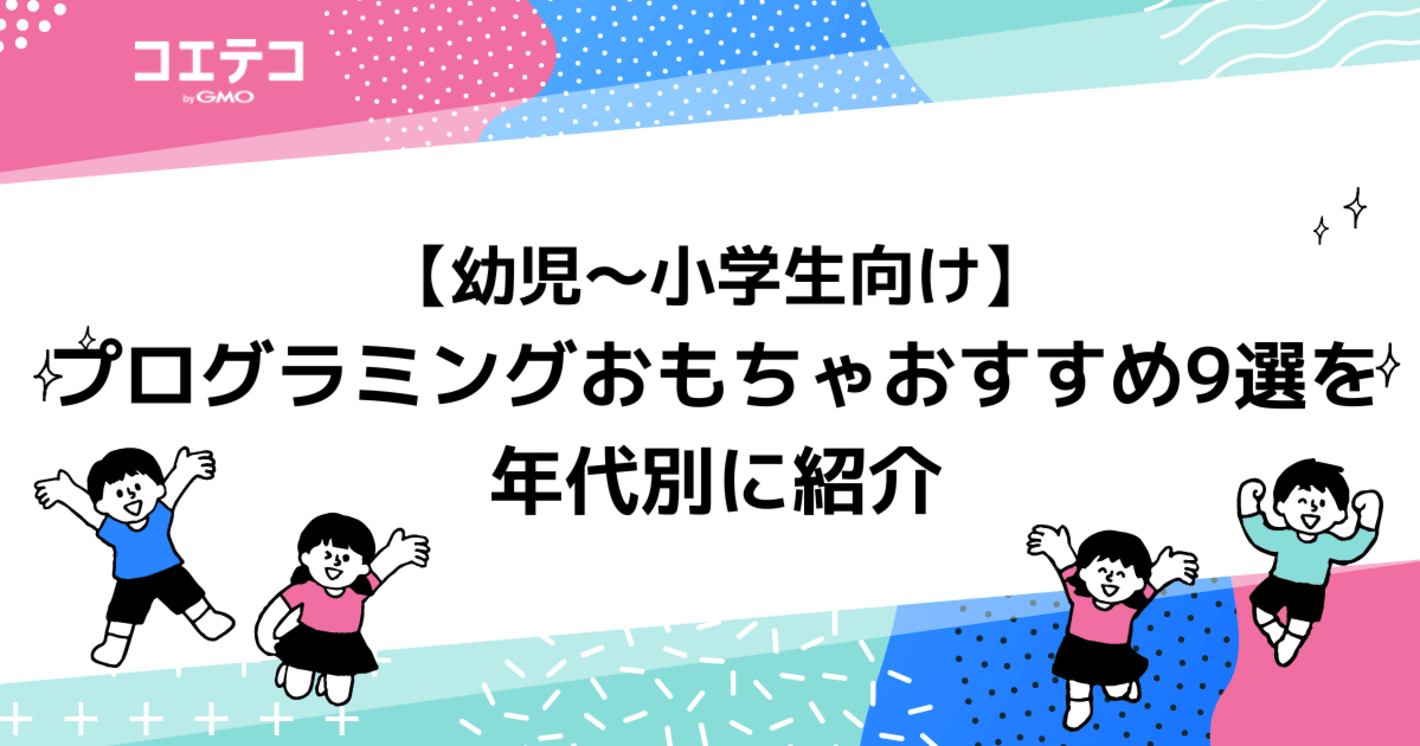
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

子ども向けに工夫された、プログラミングを楽しく学ぶためのおもちゃを紹介。東京情報大学総合情報学部の教授であり、プログラミング教育者やサイエンスライターとしても活躍する、松下孝太郎さんが解説します。
プログラミングおもちゃ(プログラミングトイ)とは、知育玩具の一種で、遊びながらプログラミング的思考やプログラミング技術を身につけられるものです。
プログラミングおもちゃの分類
プログラミングおもちゃは、コンピューターを使用しないおもちゃと、コンピューターを使用するおもちゃとに大別することができます。また、どちらのおもちゃも、ボードゲームタイプ、ブロックタイプ、ロボットタイプなど、おもちゃの形態や遊び方により分類することができます。

コンピューターを使用するプログラミングおもちゃは、コンピューターを使ってプログラミングを行い、完成したプログラムでおもちゃを動かします。その過程でプログラミング的思考やプログラミングの技術を学ぶことができ、子どもだけでなく大人も楽しめます。
コンピューターを使用しないプログラミングおもちゃは、おもちゃで遊ぶ過程でプログラミング的思考を学べるようになっています。なお、コンピューターを使用しないプログラミングを「アンプラグドプログラミング」ともいい、幼児や小学校低学年生が保護者と一緒に楽しむものが多いです。
プログラミングおもちゃの代表的な会社
プログラミングおもちゃは国内、海外ともに多数販売されています。プログラミングおもちゃの製作や販売を行っている代表的な国内の会社をいくつか紹介します。株式会社タカラトミー
1953年に設立された会社です。おもちゃの製作では国内有数の会社で、トミカ、プラレール、着せ替え人形のリカちゃんなどが有名です。会社のホームページ:https://www.takaratomy.co.jp/
ソニー株式会社
ソニーグループ株式会社のエレクトロニクス部門を担う会社です。グループの製品では、パソコンのVAIO(バイオ)、犬型ロボットのaibo(アイボ)などが有名です。会社のホームページ:https://www.sony.co.jp/
株式会社アーテック
1960年に設立された会社です。学校向けの教材製作では国内有数の会社です。近年では、こども向けの各種教室のフランチャイズにも力を入れています。会社のホームページ:https://www.artec-kk.co.jp/
くもん(公文教育研究会)
1962年(昭和37年)に設立された公文学習研究会が前身です。くもんとおる氏により開発された「公文式」と言われる学習方法による学習塾の展開を行っています。また、書籍やおもちゃの製作なども行っています。会社のホームページ:https://www.kumon.ne.jp/
おすすめプログラミングおもちゃの選定基準
プログラミングおもちゃは沢山ありますが、ここでは、コストパフォーマンス、扱いやすさと安全性、プログラミング学習の深まりの観点を考慮して、対象年齢ごとにいくつか選びました。【入学前~低学年・5歳くらい~7歳向け】おすすめプログラミングおもちゃ
物に触れながら思ったとおりに動かすことに対して興味を持つことは大切です。「面白い!!」「できた!!」と思えるかどうかという観点で選ぶと良いでしょう。コンピューターを使わない「アンプラグドプログラミング」から入ってみるのも良いでしょう。Quoridor Kids(コリドール・キッズ)/ Gigamic(ギガミック)

ネズミを前後左右へ動かすことや、フェンスを置くことよりその後の場面が変化することから、順次処理だけでなく条件分岐の考え方をゲームを通して学ぶことができます。
キュベット / プリモトイズ

動作を表すブロックをボードにはめていき、スイッチを押すとブロックの指示どおりにキュベットと呼ばれるロボットが動きます。
ロボットへの動作指示するブロックの並べ方でロボットの動作を変化させることを通して、順次処理などを学ぶことができます。また、ファンクションブロックを使うことにより、関数(サブルーチン)の考え方を学ぶことができます。
プログラミング・キンダーボット / fisher-price(フィッシャー プライス)

車状の足を持つロボットの頭上にあるスイッチにより、動く方向などをプログラミングして動かします。
ロボットの頭上のスイッチの設定を通して、順次処理の基本的な考え方などを学ぶことができます。
【中学年・7歳~10歳】おすすめプログラミングおもちゃ
中学生向けのプログラミング学習のおもちゃには、アルゴリズムやプログラミング技術の育成をやや意識しながらも、扱いやすさや動く喜びを感じられるものが良いでしょう。embot(エムボット)

ロボットを操作するこを目的としたビジュアルプログラミングを通して、アルゴリズム全般を学ぶことができます。
※タブレットは別売りです。組み立て済みロボットは入っておりません。
Artec Robo(アーテック ロボ) / アーテック

キャラクターを操作するこを目的としたビジュアルプログラミングを通して、アルゴリズム全般を学ぶことができます。
ポケモンパッド ピカッとアカデミー / タカラトミー

【高学年・10歳~】おすすめプログラミングおもちゃ
小学校高学年用のプログラミングおもちゃは、創作性や操作性に富むものや、アルゴリズムの理解、プログラミング技術の修得も念頭において選んで良いでしょう。KOOV(クーブ) / ソニー

ブロックで車やロボットなどのさまざまなキャラクターを作成し、プログラミングを行って動かします。ベーシックキット、スターターキット、アドバンスキットの3種類があります。ブロックを配置していく形式のビジュアルプログラミング環境が提供されています。
キャラクターを操作することを目的としたビジュアルプログラミングを通して、アルゴリズム全般を学ぶことができます。
LEGO(レゴ) ブースト / レゴ
ブロックでロボットなどを作成し、プログラミングによって動かします。なお、国内外において広く使われているビジュアルプログラミング言語のScratch(スクラッチ)には拡張機能として、レゴ(LEGO® MINDSTORMS® EV3、LEGO® BOOST、LEGO® Education WeDo 2.0)を操作するブロックが装備されています。
RobotX(ロボットエックス) / Apitor(アピター)
ブロックでロボット作成し、プログラミングを行って動かします。ブロックを配置していく形式のビジュアルプログラミング環境が提供されています。また、STEAM教育にも対応しています。おもちゃを活用したプログラミング学習についてよくある質問
プログラミングおもちゃを初めて買いたいという人も多いでしょう。ここでは、よくある質問に教育者の観点から答えます。プログラミングおもちゃを使った学習にパソコンは不要?
プログラミングおもちゃには、コンピューターを使うものと、コンピューターを使わないものがあります。コンピューターを使うおもちゃは、コンピューターで作成したプログラムでおもちゃを動かしますので、コンピューターが必要です。前述の「コリドール・キッズ」「キュベット」など、アンプラグドプログラミングのおもちゃであればパソコンは必要ありません。
プログラミングおもちゃを通じて学ぶメリットは?初めからパソコンで学ぶ必要は?
幼児や小学校低学年の場合は、コンピューターを使わないプログラミングおもちゃから入っても良いと思います。プログラミングではなく、コンピューターの操作自体でつまずき意欲をなくす可能性もあります。ある程度理解ができた段階や、学年が上がった段階で、コンピューターを購入し、コンピューターでプログラミングを行うプログラミングおもちゃに移行すると良いです。
購入予算はどれくらいを見積もるべき?
プログラミングおもちゃの価格は、おもちゃの種類や付属品などにより大きく異なります。一概に予算を決定することは難しいですが、同じタイプのプログラミングおもちゃでも、ベーシックキット、アドバンスキットなどのように、機能、部品数、付属品により複数の価格帯のラインナップが用意されている場合も多いです。こどもの年齢、目的とする機能を考慮し、無理のないご予算により購入されると良いと思います。
木製のプログラミングおもちゃもある?
木製のプログラミングおもちゃもあります。この記事で紹介した「キュベット」も木製です。上級生用のプログラミングおもちゃは、おもちゃ自体の製作のしやすさや、電子機能の実装の面からプラスチック製のものが多く見られます。まとめ
2020年度から開始された小学校におけるプログラミング教育の必修化されました。お子様のプログラミング教育に対し期待がある一方、どのように新しい教育に接していけばよいのかわからない保護者の方も多いでしょう。小学校では、プログラミングの技術の修得を必須としているのではなく、問題解決能力やプログラミング的思考の育成を目的としています。
子どもには、プログラミングおもちゃなどに触れることにより、プログラミングは「楽しい」「面白い」という気持ちを抱かせることが大切です。教育や成績を意識しすぎず、こどもが興味を示したおもちゃに触れさせるのが良いでしょう。
プログラミングおもちゃを通して、子どもたちがプログラミングに興味を持ち、将来の進路の幅を広げていくことを願います。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
Scratch(スクラッチ)の基本的な使い方 プログラミング例・サンプルを紹介
スクラッチはどうやって始めたら良いの?東京情報大学総合情報学部の教授であり、プログラミング教育者やサイエンスライターとしても活躍する、松下孝太郎さんが解説します。
2025.06.24|コエテコ教育コラム
-
ゲーム感覚で簡単にプログラミングを勉強できるアプリ・ソフト10選
ゲームで遊びながらプログラミングが学べるってホントなの?東京情報大学総合情報学部の教授であり、プログラミング教育者やサイエンスライターとしても活躍する、松下孝太郎さんが解説します。
2025.05.26|コエテコ教育コラム
-
レゴ®が子どものSTEM教育におすすめの理由 オンライン&通信教育で学ぶ方法
組み合わせや工夫次第でいろいろな物を作って遊べる「レゴ®ブロック」。知育玩具として選ぶ保護者も多く、STEM教育に最適な教材として、教育の現場でも活用されています。この記事では、STE...
2024.11.06|コエテコ教育コラム
-
【エンジニアとして世界へ!】情報工学やロボット工学を学べる大学 ~私立編~
子どもにとって人生のターニングポイントとなるのが大学選び。将来の可能性を広げるためにも、大学や学部選びのための情報収集は、早いうちから時間をかけて、じっくりと取り組みたいものです。今回...
2025.06.24|なりかわさやか
-
ロボット工学で有名な国公立大学おすすめ6選!
子どもにとって人生のターニングポイントとなるのが大学選び。将来の可能性を広げるためにも、大学や学部選びのための情報収集は、早いうちから時間をかけて、じっくりと取り組みたいものです。今回...
2025.06.24|なりかわさやか