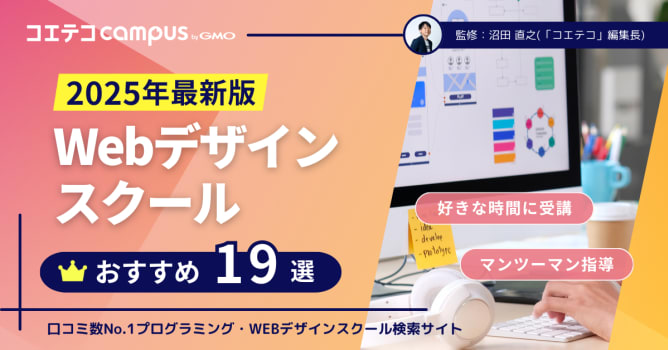E資格は意味ないは本当?真実とメリット5選を徹底解説!

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
近年、AIの進化・注目度の高まりは留まるところを知りません。経済産業省からは「2030年にAI・IT人材は最大約80万人不足する」とのデータまで出ている状況。
そんなAIを学べる資格として「E資格」が人気を高めていますが「取得する意味がない」「やめとけ」といった声も見受けられ、受験を躊躇している人もいるのではないでしょうか。
この記事では「そもそもE資格ってどんな資格なの?」といった概要をはじめ、E資格は取っても意味ないと言われている理由について、具体的に解説していきます。
E資格を取得するメリットもまとめましたので、少しでもE資格に興味がある人はぜひご覧ください。
「E資格」はディープラーニングの理論・知識を問う資格
「E資格」は、AI・機械学習に欠かせないディープラーニングの理論・実装能力等が問われる資格試験です。一般社団法人日本ディープラーニング協会(以下JDLA)が運営するもので、2018年からスタートしています。
資格概要は以下の通りで、2年以内に「JDLA認定プログラム」という講座・講習を別途修了することが受験条件になっているのが特徴です。
受験資格 |
JDLA認定プログラムを試験日の過去2年以内に修了していること |
実施概要 |
試験時間:120分 知識問題(多肢選択式・100問程度) 各地の指定試験会場にて受験 |
試験会場 |
実地開催 ※申し込み時に希望会場を選択 |
出題範囲 |
JDLA認定プログラム修了レベルの出題 ※シラバスあり |
受験費用 |
一般:33,000円(税込) 学生:22,000円(税込) 会員:27,500円(税込) |
AIの各種学習手法や数学関係等を含む、計4分野です。
-
応用数学
確率・統計、情報理論 -
機械学習
機械学習の基礎、実用的な方法論、強化学習 -
深層学習
順伝播型ネットワーク、深層モデルのための正則化、深層モデルのための最適化、畳み込みネットワークなど -
開発・運用環境
ミドルウェア、エッジコンピューティング、分散処理、アクセラレータ、環境構築
AIスキルの基底となる機械学習の理論・実装方法等を理解したうえで、実際の問題解決に取り組める程度のレベルまで求められる、かなり難易度の高い資格となっています。
AI資格おすすめランキング10選!生成AI資格試験も徹底解説
公式より合格率が公開されていましたが、2018年のスタート以来70%前後を推移しているとのこと。
JDLA認定プログラムを修了したハイレベルな人材しか受験できないにもかかわらずこの数値であるため、決して一筋縄でいくものではないことが分かるかと思います。
AIに関するプログラミング言語を学びたいと考える人は、下記記事にも目を通しておきましょう。
AI言語でできることや勉強法なども解説しているため、AIスキルを身につけたい人は参考になるでしょう。
AIプログラミング言語おすすめ5選!AIエンジニアを狙う方向けも紹介
E資格は意味ないと言われる3つの理由
その難易度に見合ったメリットがあってもおかしくないにもかかわらず、E資格に対してネガティブな声が多いのにはどのような理由があるのでしょうか。ここでは、巷で「E資格は意味ない」「やめとけ」といった意見が飛び交っている主な理由を3つご紹介します。
- 資格の認知度がまだまだ低いから
- AI関係に特化した資格だから
- 難易度が高く簡単には合格できないから
資格の認知度がまだまだ低いから
先述した通り、E資格が始まったのは2018年と、数ある資格試験の中でもかなり後発。加えて、そもそもAIやディープラーニングの認知がまだまだ進んでいないこともあり、E資格という存在自体を知らない方が少なくありません。
そのため「取得しても使い道がない」「価値が低い」と誤解されやすい傾向にあります。
この問題は、今日存在する「G検定」「AI実装検定」といったAI関連資格全般に共通する問題と言えるでしょう。
最も、資格の価値は社会全体の認知度だけで決まるわけではありません。
特定の分野での専門性を証明するためのものなので、知名度が低いというだけで「E資格は意味ない・やめとけ」とする声は、必要以上に気にする必要はないとも言えます。
AI関係に特化した資格だから
出題範囲(シラバス)を見ればわかる通り、E資格を通して学べる内容・証明できるスキルはAIの関連知識のみであり、それ以上でもそれ以下でもありません。IT系の一般的な知識・技術を証明する資格ではないため、用途を理解した上で挑戦しないとせっかく取得しても恩恵を感じにくいでしょう。
E資格が求められる業界・職場はまだ限定的であり、所持していたところで必ずしも活かせるとは限らない状況です。
その特化性が「取っても意味ない」と言われる一因となっていると考えられます。
しかし逆の観点から見れば、AI人材の中でもディープラーニングに特化したスキルを持つことは稀少性を示す証ともなります。
既にAI・ディープラーニングの活用に積極的な企業やプロジェクトにおいては、E資格を保持しておく意味は大いにあるでしょう。
AIに関しては下記記事でも詳しく紹介しています。
それぞれの記事では、AIを学ぶ目的やメリット、さらには、身近に用いられているAIなどについて解説しているので、あわせてご覧ください。
AIの勉強方法!独学で初心者は何から始めるべきか社会人向けも解説
身近なAI(人工知能)とは?日常生活で使われている例を解説
難易度が高く簡単には合格できないから
E資格は「応用数学」「機械学習」「深層学習」「開発・運用環境」の4分野の知識を兼ね備えなければ合格できないため、難易度は非常に高くなっています。本格的なディープラーニングの理論を学ぶことはもちろん、実装できる技術力を持つことまで要求されるため、生半可な準備で挑戦しても取得できるものではありません。
先にも述べた通り、JDLA認定講座をパスするほどのスキルをもってしても、3割程度は不合格となってしまうのが現実。
「どうせ合格できないから受けても意味ない」という声が出てくるのもうなずけるでしょう。
このようなハードルの高さは一見するとデメリットに感じますが、この難しさがE資格の価値を高めているとも言えます。
難易度が高いからこそ、取得者の能力や努力が如実に示され、企業の採用面接などでも高く評価されるのではないでしょうか。
参考:「E資格(エンジニア資格)2023#1」結果発表(1,112名が受験し、807名が合格) - 一般社団法人日本ディープラーニング協会【公式】
下記記事では、E資格の難易度について詳しく解説しています。
E資格の具体的な勉強方法や過去の合格率についても触れているため、ぜひ参考にしてみてください。
E資格の難易度は?勉強時間・合格率について徹底解説
E資格を取得するメリット5選
ネガティブな声が目立つE資格ですが、当然挑戦する価値が全くないわけではありません。ここからは「E資格を取得するメリット」として、E資格を持っていると自分のキャリアにどう役立つのかを具体的に見ていきます。
「E資格にチャレンジしてみたいけど、受ける意味があるのか分からない」と悩んでいる人は必見です。
- AIに関する高いスキルがあることを証明できる
- キャリアアップ・キャリアチェンジにも有利
- AI人材が集う専用コミュニティに参加できる
AIに関する高いスキルがあることを証明できる
E資格に挑戦することで、AIやディープラーニングに関する知識が体系的に身につきます。AI業界でも比較的知名度の高い資格ということもあり、E資格を持っていれば「AIに関する知識をあらかた身につけている」という証明になるでしょう。
AIのスキルは昨今非常に需要が高い一方で、独学で身につけるとなると「何から手を付ければいいのかわからない…」なんて事態に陥りがち。
その点、しっかりと練られたシラバスに沿って学習を進めていくだけで一通りのAI知識が見につくE資格は「これからAI業界で活躍していきたい」「自分のAIスキルをアピールできる資格を取得したい」と考えている人にうってつけと言えます。
G検定もAI・ディープラーニングの活用リテラシーを証明できる資格の一つです。
E検定よりも比較的難易度が易しいと言われているため、まずはG検定からの取得を目指すのも良いでしょう。
G検定の勉強方法!初心者でも合格【最新版】
キャリアチェンジ・キャリアアップにも有利
「現在の職場でより高度な業務に参画していけるようになりたい」「AIに関連する新たなフィールドへの転職を考えている」といった人たちにとっても、E資格は強力な武器となります。AIの成長が著しい今、どこの企業もスキルを持ったAI人材を欲している傾向にあるため、AIに関する包括的な知識がなければ合格できない「E資格」は評価向上に寄与しやすいからです。
AIエンジニア・データサイエンティストといったAI人材としてキャリアチェンジやさらなる評価UPを狙っているのであれば、E資格に挑戦する価値は大いにあるでしょう。
AIエンジニアの転職事情・将来性については下記記事でも詳しく紹介しています。
転職エージェントを利用するメリットを知りたい方も、下記記事をご覧ください。
AIエンジニアに強い転職エージェントおすすめまとめ!サイトも比較
AI人材が集う専用コミュニティに参加できる
JDLAは、同団体が運営する資格試験「G検定」「E資格」合格者のみが参加できる日本最大のAIコミュニティ「CDLE」を運営しています。CDLEでは、主に以下4つの活動を通して、メンバー同士が切磋琢磨しあっているとのこと。
-
情報共有
ディープラーニング全般の最新ニュース・論文・おすすめの書籍情報、業界別の最新動向、社会実装事例 -
学び合い
有識者や著名人を招いたメンバー限定の勉強会/特別講演、GoogleやAlibaba等が主催するカンファレンスなどの技術報告会・メンバー主催の勉強会・読書会など -
交流
地域別のmeet-up、業界別のmeet-up、学生限定グループ、女性限定グループ -
アウトプット
LT会、ハッカソン、Kaggleなどのコンペティション、スタートアップ、メディア運営
数多のAI人材が集うこのグループの一員になれるというだけでも、E資格を取得する価値があると言えるでしょう。
発展途上のAI業界において、情報交換・意見共有できる仲間はかけがえのない存在です。
またこのようなコミュニティは、自分だけでは気づけなかった視点を学ぶこともでき、自己成長に繋がるという意味でも非常に有意義です。
そこから生まれる人的ネットワークも、未来のキャリア形成において大きく貢献してくれることでしょう。
学習仲間と出会いたい方は、生成AIスクールを受講するのもおすすめです。
下記記事では生成AIスクールについて解説しているので、ぜひご覧ください。
生成AIスクールおすすめまとめを徹底比較【最新】補助金対象講座も解説
年収がアップする可能性がある
E資格を取得することで高いスキルを保持していることが認められ、年収がアップする可能性があります。年収アップが期待できるパターンとしては、資格取得補助が受けられる会社で働いている場合、フリーランスとして活躍している場合などです。
転職する際に、年収交渉の材料としても使えるでしょう。
デザイン・アート・テクノロジーを組み合わせた事業を展開する株式会社デジタルキューブでは、2024年7月にE資格が資格手当の対象になっています。
ただし、業界や職種によってはE資格が重視されないこともあるため、必ず年収をアップできるわけではありません。
参考:Digital Cube「資格手当の見直しを行いました(2024年版)」
就職や転職で有利になる
AIエンジニアを募集している企業の多くはE資格取得者を歓迎しているため、就職や転職で有利になるでしょう。難易度の高い資格なので、IT業界では高スキル保持者として重宝されます。
E資格は、理論だけでなく実務に直結するスキルも習得できることから、ほかのAIエンジニアとの差別要素にもなる可能性が大です。
E資格取得にかかる費用
ここでは、E資格取得にかかる費用を解説します。JDLA認定プログラムの受講費用
E資格を受験するには、いずれかのプログラムを受講し、受験日の過去2年以内に講座を修了していなければなりません。期間が「2年以内」と限定されているのは、ディープラーニング技術の最新動向を踏まえ、シラバスを1~2年おきに見直されているからです。
JDLA認定プログラムの受講費用は、5万円~49万5,000円ほどです。
JDLAに認定された16プログラムからニーズに合ったプログラムを選ぶ必要があり、PythonやE資格について学べます。
参考:一般社団法人 日本ディープラーニング協会「JDLA認定プログラム」
E資格の受講費用
E資格の受講費用は、一般:33,000円・学生:22,000円・会員:27,500円(税込)です。JDLA認定プログラムを試験日の過去2年以内に終了している人のみに受験資格があります。
試験時間は120分で、多肢選択式の問題が100問ほど出題されます。
参考:一般社団法人 日本ディープラーニング「E資格とは」
テキスト・対策講座受講費用
テキストや参考書を購入する場合は、受講料に加えて1~3万円ほど必要となります。模擬テストは3,000円~行われていますが、実施企業により費用が異なるため、注意が必要です。
口座によっては、模擬テスト代がコース料金に含まれている場合もあります。
参考:zero one「E資格チャレンジテスト」
E資格対策スクールを選ぶポイント
自分に合ったE資格対策スクールを選ぶポイントについて解説します。実績
E資格対策スクールの実績を調べることで、信頼できるスクールかどうかを確認できます。過去どのくらいの合格者を輩出しているか、運営実績はどのくらいあるかをチェックしましょう。
ノウハウが豊富なスクールなら、一人ひとりの学力や進み具合に応じて的確に指導してもらえる可能性が高まります。
実績を調べる際は、受講者の口コミや評判もチェックして、カリキュラムの質やサポートの充実度も確認するのがおすすめです。
受講者のリアルな声からしかわからない情報もあります。
サポート体制
学習サポートは充実しているか、合格サポートは実施されているか、不合格の場合はサポートを受けられるかを確認しましょう。また、実施されているかだけでなく、内容や充実度までチェックすることが大切です。
例えば、学習サポートの場合は、メンターや講師による質問対応があったとしても、回数や期間、対応時間が決められていることがあります。
「思ってたのと違う」と後悔したくない人には、サポートの詳細まで確認しておくことをおすすめします。
E資格対策も可能なおすすめデータサイエンススクール4選
AIやデータサイエンスは独学でもチャレンジできますが、体系立てて学ぶにはデータサイエンススクールの利用がおすすめです。ここではAIやデータサイエンスを学べるスクールを紹介します。下記記事ではE資格認定プログラムおすすめ講座を紹介しているので、あわせてご覧ください。
E資格認定プログラムおすすめ講座を徹底比較【最新版】
Aidemy Premium(アイデミープレミアム)

E資格の取得を目指せるのはAidemy Premium(アイデミープレミアム)です。
1年中開講しているE資格対策講座には、合格保証制度があります。受講期間中に好きなタイミングで学べるのはもちろん、一定条件を満たすと試験合格まで無料でサポートを受けられる仕組みです。
全部で6種類用意されている講座は、どれもPythonに特化しているのも特徴。受講するとPythonについての基礎的な知識を身につけ、自分でコードをかけるようになります。
学習はオンラインで進めますが、バーチャル学習室を利用すると同期生と一緒に学ぶことも可能です。同じように学ぶ仲間との交流を通して、モチベーションアップも期待できます。
※ 下記口コミは、ITスクール情報比較サイト「コエテコキャンパスbyGMO」に投稿された内容を使用しています。

- 20代 女性
- メーカー/製造業
未経験から、株式会社アイデミーのデータ分析講座を受講しました
★★★★★
5.0
学習が、小単元事に別れていて、学んだ後にすぐ確認テストがありました。 それが自分には合っていて、インプットだけでなくアウトプットしながら学習でき、定着も早かったかなと思います。

- 30代 男性
- 不動産
【初学者からのススメ】プログラミング初学者は可能な限りオンラインを活用せよ
★★★★★
5.0
完全にオンラインで完結する、夕方から夜の時間帯に講師の方々に質問が出来る、スラックであればいつでも質問できる、など、学習意欲さえあればいくらでも学習できる環境が整っていました。

- 30代 女性
- 薬剤師
先生方が素晴らしい!自分のペースで進められて育児中の母でも2コース修了できました
★★★★★
5.0
先生の質が高い。 完全オンラインのためモチベーションの維持が大変でしたが、先生のお陰で最後まで続けることができました。 転職活動中も励ましていただいたお陰で、アルバイトですがフルリモートで就職することができました。 講座が始まったばかりのころ、未経験でAIエンジニア、しかもフルリモートで働くのは厳しいと他の所で言われて凹んでいたのですが、Aidemyの先生がとてもポジティブに励ましてくださいました。 具体的にどのように転職活動すべきかアドバイスもくださり、その通り実践したところ内定をもらうことができました。 その後も、モチベーションが下がると先生方とカウンセリングして元気をもらい、当初予定していたデータ分析講座だけでなく、E資格講座も受講を終えることができました。
データラーニングスクール

データラーニングスクールは、現役データサイエンティストの個別メンタリングを受けながら、スキル習得を目指せるスクールです。
サポートも充実しており、1回につき45分の完全個別メンタリングを18回受けられます。技術的な質問やポートフォリオに関する質問にも対応可能です。
技術やスキルを学んで終わりではなく、転職成功までサポートしているのもポイント。自己分析や転職プランの作成支援、履歴書・職務経歴書の添削などを受けながら、身につけたスキルを活かせる職場への転職を目指せます。
データ分析のオンラインコミュニティ「データラーニングギルド」への永久参加権を得られるのもメリットです。交流や学習コンテンツを通して、実践的な学びにつなげられます。
※ 下記口コミは、ITスクール情報比較サイト「コエテコキャンパスbyGMO」に投稿された内容を使用しています。

- 20代 男性
- メーカー/製造業
多くの人におすすめしたい、分析で新たな気づきを教えてもらえる!
★★★★★
4.0
私自身未経験でも、半年で社内のプロジェクトで成果物だす事ができたので、興味を持って取り組める人であれば、おすすめしたい。

- 30代 女性
- サービス業
キャリアチェンジや転職を考えられている方におすすめです
★★★★★
5.0
分からないことがあればメッセージでの質問にも対応してくださったので未経験でも学習を進めやすかったです。
侍エンジニア

侍エンジニアは、累計指導実績45,000万人を誇るプログラミングスクールです。
受講生1人ひとりの希望に合わせたカリキュラム提供が魅力であり、「ITエンジニアに転職したい」「副業で収入を得たい」といった個人の希望にあわせてカリキュラムを設計してくれます。
さらに、受講生の学習完了率は98%を誇り、多くの受講生が最後まで学び終えている様子が伺えます。
そんな侍エンジニアは、資格取得コース・支援も充実しており、エンジニアに関する様々な資格取得に取り組むことも可能です。
プログラミングスクール在学中にスキルを身に付けるだけではなく、資格取得も目指す人は、ぜひ受講を検討してみてください。
※ 下記口コミは、ITスクール情報比較サイト「コエテコキャンパスbyGMO」に投稿された内容を使用しています。

- 40代 男性
- フリーランス
プログラミングを初めたきっかけ、わたしの人生の分岐点
★★★★★
5.0
自分の専属インストラクターがすごくわかりやすく理解しやすいので。

- 30代 女性
- サービス業
とても親切なスクールです。あとは自分がどれだけ主体的に取り組めるか
★★★★★
4.0
・教材が分かりやすい ・困りごとが発生した際もサポート体制が整っているので安心して相談できる ・実案件の獲得をするためのトレーニングを受けることができ、実践的なことが学べる まだ受講し始めたばかりで結果が見えていないため、その分は減点しました。

- 20代 女性
- メーカー/製造業
プログラミングスクールに通って、日々やりがいを感じています!
★★★★★
5.0
インストラクターや面談の方が話しやすく、質問したら丁寧に説明してくれるし分かりやすかったから。

- 30代 女性
- インフラ
素晴らしいSAMURAIエンジニア!やる気と努力で実る夢!
★★★★★
4.0
内容の満足度は高いですが、受講料が高いです。 しかし、やる気により、受講料が取り返せます!
キカガク

未経験からでも6ヶ月で実践的なスキル習得を目指せるのはキカガクです。長期コースを受講すると、1,500以上の講座を無期限で受け放題になります。
加えて今後追加される講座も全て無料です。今すぐに必要でない内容も、将来的に必要になったときに学べます。
最後まで学習できるよう、モチベーション維持に役立つメンタリングによるサポートも用意されています。
学習内容に関する質問の他、勉強方法についての質問や相談も可能です。質問し放題で分からないところを残しません。
dodaの転職支援をキカガク経由で受けられるのもメリットです。ITに特化したキャリアアドバイザーによるサポートを受けながら、身につけたスキルを活かした職場へ転職できます。
※ 下記口コミは、ITスクール情報比較サイト「コエテコキャンパスbyGMO」に投稿された内容を使用しています。

- 40代 男性
- メーカー/製造業
「AI人材育成長期コース」はプログラミング経験がほとんどない方にオススメ!
★★★★★
5.0
プログラミング経験やAI知識がほとんどない方には「AI人材育成長期コース」はとてもオススメです。やはりプログラミングは内容が難しく、習得する内容も多岐に渡ります。私はプログラミング経験がなかったため、特にそのように感じました。本コースは短期間で詰め込むのではなく、長期間かけて知識や技術を自分に落とし込むことを目的としているので、初学者向きだと思います。ただ、内容はかなり本格的でデータ取得からAIアプリ作製までの一貫の流れを学ぶことができ、プログラミング経験がない私でも最終的に実装する力を身につけることができました。途中で詰まってしまった場合でも、Slack上で質問したり、「オンライン講義」で講師と1対1で相談したりできたので、無理なく受講することができました。また受講期間終了後もコミュニティサイトで定期的にイベントが開催されますので、他の受講者の方と一緒にコンペに参加したり、資格や転職について情報交換したりできる点も魅力的です。

- 20代 男性
- アルバイト・接客業
AI人材育成長期コースを楽しめたと感じた一例と学習スタンス
★★★★★
5.0
能動的に参加できる方であればお勧めできます。目標次第で満足度は変わるかと思いますが、「自分で基礎は何とかするからAIの面白いこと、より面白くするアイデアを教えて!」位の気概がよいかと思います。半年といってもやはりゼロからのスタートだと誰でも大変だと思います。実力と、どれだけ時間の確保ができるかだと思います。質問チャンネルや質問を講座の前に丁寧に質問すれば、ちゃんと把握した先生が回答してくださる印象です。講座開始直前になって難しい質問をすると質問ルームが埋まっていたり、分野に詳しい先生が先約で対応できなかったりするので注意は必要かと思います。 講座の内容は3カ月が目安ですが事前に受付を早くすませば、予習期間として早めに勉強できます。カリキュラムよりも予定が遅くなればモチベーションが低下すると感じ、10月スタートの講座を9月から毎日2h前後勉強し11月に終わるくらいでした。早めの学習が持続できたコツかなと感じます。独学の勉強でpython基礎、機械学習の操作はさっさと攻略して、実践的な操作にはつまずきつつ、質問を利用して実践的な内容に取り組む時間に当てるくらいがちょうど良かったです。
E資格取得に必要な勉強時間
Study-AIの調査によると、E資格を受験した88%以上の人が100~300時間勉強していることがわかっています。「あなたの勉強時間を教えてください」という問いに対して、「100~200時間」と回答した人は45.59%、「200~300時間」と回答した人は42.65%でした。

上記の結果から、プログラミング初心者は、6か月以上の準備期間が必要だと考えられます。
期間を短くしたい場合は、毎日の勉強時間を増やすのが賢明でしょう。
E資格は意味ない?実務に活かせる知識を身につけよう
当記事では、AIやディープラーニングに興味を持っている人に向けて「E資格は意味ない」と言われている理由とその実態について、詳細に解説してきました。まだまだ知名度が低かったり、一筋縄ではいかない難易度だったりと「やめとけ」「意味ない」と言われてしまう要因が少なからずあることは確か。
しかし、AI人材の重要性がどんどん高まっている昨今において、AI開発に必要な知識を体系的・網羅的に学べるE資格は、十分に魅力的な資格と言えるでしょう。
経済産業省もAI・IT人材不足に警鐘を鳴らしている今、AI人材の需要が益々増大していくことはほぼ間違いないでしょう。
AI業界で活躍していく知識・技術を身につけたいなら「意味ない」なんて声は気にせず、E資格に挑戦してみてはいかがでしょうか。
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
プログラミングの適性診断ができるおすすめサイト5選
IT全盛の現代において、急速に需要を高めている「プログラミング」。2030年までにIT人材が約80万人規模で不足するとの情報も出ているほど、今そのスキルが重宝されています。挑戦したい気...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
IT人材不足はなぜ?経済産業省のデータで徹底解説
IT人材は2030年には最大で79万人不足すると経済産業省が発表しています。 世界中におけるデジタル環境が加速化する中で、日本が後れをとらないためにも必要とされるIT人材の育成は急務...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
E資格の難易度は?勉強時間・合格率について徹底解説
人工知能(AI)やディープラーニング技術の高まりを受け、近年注目を集めている「E資格」。E資格取得に向けてこれから勉強を始めようと考える人にとって、具体的にどのくらいの勉強時間が必要か...
2025.10.29|コエテコ byGMO 編集部
-
E資格認定プログラムおすすめ講座4選を徹底比較【2026年最新版】
AI技術が進化し生活が便利に豊かになるなか、AI、とりわけディープラーニング分野の認定資格である「E資格」が注目されています。E資格には「JDLA認定プログラム」の受講が必須ですが、こ...
2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部
-
プログラミングが学べるIT専門学校おすすめ3選!進学するメリットも解説
2030年には最大79万人もの人材が不足すると報告されていることもあり、IT業界ではエンジニアの採用が急務とされています。実務経験なしで応募できる未経験可の求人も増えていることから、I...
2025.11.13|コエテコ byGMO 編集部