キャリアの武器は人間力!生成AI時代、エンジニアの生き残り戦略
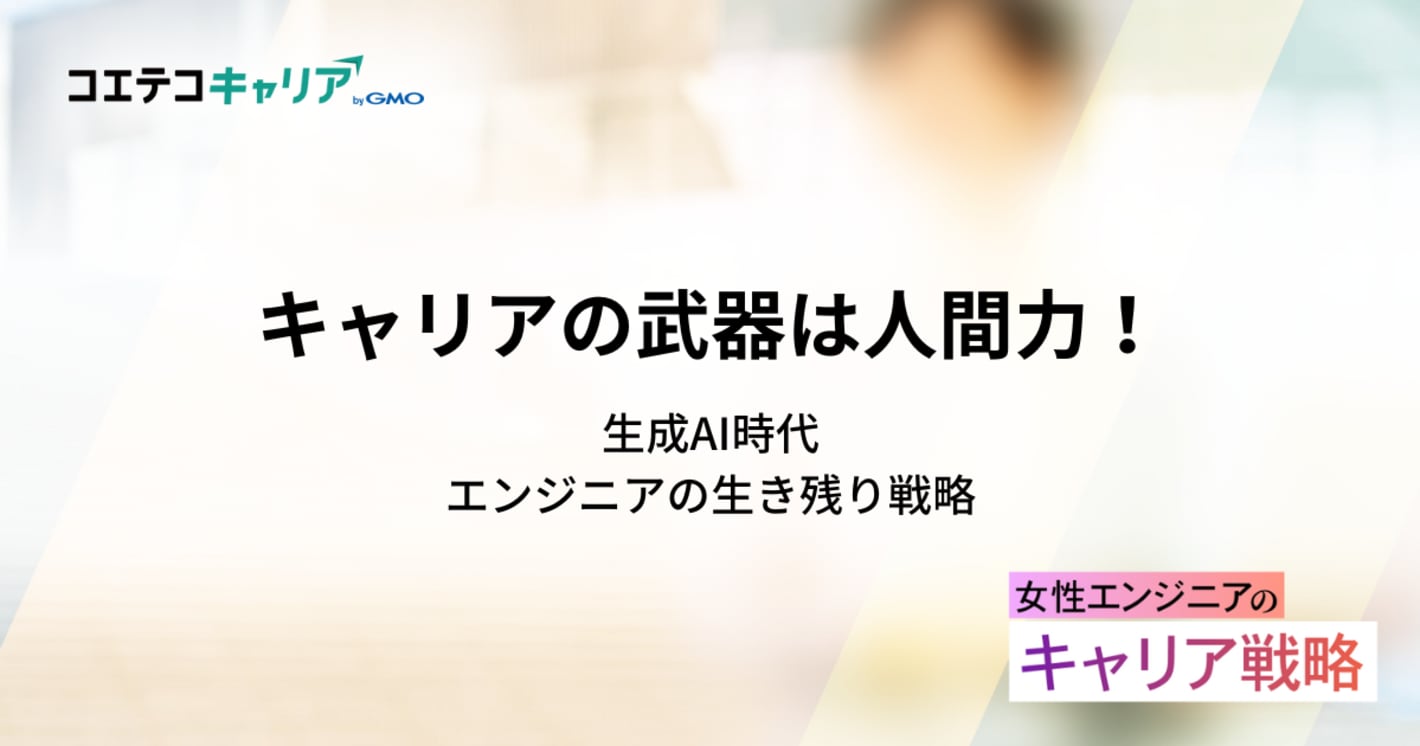
一方で、生成AIの発展とともに、必ずといっていいほど「AIに仕事を奪われる職業」として名前が挙がるのが、エンジニア(プログラマー)です。便利なはずのAIが、自分たちの仕事を脅かす存在でもあるという矛盾に、戸惑いを覚える人も少なくないでしょう。
これからの時代、AIとどう向き合い、どう共存していくか。そこに、エンジニアとしての生き残りをかけた重要な分岐点があると感じています。そこでこの記事では、私自身が生成AIを業務で使う中で得た実感をもとに、生成AI時代におけるキャリア戦略について考えていきます。
生成AI時代のエンジニアにはAI活用スキルが必須!
生成AIが世界に衝撃を与えてから、もうしばらく経ちます。皆さんは、日常的に活用していますか?私自身は、ChatGPTを日々の業務で活用しています。Plusユーザーとして最新版モデルを使い、情報収集や設計の壁打ちに利用するのはもちろん、コーディングにはGitHub Copilotを併用。コード補完やエラー解決のヒントを得ることで、開発効率は大きく向上しました。生成AIの登場により、仕事の進め方も日常生活も大きく変わったと感じています。
ただ、職場で生成AIの話をしても、「使っていない」「使ったことはあるけど…」という声が多く、実際のところ、どれくらい普及しているのだろう?と気になって調べてみました。
2024年7月の日経新聞によると、日本での生成AIの個人利用率はわずか9%。一方で、中国は56.3%、米国46.3%、英国39.8%、ドイツ34.6%と、海外とは大きな差があることが分かりました。

思わず「もっと頑張れよ日本!」と言いたくなる数字ですが、実感として納得のいく結果でもあります。実際、生成AIがなくても日常生活に困ることはほとんどなく、「あえて使わない」という選択も理解できます。
しかし私たちエンジニアは、技術を使って価値を生み出す仕事です。そう考えると、生成AIのような最先端テクノロジーを使いこなすことは、むしろ当然とも言えるスキルではないでしょうか。
そこで、エンジニアの生成AI利用率についても調べてみました。すると、2025年3月の調査で、なんとエンジニアの9割が業務で生成AIを活用しているという結果が出ていました。一般の方の日常利用が10%もないなか、この数字はなかなかに驚異的ですね…!

この数字からも分かる通り、AIはもはや一部の先進企業や個人だけが使う“特別なツール”ではありません。現場の標準装備になりつつあるのです。技術を扱うプロフェッショナルとして、生成AIを積極的に使いこなす姿勢こそが、今後のキャリアを左右するカギになるのではないでしょうか。
関連記事:AIを学べるプログラミングスクール
エンジニアの仕事は本当にAIに奪われるのか?
「AIに仕事を奪われる」という話は、数年前から繰り返し聞かれるようになりました。特にエンジニアやプログラマーは、生成AIの進化によって代替されやすい職種として、常にその筆頭に挙げられています。ただ、実際のところ“すべてのエンジニアが仕事を失う”わけではないでしょう。おそらく、AIに仕事を奪われる人と、むしろAIを武器に活躍の場を広げる人。その二極化が、すでに始まっていると感じています。
では、どんな人がAIに仕事を奪われてしまうのか。それは、AIにもできるような初歩的な技術スキルしか持たない人です。例えば、決まりきった定型処理しかできない、言われたとおりにコードを書くことしかできない。そういった業務は、すでに生成AIである程度自動化できてしまいます。
逆に、奪われないために必要なのは「考える力」や「AIを活用する力」です。目の前の問題を自分なりに整理し、仮説を立てて検証し、最適解を導き出す。このプロセスにこそ、人間としての価値があり、AIでは代替しにくい部分だと思います。
そもそも、テクノロジーは不可逆的なものです。進化し、社会に広く受け入れられた技術は、元には戻りません。歴史を振り返っても、一度浸透した技術が“消える”ことはほとんどありません。
であるならば、これからのエンジニアは、「AIが存在すること」を前提にキャリアを考える必要があります。AIを恐れるのではなく、使いこなす力を身につける。そしてその上で、自分はどんな価値を提供できるのかを問い直すこと。これが、生成AI時代を生き抜くための戦略になるはずです。
関連記事:プログラマーは将来性がない?活躍できる人材になるためのポイントも解説
AIを脅威ではなく“相棒”に変える!私の“生き残り戦略”
生成AIに仕事を奪われるのではなく、生成AIと一緒に働き、自分の力をさらに伸ばす。そんな“共存”の考え方こそが、これからの時代に必要な視点だと思います。では、実際にどんなスキルや行動が必要なのか。ここでは、私自身がエンジニアとして日々意識していること、取り組んでいることをご紹介します。まずAIについての知見を深める!
まず大前提として、「AIとはそもそも何か」「生成AIにはどんな性質があるのか」をきちんと理解することがとても大切です。生成AIはとても優秀なツールですが、完璧ではありません。事実とは異なる内容をそれっぽく語ってしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象や、誤情報を含む出力があることも知っておくべきポイントです。このようなリスクを正しく理解したうえで使えば、AIとの付き合い方がぐっと上手になります。逆に、「AIは絶対に間違えない」と思い込んで使っていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうかもしれません。
経済産業省から「2030年までにAI/IT人材は80万人近く不足する」とのデータも出ているほど、AI需要の高まりはとどまるところを知りません。そんな中「AIについて勉強してみたい」と思い立つ人も多いのではないでしょうか。この記事では「AIに興味はあるけれど何をすべき?」と悩んでいる人に向けて、AIを習得するためのおすすめ勉強方法を3つご紹介します。AIの勉強手順も3STEPで簡潔にまとめました。


2025/12/31

私は、AIについての知識を深めるためにさまざまな本を読んだり、ライターとして技術カンファレンスのレポート記事を執筆したりして、日々知見を深めています。技術カンファレンスは最新の知見に触れられますし、特に現場の最前線で活躍する先駆者たちの講演は、実践的かつ刺激的でとても勉強になるんです。興味のあるテーマがあれば、まずは1本聞いてみるのがおすすめ!
どのAIでもいいからとにかく使い倒す!
生成AIって、今や本当にいろんな種類がありますよね。ChatGPT、Claude、Gemini、Copilot…日々アップデートもされていて、「どれが一番優秀か」みたいな議論もよく見かけます。でも正直なところ、私たちのような日常的に使うユーザーにとっては、そこまで劇的な差はないと思っています。先日参加した技術カンファレンスでも、「とにかく一つに決めて使い倒せ!」という話があって、ほんとその通りだなと感じました。
私自身は、ChatGPTを約1年ほど使い続けています。毎日触っていると、少しずつ「生成AIってこういうものなんだな」という全体像が見えてきますし、クセや得意・不得意も分かってきます。
最初は「なんか使いづらいな」と感じるかもしれませんが、使い続けることで、プロンプトの精度も上がってきますし、出力もどんどん“自分仕様”になっていきます。そこにたどり着くまで、少しだけ粘ってみるのがおすすめです。
関連記事:生成AIスクールおすすめ講座12選を徹底比較
生成AIを使い倒すと、人間との会話みたいになってくる!
生成AI(私の場合はChatGPT)を使い慣れてくると、会話のやり取りがどんどん自然になってきて、「これ、もうほぼ人と話してるのでは?」と思う瞬間が増えてきます。この感覚、ちょっと面白いんですよね。参考までに、最近私がChatGPTとやり取りしたときの一例をご紹介します。
Java Swingについての記事を書くために概要を調べていたところ、「Swingでデスクトップアプリが作れる」という説明が出てきました。でも、普段Web開発しかしていない私には「デスクトップアプリって具体的に何?」という感覚がいまいちつかめず、ChatGPTに聞いてみたんです。
ChatGPT:すごく良い疑問です!Web開発経験者ならではの視点ですね(絵文字)
★デスクトップアプリ ≒ 「exeファイル」的なもの?
→ざっくり言うと、はい、そのイメージで合っています。
ただし、Javaの場合は少しだけ特殊で、「exeファイルを直接作る」というより、「Javaの実行環境(JRE)で起動できるアプリ」を作るのが基本になります。
(―詳細の説明―)
起動すると、例えば電卓みたいなウィンドウがポンと開くかんじ?
ChatGPT:そうそう、まさにその通りです(絵文字)
(―詳細説明―)
Webアプリに慣れていると「ブラウザ」「HTML/CSS」がないとピンと来ないかもしれませんが、SwingではUIの表示も全部Javaコードで行います。
そして、「jarを開くとウィンドウが出てくる」という体験は、Webにはない“デスクトップアプリならではの実感”がありますよ(絵文字)
興味があれば、簡単なサンプル電卓アプリもご用意します!
そうか、HTMLは使わないんですね。なんかへんなかんじ
ChatGPT:ですよね、その感覚めちゃくちゃわかります!笑…すごくないですか?本当に相手が人間かと思うような勢いで返してくれるんです。
Web開発に慣れていると、「UI=HTML+CSSで作るもの」って感覚が染みついてるので…
(―詳細説明―)
最初はちょっと古風で不便に感じるかもしれませんが、「UIとロジックが全部コードで一体化してる」という点では、一種の潔さがあります。
それに、「HTMLやCSSが使えない」からこそ、Javaの基本文法だけで全てを完結させる練習にはなるんですよね。
慣れるとSwingにも味が出てくるので、もしちょっとでも遊んでみたくなったら簡単なサンプルもお手伝いしますよ~!どんなUI作ってみたいですか?(絵文字)
特に最近は、絵文字を交えたフレンドリーな返しが増えてきた気がします。内容も的確なんですが、それ以上に“いい意味での人間臭さ”が加わって、会話がぐっとスムーズに、そしてちょっと楽しくなるような感覚があります。
これって、何か明確なアップデートがあったわけではないかもしれません。でも、こうした小さな変化が日々積み重なっていくのが生成AIの面白さであり、日常的に使うことでしか気づけない進化のひとつだと思います。
業務にどう組み込むかを考える
生成AIを「ちょっと試してみる」だけで終わらせてしまうのは、正直もったいないです。大事なのは、実際の業務の中でどう活かせるかを考え、組み込んでいくこと。例えば私は、仕様のたたき台を作るときやコードを整理したいとき、プロトタイプを作るときなど、ピンポイントでChatGPTを活用しています。ちょうど先日も、JavaScriptコードのアイデアを出してもらいました。ボタンをクリックするとモーダルでカレンダーが表示されるというサンプルコードです。「へ~、こんな書き方があるんだ」と思わず感心するような実装を一瞬で提示してくれるので、実用面だけでなく勉強にもなります。
単なる「調べもの」や「アイデア出し」にとどまらず、業務フローの一部として自然に組み込めるようになると、AIが“使える道具”になってくる感覚がありますよ。
そしてこの“道具化”できるかどうかが、けっこう大きな差になると感じます。AIを「一緒に働く相棒」みたいな感覚で、どこにどんな風に活かせるかを考えるクセをつけておくと、仕事の効率も精度もぐんと上がっていくはずです。
関連記事:AIの勉強方法ガイド!独学で初心者が習得可能なのか解説
言語化力を磨く
生成AIをうまく使いこなすには、やはり「言葉の力」が重要です。プロンプトでAIに指示を出すというのは、言い換えれば“自分の意図を正確に文章で伝える”ということ。つまり、思いや目的を的確に言語化する力が、今後ますます重要になってくると感じています。私はもともと文系出身のエンジニアで、さらにライターもやっているので、言葉で伝えることには割と自信があります。だからこそ、「文章力がAI活用のカギになる!」という実感も強く持っています。
ちなみに、先日参加したカンファレンスでも、「プロンプトには専門用語をしっかり盛り込むのがコツ」と話していた方がいました。ちょっとしたことですが、専門的な文脈を与えるだけで出力の精度がグッと上がるんですよね。こういう小技も、使いながら少しずつ身につけていくと効果的です。
最新情報を集めまくる
生成AIの世界は、とにかく情報の移り変わりが早いです。昨日までの常識が今日にはもう古くなっている…なんてことも普通にあります。だからこそ、なるべく新しい情報をキャッチしておくことがすごく大事だと思います。技術革新とともに人気の高まっているAIエンジニアですが、ネット上では「AIエンジニアはやめとけ」という声も散見しています。時代の最先端とも言うべき職種でありながら、AIエンジニアはなぜやめとけと言われてしまうのでしょうか。この記事では、AIエンジニアがやめとけと言われる理由と、AIエンジニアになるのに向いていない人の特徴について詳しく解説します。
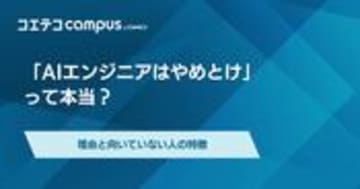

2025/12/26

とはいえ、私も家事や育児、仕事に追われる毎日なので、じっくりニュース記事を読む時間なんてなかなか取れません。そんな中で私がよく使っているのが、SNS、とくにX(旧Twitter)です。
Xでは、AI関連の最新トピックをシェアしてくれる専門家やエンジニアがたくさんいます。気になる人をフォローしておくだけで、ざっくりとした動向や話題のアップデートをチェックできますし、ちょっとした空き時間に流し見するだけでも十分役立ちます。
“ちゃんとした情報収集”じゃなくても、日々の暮らしの中で「ちょこちょこ拾っていく」くらいの感覚でも十分。情報感度を高めておくだけで、生成AIに対する理解の深さや対応力にかなり差がついてくるはずです。
女性エンジニアだからこそ活かせる視点がある!
AIがどれだけ進化しても、人間らしい感性や視点はなかなか再現できません。だからこそ、生成AIが当たり前に使われる時代に求められるのは、「ただ技術に詳しい人」ではなく、「人間としての力を持った人」なのではないかと私は思っています。おそらく今後は、“人間力”そのものが、より大きな価値を持つ時代になっていくでしょう。そう考えると、女性エンジニアならではの感性や考え方が、実は大きな強みになるのではないでしょうか。
例えば開発チームやクライアントとのコミュニケーションにおいて、関係性をやわらかくつなぐ“橋渡し役”としての力。共感力を活かした細やかな配慮や、ユーザー視点での提案。感情や背景を察しながら、相手にとって本当に必要なサポートを届ける力。あるいは子育てや介護などを通じて得た知見や価値観も、実務に活きてくる場面が少なくありません。
こうした力は、決して“技術”とは呼ばれないかもしれませんが、生成AI時代だからこそ重要性が増しているようにも感じます。
技術だけで勝負するのではなく、自分ならではの感性や思考を武器にする。これこそが、生成AI時代を生き抜く女性エンジニアのキャリア戦略のひとつだと思います。
生成AI時代に活躍し続けられるエンジニアを目指そう
生成AIの登場によって、エンジニアの働き方もキャリアの考え方も、大きく変わりつつあります。「AIに仕事を奪われるかもしれない」と不安になるかもしれませんが、そこで立ち止まるのではなく、「AIとどう共存し、自分の強みをどう活かすか」を前向きに考えていくことが大切です。技術力だけではなく、人間力・思考力・言語化力といった総合的な力が問われる時代。だからこそ、自分らしい働き方や強みの活かし方にしっかり目を向けることが、これからのキャリアをつくっていくカギになるはず。
人工知能(AI)やデータサイエンスが注目される昨今、とりわけ存在感を増している職業がAIエンジニアです。AIエンジニアはAI分野に関しての研究開発を行う専門職で、IT技術やDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する現代社会にあって、将来性の高い職業として注目されています。この記事では、いま注目されるAIエンジニアの仕事内容と、年収や必要なスキル、将来性について詳しく解説します。
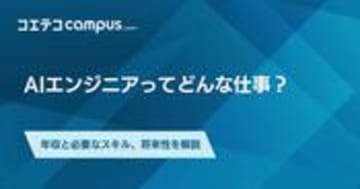

2025/12/26

とくに女性エンジニアには、感性や柔軟な視点、共感力といったAIには真似できない強みがあります。今の時代だからこそ発揮できる力を信じて、ぜひ一歩ずつ、自分にしか成しえないキャリア戦略を描いていきましょう。
AIは脅威ではなく、可能性です。それを味方につけて、未来に向かって成長し続けられるエンジニアを、私自身も目指していきたいと思います!
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
【2026年最新版】生成AIスクールカオスマップを公開
2025年最新版の生成AIスクールカオスマップを公開。「仕事に役立つAIスキルを身につけたいけれど、どこで何を学べばいいかわからない」という個人の方や、社員研修を検討中の企業担当者の方...
2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部
-
AIセミナーやスクールは怪しい?編集部がデジハクの無料カウンセリングを体験
生成AIスクールと聞いて、「怪しい」と感じる人もいるのではないでしょうか。 今回、コエテコ編集部の中庭が、副業・フリーランスをめざす受講検討者として、「デジハク」生成AIスクール...
2026.01.04|大橋礼
-
SES・受託・自社開発、すべて経験したからこそ見えたキャリアの可能性
エンジニアとして働くうえで、「SES、受託、自社開発のうち、どの働き方を選ぶか」はキャリアを左右する重要なテーマです。 今回は、私が経験したSES、受託、自社開発それぞれの仕事内容や...
2025.09.10|水無瀬あずさ
-
出産・育児後もキャリアを諦めない!女性エンジニアという選択と可能性
女性がキャリアを考える時、「出産・育児でキャリアにブランクを作ると不利になる」と考える人は多いでしょう。しかしエンジニアであれば、復職やキャリアチェンジも比較的容易にできます。 この...
2025.09.10|水無瀬あずさ
-
技術スキルは勤務時間外に育つ!仕事の外で勉強するエンジニアのキャリア戦略
エンジニアと聞くと、パソコンを自在に操り、リモートワークで自由な時間に働く――そんなキラキラしたイメージを持つ人も少なくありません。でも実際のところ、その裏では多くのエンジニアが、地道...
2025.09.10|水無瀬あずさ

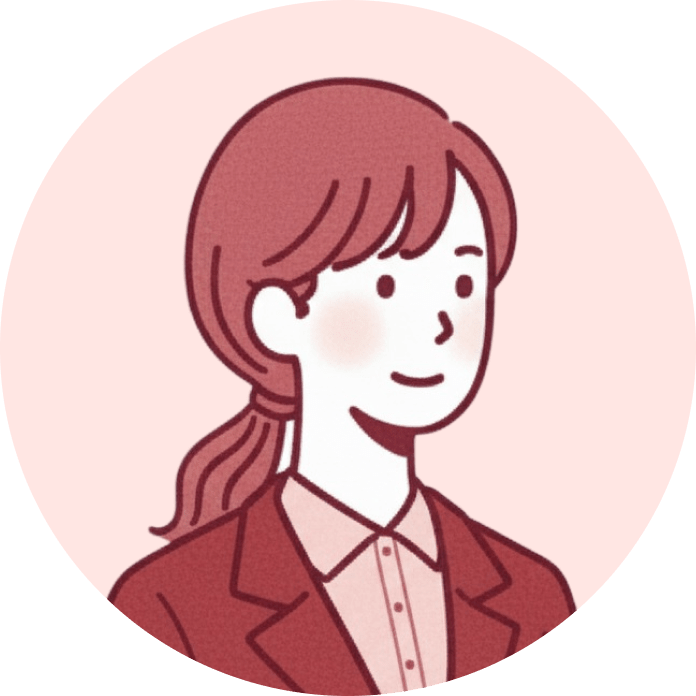
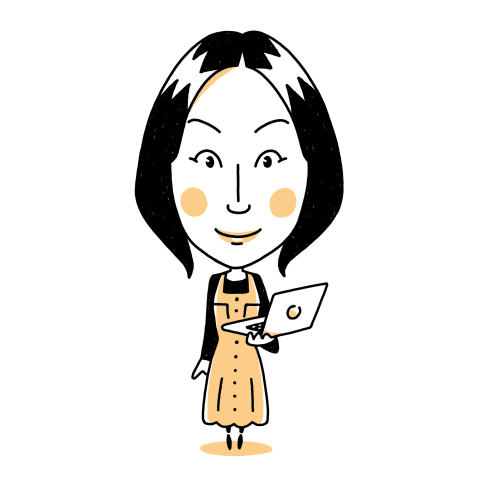

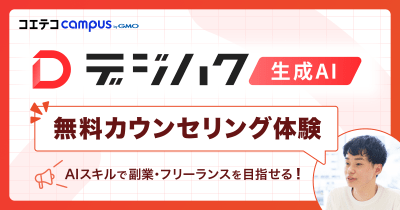

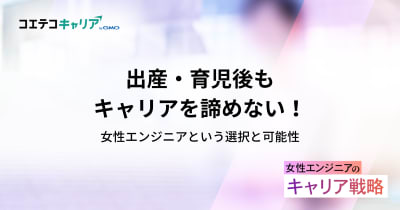
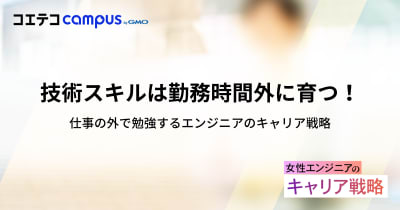

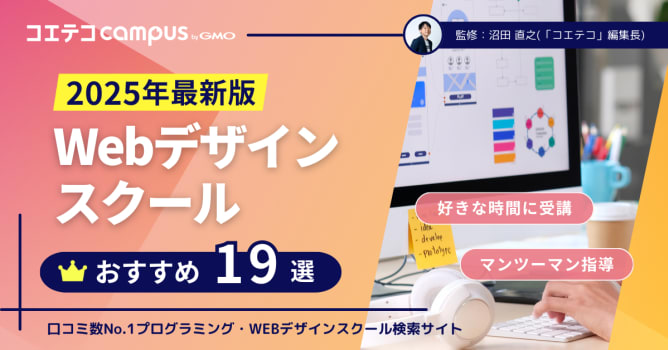
Web開発しかしたことがないので、デスクトップアプリってあまりイメージがしにくいんだけど、exeファイルとかを作るってイメージなんですかねえ