英語が話せないのはなぜ?専門家が解明する構造問題とAI時代の本物の英語力

-
今回お話を伺った方
-
Crimson Education Japan 代表取締役 / 文部科学省中央教育審議会 委員
松田 悠介氏大学卒業後に中学体育教師として勤務し、英語で体育を教える「Sports English」を立案。その後、市川市教育委員会分析官を経てハーバード教育大学院で教育リーダーシップ修士を取得。PwC Japanで人材戦略に携わった後、退職してLearning For Allを設立し、Teach For Japanを創設。教育格差是正に尽力した。スタンフォードで経営学修士を取得後、同大学客員研究員となり、Crimson Education Japan代表取締役およびCrimson Global Academy日本代表として留学・教育支援を展開。ELSA Speak顧問やAwakApp取締役も務めている。さらに、教員養成や教育政策にも関与し、文科省や内閣府の委員を歴任。
-
実はその原因は、個人の努力不足ではなく、日本の英語教育が抱える根深い“構造問題”にあるのかもしれません。
この記事では、中央教育審議会の委員として教育政策の最前線に立つ松田悠介さんにインタビュー。
なぜ私たちは「話せる」ようにならないのか、その構造的なボトルネックを解き明かします。
さらに、AI時代に本当に必要な英語力、そして家庭で子どもの可能性を伸ばすためのヒントまで、未来を見据えた提言を伺いました。

Crimson Education Japan 代表取締役、文部科学省中央教育審議会 委員 松田悠介さん
なぜ、私たちは英語を学んでも「話せない」のか?
日本の英語教育が抱える最大の課題は、「目標」と「制度設計」が連動していないことです。
学習指導要領では「使える英語力」、つまりCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に基づいた四技能の運用力を育てると明確に掲げています。
ところが、実際の評価・指導・人材育成、そして何より入試制度が、その目標と整合していない。
ここに大きな構造的なギャップが存在します。
構造的なギャップ...!
具体的にはどのような問題なのでしょうか?
はい。その構造的不整合の根源には、主に4つのボトルネックがあります。
①入試制度が「読む・聞く」に偏っていること。
最も大きな要因は、大学入試の「ウォッシュバック効果」です。
全国規模の共通テストが「読む・聞く」中心のため、学校や生徒の学習も自然と試験対策に最適化されてしまいます。
評価が変わらない限り、授業も本質的には変わりません。
②大人数・一斉型の授業形態。
日本の学級規模はOECD諸国と比べても大きく、1クラス35〜40人という環境では、生徒一人ひとりの発話量を十分に確保するのは物理的に困難です。
結果として、英語を「使う」トレーニングが圧倒的に不足してしまいます。
③教員の英語運用力・指導力のばらつき。
高校段階でCEFR C1レベル以上の高度な英語力を持つ教員は約2割にとどまります。
教員の英語力や英語で授業を運営するスキルが体系的に育成されていないため、指導の質に大きな差が生まれているのが現状です。
④学校現場のKPI(評価指標)とのズレ。
学習指導要領は「使える英語」を掲げても、学校が実際に評価されるのは筆記試験の点数や進学実績です。
そのため、スピーキングやライティングに時間を割くより、点数を取りやすい筆記中心の授業が優先されがちです。
つまり、政策と現場の目標が一致していないのです。
個人の努力や先生方の工夫だけでは乗り越えられない、制度的な課題が複雑に絡み合っているのですね。
この状況を打破するには、どこから手をつければよいのでしょうか...?
これらの構造的課題を放置したままでは、どんなに教科書を新しくしても「使える英語力」は身につきません。
解決のためには、「評価・授業・教師力」を三位一体で再設計する必要があります。
まずは、評価を先に変えること。
大学入試において、CEFR準拠の外部検定や、標準化されたスピーキング・ライティング評価を選択肢として段階的に導入し、「四技能を測る」という明確な方向性を示すことが重要です。
次に、授業条件の再設計。
学級規模の縮小やチームティーチング(TT)を推進し、生徒一人ひとりの発話時間を増やす。
タスク・ベースド・ラーニング(TBLT)のような実践的な指導法を、教員研修に標準で組み込むべきです。
そして、教師力の底上げ。
教員がCEFR B2〜C1レベルの英語力に到達できる研修ロードマップを制度として整え、能力向上へのインセンティブを明確にする必要があります。
この3つの歯車を同時に噛み合わせていくことこそが、日本の英語教育改革を次のステージへ進める鍵だと考えています。
「静かな優秀さ」から「発信する優秀さ」へ ― 世界が求める日本人像
英語教育の課題と同時に、日本の若者の「内向き志向」も指摘されます。
留学や海外大学への進学の現状を、どのようにご覧になっていますか?
日本の若者の海外進学は、パンデミック後にゆるやかに回復していますが、世界全体の留学生増加率から見れば、日本は明らかに出遅れています。
一方で、海外大学から見た日本の学生への評価は非常に高い。
誠実さ、勤勉さ、協調性は世界的に知られています。
しかし同時に、「正解を出す力」はあっても、「問いを立てる力」や「自分の意見を言葉で伝える力」が弱い、という課題を突きつけられるのが現実です。
たしかに!
勤勉さは評価される一方で主体性や発信力に課題があるのは、多くの日本人が感じることかもしれません。
海外の大学は、他にどのようなことを期待しているのでしょうか?
はい、まさにそこが重要なポイントです。
近年、海外大学が日本の学生に期待するのは、単なる学力ではありません。
日本の食文化、ものづくり精神、アニメといったソフトパワーへの関心が高まる中で、大学側は単に英語ができる留学生ではなく、“Japan Representative”として自国の文化的ルーツを世界に伝え、異文化と橋渡しできる人材を求めています。
今、日本の若者に求められているのは、“Silent Excellence(静かな優秀さ)”から“Engaged Excellence(関与し、発信する優秀さ)”への転換です。
静かに優秀であるだけでなく、積極的に対話し、社会に自分の視点を発信する。
その姿こそ、世界の大学が最も待ち望んでいる日本人像なのです。
より多くの若者がそうした人材になるために、国や社会はどのようなサポートをすべきでしょうか?
特に「行きたいけれど行けない」という声も多く聞かれます。
国として必要なのは、「留学を特別なことにしない社会的仕組み」をつくることです。
最大の障壁は、やはり経済的ハードルです。
海外大学の学費と生活費は、多くの家庭にとって現実的な額ではありません。
これを解決するために、公的な給付型奨学金の拡充や、卒業後の所得に応じて返済できる教育ローンの制度設計が急務です。
「能力と意欲がある限り、誰でも挑戦できる社会」をつくることが大前提です。
さらに、日本に欠けているのが「帰国後のエコシステム」です。
海外で学んだ若者が戻ってきたとき、その経験を社会に活かせる職場やネットワークがまだ不十分です。
企業・行政・大学が連携し、海外大卒業生が国内外を自由に行き来しながら活躍できる仕組みを構築する必要があります。
海外進学を一部の特別な層の話にせず、「誰もが挑戦できる構造」に変えていくこと。
それが、次の時代の日本の若者が世界で活躍するための土台になると考えています。
なるほど...!
公的な給付型奨学金といえば、文部科学省が主導している「トビタテ!留学JAPAN」がありますね。
返済不要の奨学金プログラムを導入し、留学に挑戦する高校生や大学生等のサポートを行っているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
文部科学省の「トビタテ!留学JAPAN」は、官民協働で日本の高校生・大学生を支援する奨学金プログラム。約1万人以上を世界に送り出した実績を持つこのプログラムについて、プロジェクトディレクターの荒畦悟氏に詳しくお話を伺いました。


2025/08/29

AI時代だからこそ価値が高まる「本物の英語力」とは?
近年、AIによる自動翻訳の精度が飛躍的に向上しています。
そんな時代に、私たち人間が身につけるべき「本当に使える英語力」とは、どのようなスキルだとお考えですか?
AIが進化する中で求められるのは、単なる「正確な英語」ではありません。
英語を “information tool(情報伝達の道具)”としてではなく、“thinking tool(思考の道具)”として使えるかどうかです。
AIが事実を翻訳し、文章を生成してくれる時代だからこそ、人間に求められるのは、「何を伝えるか」「なぜそう考えるか」「どんな価値を加えるか」という発想・構築・対話の力です。
AIが「How(どう伝えるか)」を担うからこそ、人間は「What(何を)」「Why(なぜ)」の部分で価値を発揮すべきだ、ということですね。
ただ、それも翻訳機を介して伝えれば良い、という考え方もあるかと思います。
どれだけAIが発展しても、翻訳機越しのコミュニケーションには限界があります。
翻訳された言葉は意味を伝えても、その人の「熱量」や「意図」、そして「間(ま)」までは伝えきれません。
私自身、スタンフォード大学のビジネススクール時代や、現在のグローバル企業での経験から断言できますが、同時通訳機を介して多国籍チームの複雑な意思決定がスムーズに進むとは到底思えません。
議論のテンポ、相手の表情、微妙なユーモア──そうした「非言語の文脈」こそが信頼を築く鍵だからです。
つまりAI時代の「英語力」とは、単なる語彙や文法の正確さではなく、相手と信頼関係を築き、協働できる“関係構築の言語力”を意味します。
AIが言語の壁を下げたからこそ、人間同士が“信頼”を介して対話できるかが、真の競争力になるのです。
そう考えると、AIの登場で英語学習の価値が失われるどころか、むしろ「人間ならではのコミュニケーション力」を磨くという意味で、その重要性は増していると言えそうですね!
はい。AI時代に私たちが英語を学ぶ価値は、三つあると考えています。
一つ目は、「思考の幅を広げる」ため。言語は思考のフレームです。
英語で考えることで、日本語だけでは得られない視点や発想が生まれます。
二つ目は、「信頼と共感を築く」ため。
直接相手の言語で語りかける“human touch”こそが、グローバルな環境で最も大きな差を生みます。
三つ目は、「グローバルに発信する主体性を持つ」ため。
AIに翻訳を任せるのではなく、自分の言葉で世界の議論に参加できること。
そこにこそ、英語を学ぶ最大の意義があります。
家庭でできる最大の支援は「世界を面白いと思わせる」こと
お子様の英語教育について、多くの保護者が悩んでいます。
「早く始めないと」「ネイティブのように話せるように」といった焦りを感じる方も少なくありません。
ご家庭でできる、最も重要なサポートとは何でしょうか?
保護者が果たすべき最も重要な役割は、「英語を目的化しない環境をつくること」です。
「英語を勉強すること」がゴールではなく、「英語を通じて世界とつながる」「自分の世界を広げる」ための手段として位置づける。その視点が何より大切です。
英語は「早く始めた人が勝つ科目」ではなく、「長く関わり続けた人が伸びる言語」です。
そのためには、子どもが「英語=楽しい」「世界とつながれるツール」と感じるポジティブな感情体験が不可欠です。
スキルよりも「楽しい」という感情を育むことが、結果的に持続的な学びに繋がるのですね!
ただ、日本の英語教育は「間違いを恐れる文化」が強いように感じます。
家庭ではどうすれば良いでしょうか?
おっしゃる通り、日本の英語教育は「完璧主義」と「減点主義」に陥りがちです。
学べば学ぶほど間違いを指摘され、自己肯定感が下がってしまう。
だからこそ、家庭では絶対にその「減点の文化」を再現してはいけません。
むしろ、「間違えてもいい」「通じたらOK」という温かい空気、つまり「失敗を恐れない文化」を意識的につくることが、最も大切なサポートです。
考えてみてください。
海外の方がたどたどしい日本語で話しかけてきたとき、私たちは完璧な文法を期待しますか?
一生懸命伝えようとする姿に好感を持ちますよね。
おっしゃる通りです...!
英語もまったく同じです。大事なのは、伝えようとする勇気と態度です。
親が完璧でなくても堂々と英語を使う姿を見せる。
子どもが間違えても笑わない。そうした環境があれば、子どもは自然と「英語を使うことは怖くない」と思えるようになります。
英語教育の本当の目的は、「英語ができる子」を育てることではありません。
「世界に向かって自分の言葉で語れる子ども」を育てることです。
そのために家庭でできる最大の支援は、「学ばせる」のではなく、「世界を面白いと思わせる」ことなのです。
英語は、世界と自分を知るための「鍵」
様々な課題と可能性についてお話しいただきましたが、松田さんがその先に描く、日本の英語教育の“あるべき姿”をお聞かせください。
私が目指すのは、日本が「英語を学ぶ国」から「英語で学び、英語で発信する国」へ転換することです。
英語が特別なスキルではなく、思考と対話の共通言語として社会に溶け込んでいる。
子どもたちが「受験のため」ではなく、「世界を理解し、自分の言葉で語るため」に学ぶ。そんな未来を創りたいと考えています。
グローバルに挑戦することは、「日本を捨てる」ことではありません。
むしろ、海外に出ることで日本の文化や社会の素晴らしさといった「当たり前の中の価値」に気づき、それを世界につなぐことなのです。
英語は、そのための「鍵」であり、同時に世界の一員としての「責任」を引き受けるための言語でもあります。
ですから、私が描く未来の英語教育とは、英語を通して「自分を知り、世界とつながり、社会を変えていく力」を育むこと。
この力を持つ若者が増えたとき、日本は本当の意味でグローバルな国になると信じています。
最後に、これからの時代を生きる子どもたち、若者、そして彼らを支える大人たちへ、それぞれメッセージをお願いいたします!
子どもたちへ。
これからの時代は、どんなにテクノロジーが進化しても、「自分の言葉で語れる人」が一番強いです。
完璧でなくていい。間違えてもいい。
世界のどこにいても、自分の思いを伝え、誰かとつながる勇気を持ってください。
英語は、あなたの世界を広げる“鍵”であり、同時に自分の中の可能性を開く“鏡”です。
その扉を開ける勇気を、持ち続けてほしいと思います。
若者たちへ。
世界は、あなたが思っている以上に、あなたの声を待っています。
海外大学進学も、留学も、国際的な挑戦も、特別な人だけのものではありません。
世界に出るとは、「自分の外側の世界を知ること」ではなく、「自分の内側を深く知ること」。
その過程で出会う人や経験が、あなたの生き方を形づくっていきます。恐れずに、一歩を踏み出してください。
そして、保護者・教育者の皆さんへ。
子どもたちにとって最も大きなギフトは、「安心して挑戦できる環境」です。
結果を求めすぎず、過程を認める。できた・できないではなく、「やってみた」ことを喜ぶ。
そうした日常の言葉が、子どもの心に“挑戦の灯”を灯します。私たち大人ができる最大の教育は、「挑戦する背中を見せること」です。
日本の未来を変えるのは、制度でもテクノロジーでもなく、一人ひとりの勇気ある学びの選択です。
その積み重ねが、英語を“受験の科目”から“共通の世界語”へと変えていく。
そして何より、学ぶことを通じて「日本から世界へ、世界から日本へ」と往来する人材が当たり前に育つ社会を、次の世代と一緒につくっていきたいと思います。
ありがとうございました!
松田さんは海外進学塾「Crimson Education Japan」の代表取締役、およびオンラインのインターナショナルスクール「Crimson Global Academy」日本代表としてご活躍されています。
ご自身のハーバード大学留学体験をまとめた著書「グーグル、ディズニーよりも働きたい「教室」(ダイヤモンド社)」も出版。
さらに、海外進学や国際教育情報をX(旧Twitter)でも積極的に発信されています。
気になる方はぜひチェックしてみてください!

WRITERこの記事を書いた人
英語学習ガイド
-
おすすめオンライン英会話
-
おすすめ英語コーチング
-
おすすめ英会話スクール
-
英語の勉強法
-
英語学習Q&A
-
海外で英語を学びたいと思ったら
-
コエテコ編集部ライターによる体験談
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
社会人の英語習得に必要な勉強時間は?専門家が継続のコツと成果の出し方を徹底解説
「英会話レッスンに通っているのに、なぜか話せるようにならない」「忙しくて学習時間が確保できない」。その原因は学習の「やり方」と「続け方」にあるのかもしれません。今回は、英語コーチング「...
2026.01.30|コエテコ byGMO 英語編集部
-
コーチバディ(旧スピークバディ パーソナルコーチング)|1日1時間で「話せる」を目指せる!スピーキング特化型の英語...
英語を「話せる」ようになりたいなら、スピーキング特化型英語コーチングの「スピークバディ パーソナルコーチング」がおすすめです。高い英語力・スピーキング力を持つコーチが、あなたが話せるよ...
2025.11.17|安藤さやか
-
(取材)スマートメソッド®|オンライン英会話発!「話せる」英語を目指せる英会話コーチングとは?
スマートメソッドは、オンライン英会話「レアジョブ」と同じ運営会社が提供する、英語を「話せる」ようになるための英会話コーチング。スピーキング力の向上に特化したサービスで、場面に合わせて適...
2025.06.11|安藤さやか
-
【インタビュー後編】新しいオンライン英会話をめざす学研のオンライン英会話Kiminiの魅力とは?【ビジネス編】
学研のオンライン英会話Kiminiを運営する株式会社Glats代表取締役社長の杉原聡さんにインタビュー。 2回目は、主にビジネスユーザー向けに、他のスクールとどこが違うのか。「ネット...
2025.11.17|YOSHIHASHI
-
IELTS対策はミニマムに?英語教育エキスパート嶋津幸樹さんが教える、IELTSの本当の価値とは
IELTS対策はミニマムに?スコアを上げるだけでなく、将来にも活きる本質的な英語力の身につけ方を、英語教育の専門家・嶋津幸樹さんに徹底解説していただきました。
2025.04.24|高山志帆


































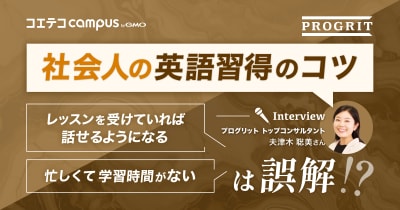





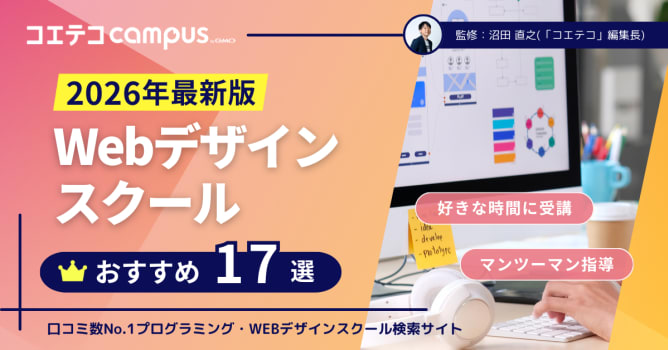
多くの子どもたちが小学校から英語を学び始め、中学・高校と合わせれば10年近く英語に触れています。
それにもかかわらず、「英語を話せない・使えない」という課題が、なぜ長年解決されないのでしょうか?
中央教育審議会の委員というお立場から、その根本的な原因を教えてください。