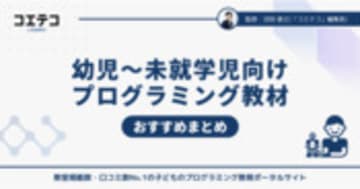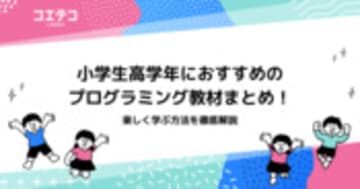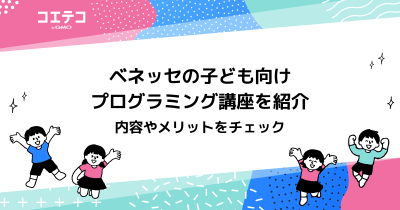ロボットプログラミング教材おすすめ23選【2026年最新版】

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
プログラミング教材といっても種類が豊富で何を選べばいいのかわからない、とお困りの保護者の方も多いのではないでしょうか。
そこで、「レゴブロックが好き!」「動くおもちゃが好き!」「工作が好き!」というお子さんにおすすめしたいのがロボットプログラミング教材です。
この記事では、小学校低学年からロボットで楽しみながらプログラミングを学べるおすすめロボットプログラミング教材についてくわしく解説します。ぜひ参考にしてください。
なんでプログラミングに注目が集まっているの?
2020年に小学校でプログラミング教育が必修化されたことはご存知ですか?『日本再興戦略 2016』で義務教育におけるプログラミング教育の必修化が明記され、2017年に文部科学省が発表した「新学習指導要領」で小学校でのプログラミング教育が必修化されることが決まりました。
そういった背景もあり、『プログラミング』に注目が集まっています。
ロボットプログラミングとは?
ロボットプログラミングとは、その名の通り、「ロボットを活用してプログラミングを行うこと」です。プログラミング教育の必修化で注目が集まる「プログラミング」ですが、もしプログラミングがわからない状況で始めるとしたら、ロボットプログラミングがおすすめです。ロボットは、「既に用意されているもの」や「自分で組み立てるもの」などさまざまですが、ロボットをプログラミングで動かすと、目に見えて成果が分かるため、子どもでも飽きずに続けられます。
子どもが楽しみながらプログラミングを学べる、おすすめロボットプログラミング教材23種類を詳しく紹介します。
おすすめロボットプログラミング教材23選
最近では、たくさんのプログラミング教材が販売されており、ロボットプログラミング教材も充実しています。プログラムを組んでロボットを動かすことができ、また商品によってはロボットのパーツを組み立てる段階から制作をはじめることができます。さらに教材によっては、実際にコードを記述する実践的なプログラミング言語を学ぶことができたり、IoT(Internet of Things)を利用したプロダクト製作を行えたりするものもあります。
「ソビーゴ RP1」(対象年齢:8歳〜)
こどもプログラミング | ソビーゴ | 遊びごころで未来をつくる

https://hello-sovigo.com/ >
子ども向けパソコン「IchigoJam」を使用して、ダンボールでできたロボット「ソビーゴ」を動かすことができるプログラミングロボット教材です。
プログラミングで動かすことができるロボットがダンボール素材のため、子どもでも組み立てることができ、ボディや頭などに好きな絵や文字を書くこともできます。走らせたり、踊らせたりすることができるので、ロボットに興味のあるお子さんにぴったりです。
「KOOV(クーブ)」 (対象年齢:8歳〜)
ソニーのKOOV(クーブ)を使用する成長率No.1の小学生・子ども向けプログラミング教室。全国1,000以上の教室で無料体験授業のお申込を受付中。

https://www.koov.io/ >
ソニー・グローバルエデュケーションが学校教材を扱うアーテック社と共同開発した、プログラミングロボット教材です。カラフルなブロックを組み立てて動物や乗り物など好きなものを作り、プログラミングで動かします。
「じゆうせいさく」「ロボットレシピ」「がくしゅうコース」の3つのアプリが用意されています。お子さんの年齢、レベルによってアプリを選択することができます。「じゆうせいさく」を選ぶと、自分で組み立てたロボットが動いている様子を、世界中の仲間に公開することができます。
「Makeblock プログラミングロボット mBot 日本語版」(対象:小学生~高校生)
Makeblock mBot ロボット 子ども電動おもちゃ Bluetoothドングル付き STEM教育キット STEMプロジェクト 子供向け コーディング ロボットキット 学習 教育用おもちゃ 工学 電子工学 スクラッチ 8歳 - 12歳 ギフト プレゼント

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BS6C99RT >
Makeblock社が提供しているプログラミングロボット教材です。
mBot自体は10分程度で組み立てることができるため、よりプログラミング要素の強い教材となっています。ビジュアルプログラミング言語である「Scratch(スクラッチ)2.0」でプログラムを組むことができ、プログラミングが初めてでも簡単にプログラミングが習得できます。
「embot(エムボット)」(対象:小学校3年生〜)
embotは、NTTドコモとインフォディオが開発したロボットプログラミング教材であり、多くの子ども人気を集めています。新たな機能を追加した「embot+」はより拡張性の高い商品に進化し、2023年に販売が開始されました。embotはダンボールでできているため、子どもが自由に組み立てて新しいパーツを足したり色を塗ったりすることができます。
自作したロボットは、タブレットやスマートフォンからプログラミングで操作することができます。
動かす言語はビジュアルプログラミング言語のため、子供はブロックを組み立てるような感覚でプログラミング学習ができます。
「ハブラシロボットキット」(対象:小学生〜)
ハブラシロボットキット

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073R9CLW8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=coeteco-22&linkId=adab64a3a02010347aafa870bb8e8fbd&language=ja_JP >
ユカイ工学が開発したロボットプラグラミング教材キットです。基板がスペースシャトル型になっていて、そこに付属のハブラシを取り付けます。そしてハブラシの振動によってシャトルが走りだす、オリジナリティの高いロボットです。
またiPhone・iPad向けの別売りであるフィジカルコンピューターツールキット「konashi/Koshian」をつなぐとスマートフォンからロボットを動かすことも可能です。
「レゴ(LEGO)マインドストームEV3」(対象年齢:10歳~)
Create and command robots that do what you want with LEGO MINDSTORMS EV3!

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00CWER3XY/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=coeteco-22&linkId=43bfbb5f3db0ad216aefa44912c223b4&language=ja_JP >
LEGOとMITが共同開発したプログラミングロボット教材で、世界70カ国以上、5万以上の教育機関で利用されているプログラミングロボット教材です。好きな形にロボットを組み立てることができるだけではなく、「Python」や「C#」といった様々な言語でプログラムを組むことができます。
「カムプログラムロボット工作セット」(対象年齢:10歳~)
自由にセットできるカムを使って動きをプログラムできるロボット工作。 モーターを2個搭載して三角形のクローラーで進み、左右の腕も動作。 カムを差し込んだプログラムバーをロボットの中央にセット。 内部のギヤでバーを移動させてカムの配列を機械的に読み取り、車体下のステアリングレッグを押し下げて、クローラーを浮かせることで動きを変化。 全長約136mm。基本の動きは2タイプ。 ...

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073S47B11/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=coeteco-22&linkId=98207ba486922107644f01ca28f5fa67&language=ja_JP >
タミヤが販売しているロボットプログラミング教材です。
プログラムバーにカムという動きを制御する部品を取り付けることで、プログラミングを学びます。カムで設定できる動きは2種類で、マイコンボードを取り付ければプログラミング学習をすることも可能です。
「PETS(ペッツ)」(対象年齢:3歳後半〜)
「PETS(ペッツ) 」は木製プログラミングロボットです。PETSは背中の部分にブロックを押し込めることができ、ブロックを押し込むことでプログラムを組むことができます。
マス目の書かれたシートの上でPETSを前進させたり、後ろを向かせたり、障害物を避けさせたりしながらゴールを目指します。押し込んだブロックによって動きがすぐに変わる体験を通して、プログラミングの概念を学べます。
「LEGOBOOST(レゴブースト)」(対象年齢:7歳〜)
Amazon.co.jp: レゴ(LEGO) ブースト レゴブースト クリエイティブ・ボックス 17101 おもちゃ ブロック プレゼント ロボット STEM 知育 男の子 女の子 7歳~12歳 : おもちゃ

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06X6GN2VQ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=coeteco-22&linkId=8f7ccf1a5f47848bc3e1e34aa69733ba&language=ja_JP >
LEGOが提供するプログラミング学習キットです。843個のブロックでロボットやギター、宇宙ステーションなど様々なものを組み立てるつくることができます。
iPhoneやAndroidなどスマートフォンで専用アプリをダウンロードをすることで、プログラミングでロボットに指示を出すことも可能です。前進させたりと動きの指示だけではなく、話したり周りのものに反応させたりもできます。
「Cubetto(キュベット)」(対象年齢:3歳〜)
キュベット プレイセットは、下記の内容がセットになった、プログラミングの基礎が学べる知育玩具です。 【セット内容】 かわいい木製のロボット、 プログラミング用の木製パネル、 プレイフルなプログラミング用ブロック16個、 美しいデザインのマップ、 遊び方を解説したストーリーブック デジタル画面を使用しないので、小さなお子さまにも安心してお使いいただけます。 ...

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01N02G5ET/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=coeteco-22&linkId=77469e68ec057bc7c607924f4988e943&language=ja_JP >
イギリスのプリモトイズが開発した木製箱型ロボットです。
Cubettoにはプログラムで動く本体の他にコーディングができるブロック、そしてブロックをはめるボードがあります。ボードに前進や後退などそれぞれの指示のブロックをはめることで、ロボットに命令できます。
またCubettoの下に様々な世界が描かれている「World Map」を敷くことでゴール設定ができ、子ども達の想像力を膨らませることもできます。
「Ozobot(オゾボット)」 (対象年齢:3歳〜)
アメリカのエボルブ社が開発した、世界最小といわれているプログラミングロボットです。紙の上にカラーペンで線を書き、色ごとに指定された指示に従って進むロボットです。
「OzoBlokly」を使えば、オンライン上で指定された指示にしたがってOzobotを動かすことができ、より専門的にプログラミングを学べます。
「ROBOTAMI」(対象年齢:小学校1年〜6年)
ロボットプログラミング教材「ROBOTAMI」(ろぼたみ)の製品サイト。関東を中心に、塾、教室、英会話スクール、学童等で導入・運用されているROBOTAMIは小学1年~6年生を対象とした総合統合能力を育てるSTEM教育に最適なロボットプログラミング教材です。

https://robotami.jp/ >
韓国のrobotron社が開発・製造・販売をしているロボットプログラミング教材です。ROBOTAMIの教材は入門・初級・中級・上級の4レベルがあり、すべて習得するのに2年かかります。
はじめは、コードの記述などのないロボット制作からカリキュラムが始まり、ロボットの動力や力学などを学び、徐々にプログラミング学習の要素がカリキュラムに加わってきます。
「Rapiro(ラピロ)」(対象年齢:15歳~)
機楽株式会社、株式会社ミヨシ、株式会社スイッチサイエンスの3社の共同プロジェクトで開発された人型模型ロボットです。Rapiroは組み立てた後コードを記述しなくても、メイン基板にプログラムが書き込まれているため、すぐにロボットを動かすことができます。
メイン基板はArduino互換なため、Arduino IDEの開発環境でプログラミングができます。さらに、Rapiro には「Rasberry Pi(ラズベリーパイ)」を搭載することもでき、本格的なプログラミングを行えます。
「little Bits STAR WARS R2-D2 Droid Inventor Kit」(対象年齢:8歳~)
Amazon.co.jp: littleBits STAR WARS R2-D2 ドロイド・キット Droid Inventor Kit : おもちゃ

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073P63ST7/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=coeteco-22&linkId=f582b698d4f21493eafcb6a94d3cb927&language=ja_JP >
磁石で電子回路を繋いで電子工作ができるオープンソースライブラリ「littlebits」を利用してスターウォーズのキャラクター『R2-D2』を動かせるキットです。
R2-D2を動かすのに様々なモードがあり、遊びながらlittle Bitsに触れることで、簡単に電子回路を作って学べます。
専用アプリを利用することでR2-D2に新しいスキルを覚えさせたり、17種類以上のミッションを実行させたりすることもできます。
「うきうきロボットプログラミングセット」(対象年齢:8歳~)
未来の大発明家を目指そう! 日経BP社刊「うきうきプログラミング」で作成しているロボットが作成できる特別キット! 作例 1自動ドア 2リモコン式ねらいうちゲーム 3ピカピカLEDマシン 4お母さん検知マシン 5床拭きお掃除ロボット それ以外にも、アイデア次第でオリジナルロボットも作ることができます。 【セット内容】 ...

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00TH0A86A/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=coeteco-22&linkId=39ed0a96aa7c961ce18001986d619514&language=ja_JP >
「Artec Block(アーテックブロック)」とロボット用基板「スタディーノ」を組み合わせた、ロボット制作のための入門書も含まれたプログラミングセットです。
セットの中のパーツでタイマーやお絵かきロボットなどをつくれます。またコンピューター基板はハンダづけをする必要ありません。わかりやすい解説書付きのため、自宅で学習することができます。
「プログラミングロボット ダッシュくん」(推奨年齢:6歳~)
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://www.dash-robo.com/ >
全世界で2,000校以上の学校に導入されている、世界中でプログラミング教育に活用されているプログラミングロボットです。
ダッシュくんを動かすことができるアプリは全部で5種類あり、6才の子供が使用できるものから、8才から使用できる難易度の高いものまであります。復習も兼ねてミッションをクリアできる「Wonder」といったアプリなどもあります。
「コード・A・ピラー」(対象年齢:3歳〜6歳)
Explore Fisher-Price nursery essentials and toys for newborns and babies at Mattel.com. Shop top registry picks, developmental toys, and more!

https://www.fisher-price.com/ja_JP/product/98301 >
フィッシャープライス製のイモムシ型ロボットです。
本体の部分のパーツには前進、右折、左折といった命令が組み込まれており、パーツの順番を変えることでロボットに指示が出せます。音と光を出しながら動くため、プログラミングを学びながら視覚でも楽しめるロボットです。
「Elegoo UNO スマートロボットカー」(対象年齢:全年齢)
初心者や専門家がエレクトロニクス、プログラミング、ロボットを勉強するために設計され、UNO R3ボードをベースにした教育的キットです。 このロボットカーキットを組み立てることは、エンジニアにも初心者にも、非常に直観的で簡単です。 こんなに簡単でロボットプロジェクトを構築することはこれまでもなかったです。 電子、プログラミングやロボット技術に夢中になっている方に対し このキットは素晴らしいプレゼントだと思います。 内容物: 1pcs UNO R3 1pcs USB ケーブル 1pcs V5.0拡張ボードV3.0 1pcs L298NモータードライバボードV3...

https://www.amazon.co.jp/Elegoo-UNO%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BCV3-0-UNO-R3-%E6%95%99%E8%82%B2%E7%9A%84%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83%E3%80%81%E5%85%A8%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88/dp/B0749L7B3F/ref=as_li_ss_tl?SubscriptionId=AKIAJXQE7DF2QCI3XPBQ&linkCode=ll1&tag=coeteco-22&linkId=764c52f6ceee3fbafaeb8625722868bf&language=ja_JP >
Arduino言語でプログラムが組める教育キットです。ロボットカーの組立方法は説明書に分かりやすく解説されており、また赤外線コントロール、Bluetoothコントロール、追跡装置といった様々な機能が付いています。
「アーテックロボ ベーシック」(対象年齢:8歳〜)
アーテックロボはブロックで遊びながらかたちを組み立て、プログラミングをして思い通りの動きを与えるプログラミングロボットキットです。

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo/ja/sample/product_01.php >
アーテックが提供しているロボットプログラミングキットです。
アーテック社のロボットは様々な種類がありますが、こちらの『ベーシック』が基本セットになります。
パーツは追加購入できるため、自分の好きなロボットにカスタマイズもできます。
「MESH(メッシュ)」 (推奨年齢:小学校3年生〜)
特別な知識がなくてもプログラミングが体験できるIoTブロックMESH。あったらいいなをカタチに。だれでも手軽に、つくって楽しい。

http://meshprj.com/jp/ >
ソニーが開発した、誰でも簡単にプロジェクトをつくることができるブロック形状の電子機器です。過去にはグッドデザイン賞の中でも評価の高い「グッドデザインベスト100」を受賞しています。
MESHではiPhoneやAndroidスマートフォンなどのデバイスに専用のアプリをダウンロードし、そのアプリ内でプログラムを組みます。MESHには「LED」「人感」「動き」「湿度温度」など計7種類のブロックがあり、LEDタグではメールを光で通知したり、人感タグでは人が動いた時に写真撮影を行ったりすることができます。
「Apitor(アピター)」(対象年齢:8歳〜)
Apitorは総数400以上のパーツがセットになった、全18種類のロボットを作れるプログラミングキット。ブロックトイのようなロボット作りから始まり、ラジコン・プログラミングへと段階を踏みながら本格的なプログラミング学習ができるため、小学校低学年から高学年まで長く遊び続けられます。
また日本語対応済みの無料専用アプリとの連動も可能。
音楽再生やLEDライトの点滅などの細かな動作・時間も正確にコントロールできます。
ご家庭で楽しみながらプログラミング教育に取り組める教材です。
「toio(トイオ)」(対象年齢:6歳〜)
デジタル絵本アワード・キッズデザイン賞・グッドデザイン賞など様々な受賞歴を持つtoioは、世界中から高い評価を得ているプログラミング教材。toioで遊ぶには、本体と呼ばれるキューブ型のロボットとコントローラーが必要です。
「工作生物ゲズンロイド」や「大魔王の美術館と怪盗団」 など物語性に富んだソフトを差し込むことで遊びと学びの多様性を広げることができます。
プログラミング教材はパーツが多く組立の難易度が高いものも多いですが、toioのキューブはレゴブロックの取り付けが可能です。
手持ちのレゴブロックで自分だけのオリジナルロボットを作れるのも魅力。
toioで遊ぶことで自然とアイデア力や想像力も養われるでしょう。
「Sphero RVR(ローヴァー)」(対象年齢:8歳〜)
Sphero RVRは、教育ロボットナンバーワンを誇るアメリカのロボティクス企業から生まれたプログラミング教材。世界4万以上の教育機関で利用されている定評の高いプログラミング教材をさらに進化させたSphero RVRは、6種類のセンサーを搭載しカスタマイズ性を強化しています。
従来のプログラミング教材、他社のプログラミング教材とは一線を画す子どもの想像力を掻き立てる先進的でスタイリッシュなロボットです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?ロボットプログラミング教材といっても、いろいろな種類がありますね。こちらの記事で紹介したロボットプログラミング教材であれば、ロボットで楽しく遊びながら自宅でプログラミングを学ぶことができます。未就学児から使える機材などもあるので、子どもの好みや楽しめるような機能を持ったロボットプログラミング教材を探して、プログラミング学習をはじめてみてはいかがですか?


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
QUREOとは?ゲーム感覚で楽しめるプログラミング教材の使い方と特徴
小学校でプログラミング教育が必修化します。そんな中、子ども向けプログラミング学習教材も世界中でどんどん開発・発売されています。この記事ではプログラミング学習教材「QUREO(キュレオ)...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
ベネッセのプログラミング講座!内容やメリットをチェック
ベネッセ(ベネッセコーポレーション)は、子どものプログラミング教育を積極的に応援しています。学校教育用のツール・システムのほか、家庭用教材でもプログラミング教育に関係したさまざまなカリ...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部
-
(販売・供給終了)LEGO®︎マインドストームEV3とは?特徴、価格、開発会社まとめ
2020年度からついに小学校でプログラミング教育が始まります。 そんな中、子ども向けプログラミング学習教材も各社から様々なものが発売されています。 この記事では「LEGO®︎マイン...
2025.06.03|コエテコ byGMO 編集部
-
「Scratch」でプログラミング!子どもでも簡単に始められる!
子ども向けプログラミングスクールでもよく使われている「Scratch」。プログラミングと聞くと「難しそう」「分からない」といった先入観があるかと思います。そこで今回はどこよりも簡単なチ...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
KOOVとは?ロボット・プログラミング学習キットの魅力と特徴を解説
小学校でのプログラミング教育必修化に向けて関心が高まる中、子ども向けプログラミング学習教材も世界中でどんどん開発されています。 今回はソニー・グローバルエデュケーション開発の「KOO...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部