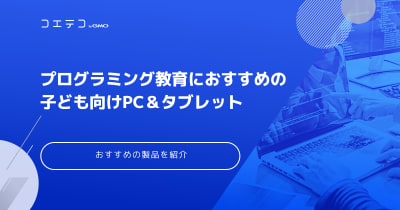小学生高学年におすすめのプログラミング教材10選!楽しく学ぶ方法を徹底解説
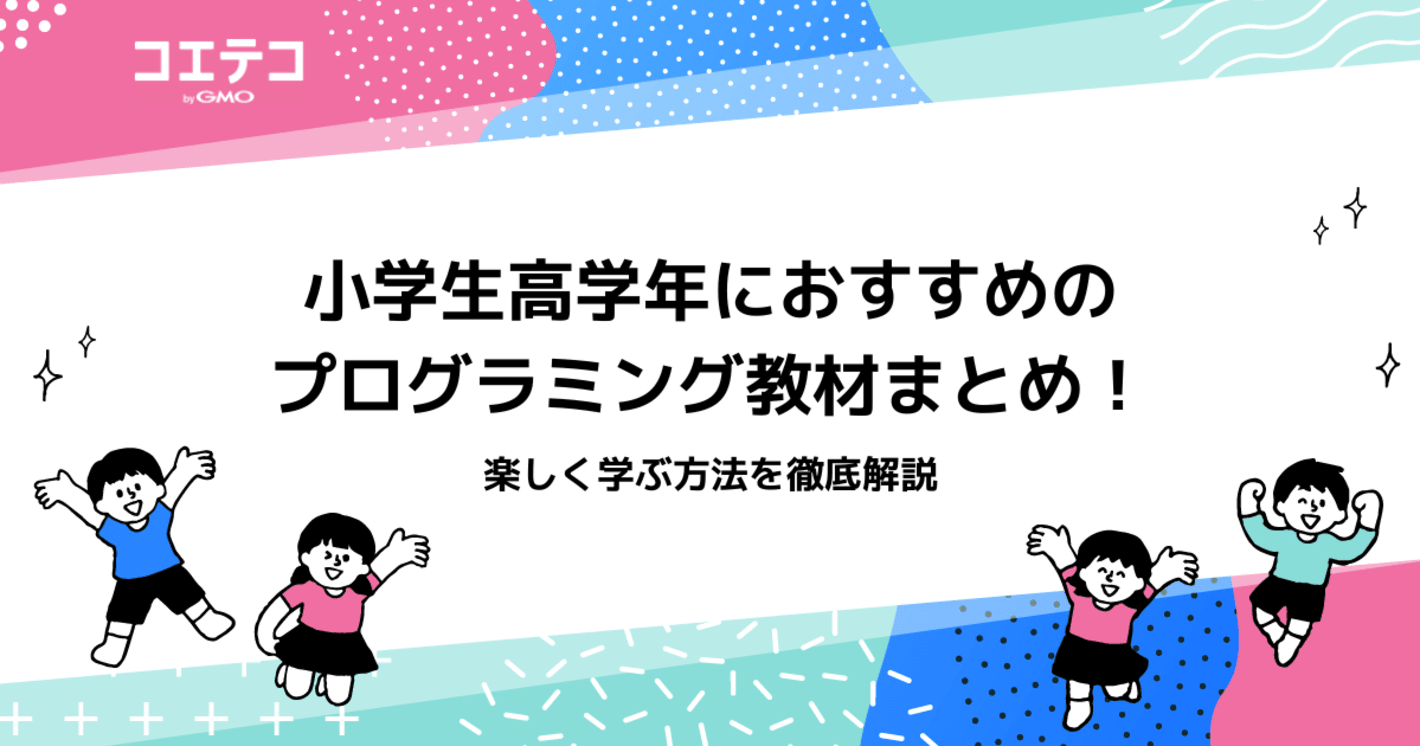
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
近年では、「自分のアイデアを形にしたい」「ゲームやアプリを作ってみたい」といった発想力や探求心を伸ばせるプログラミング教材が続々と登場しています。そこで今回は、小学校高学年のお子さんにおすすめのプログラミング教材をご紹介します。
小学校高学年、大人並のプロダクトも使いこなせます
小学校高学年になり簡単なプログラムやビジュアル型のツールに慣れた子どもたちは、本格的なテキストコーディングやロボット制御に挑戦する力をつけていきます。たとえばScratchやPythonを使ったゲーム制作、AIを活用したシステム開発など、高度な概念も遊びを通じて習得できるでしょう。自作アプリが動く達成感やロボットをプログラミングで動かせた喜びは、小学校高学年の子どもたちの大きな自信になります。
コンテストや競技会に挑戦する機会も増え、技術やアイデアを形にして試す経験が成長につながります。
2020年の小学校授業必修化に向けて増えつつある、ご家庭用のプログラミング教材。たくさんあって何がなにやら分からない......という方のために、年代別のおすすめ教材をご紹介していきます!今回は幼児向けの教材をご紹介します。
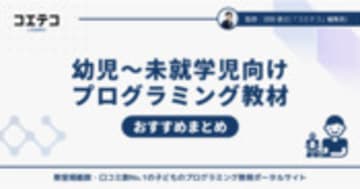
https://coeteco.jp//articles/10440 >
Minecraft

Minecraftは、自分だけの世界を作り上げる創造的なゲームとして世界中で愛されています。Minecraftの教育版である「Minecraft Education Edition」では、学びの要素がさらに強化されており、「コードビルダー」機能を使って本格派のプログラミングに挑戦できます。
Minecraft内でブロックベースのプログラミングツール(MakeCode)を活用すると、キャラクターの動きを制御したり、ゲーム内で作業を自動化したりといった複雑な制作が可能です。教育現場だけでなく家庭でも利用でき、本格的なプログラミング教育を遊び感覚で体験できる点が魅力です。
マインクラフト(マイクラ)が子どものプログラミング教育にぴったりなことをご存知でしたか?この記事ではマイクラが教育に最適な理由と、具体的に身につくスキル、マイクラを使ったプログラミング教室についてまとめました。
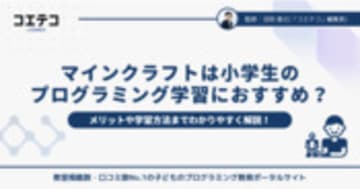

2025/11/17

Roblox

Roblox(ロブロックス)は、小学校高学年向けのプログラミング教材としても注目されています。 Roblox Studioを活用すれば、ビジュアルプログラミングを卒業した次のステップとして本格派のゲーム制作を学べます。ゲームの制作環境の設定からプログラミング言語「Lua」を使った開発、さらに完成したゲームを公開する方法までをRobloxで学べるのが魅力です。
2024年には保護者コントロールやデフォルト設定が強化される発表があり、小学生のお子さんがより安全に利用できる環境が整備されました。「今まで遊んでいたゲームを今度は自分で作ってみよう!」と、新しい挑戦の場を提供したいご家庭におすすめです。
Scratch

ScratchはMITメディアラボが開発したビジュアル・プログラミング言語で、ブロックを組み合わせて直感的にアニメーションやゲームを作れます。小学校高学年では、条件分岐や繰り返しといった本格的なプログラミング概念を理解しながら、創造力や論理的思考力を深められるのが魅力です。
プログラミングに慣れてきたら全国規模のコンテストに参加し、プレゼンテーション能力や作品の完成度を競う場にチャレンジするのもおすすめです。作品をオンラインでシェアすることで、仲間と刺激し合いながら成長できるのも高学年ならではの楽しみ方です。
KOOV®

ソニー・グローバルエデュケーションが提供するKOOV®はブロックを自由に組み立ててロボットを制作し、専用アプリで動かせるプログラミング教材です。小学校高学年では、複雑な構造や動作を組み込んだ高度なロボット制作に挑戦できます。
プログラムはビジュアルベースで直感的に学べるため、初めてでも安心。さらに自分のアイデアを形にして、試行錯誤しながら動きを最適化することで、問題解決力や創造力が身につきます。全国大会「KOOV Challenge」も開催されており、高学年になると技術力や発想力を競う場に挑戦する楽しさも味わえます。
小学校でのプログラミング教育必修化に向けて関心が高まる中、子ども向けプログラミング学習教材も世界中でどんどん開発されています。 今回はソニー・グローバルエデュケーション開発の「KOOV(クーブ)」についてご紹介します。
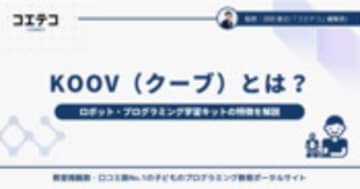

2025/11/17

レゴ® エデュケーション SPIKE™ プライムセット

レゴ® エデュケーション SPIKE™ プライムセットは、小学校高学年・中高生向けに設計されたSTEAM教育対応のロボット教材です。レゴ®ブロックとモーターやセンサーを組み合わせて、ロボットを組み立て、専用アプリを使ってプログラミングすることで動作させる仕組みです。
Pythonによるテキストベースのプログラミング言語まで段階的に学べるのが特徴で、ロボット競技会に挑戦することで自信を持つきっかけになるでしょう。さらに拡張セットの活用によって複雑な動作や高度な制御システムにもチャレンジできます。
レゴ® マインドストーム® EV3(販売終了)

レゴ® マインドストーム® EV3は、組み立てたロボットをC言語やJava、C#、mrubyといった多様な言語で制御できるため、高度なプログラミング教育にも活用されてきました。プログラミング環境の構築から実装までの一連の流れを体験できる点が大きな魅力です。
レゴ® マインドストーム® EV3はWRO(World Robot Olympiad)といった世界規模のロボット競技会でも広く採用され、多くのロボット教室や教育現場で親しまれてきました。2024年現在、レゴ® マインドストーム® EV3は販売終了しています。
2018年9月9日に金沢で開催された『WRO Japan 決勝大会』。 約2,000チームが参加した予選会を勝ち抜いた179チームが参加しました。 あいにくの空模様の中で白熱した戦いのレポートをお届けします!


2025/05/26

2019年1月13日(日)、「教育版レゴ®︎マインドストーム®︎EV3」の正規代理店・株式会社アフレルによる「はじめてのロボコン講習会」が行われました。イベントには、これからロボコン出場をめざす子ども達が多数集まりました。


2025/06/25

学習塾「栄光ゼミナール」などで有名な株式会社栄光が、小学生のためのロボット製作&プログラミング教室としてスタートさせた「栄光ロボットアカデミー」。世界60ヵ国以上で採用されている「教育版レゴ®マインドストーム®EV3」を使用し、レゴブロックを使いながら楽しくプログラミングを学べるのが特徴になっています。今回は、こちらの「栄光ロボットアカデミー」が小学3〜6年生向けに行っている「セカンダリーコ...


2025/05/26

IchigoJam

IchigoJamは初心者向けのプログラミング専用コンピュータで、子どもたちが手軽にコードを学べるプログラミング教材です。使用する言語は「BASIC」で、シンプルな構文とわかりやすい可読性が特徴です。
IchigoJamでは、コマンドを打ち込むことで文字表示や簡単なゲームの作成、電子工作の制御も可能。プログラムがすぐに反映されるため、コードを動かす楽しさを直感的に学べます。低価格かつシンプルな構成で、小学校高学年でも無理なく取り組める点も魅力です。
子ども向けプログラミング教室やイベントなど様々な場所で活用されているプログラミング専用子どもパソコンIchigojamについて解説します。はんだ付けでの組み立てからプログラミングの導入までをレポートします。


2025/05/26

micro:bit

micro:bitはPython、JavaScriptに対応し、プロと変わらない本格的なコーディングができるマイコンボードです。プログラミングが初めてのお子さんでも取り組みやすいブロックタイプのプログラミングから、JavaScriptやPythonといったテキスト言語にも対応しています。
情報教育の先進国であるイギリスでは11歳・12歳の子どもたちに無償配布され、教育現場での導入が進んでいます。micro:bitは実用性と効果は高く評価されているプログラミング教材の一つと言えます。
いま話題の『micro:bit(マイクロビット)』はイギリスの放送局BBCで開発された教育用のマイコンボードです。イギリスでは11歳から12歳のすべての生徒に無償配布され、現在では40か国を超える国々で利用されています。多彩な機能と拡張性を秘めているのが特徴で、プログラミングが初めてというお子さんでもすぐに使えるほどシンプルでありながら、プログラミングに手慣れた大人までも唸らせるその魅力を、...


2025/05/26

2020年からの小学校でのプログラミング教育必修化にともない、盛り上がりを見せるロボットやプログラミング教室。でも、そんな中でなんとなく取り残されているのがお母さんたち...。「いったい何が行われるの?」と思いながらも、ご自身が体験できる機会はそれほど多くありません。今回は、そんな迷えるお母さんたちの願いをかなえてくれる『ITな女子会』をご紹介します。
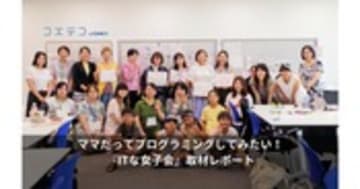

2025/05/26

MESH

MESHは、センサーやボタンなど機能を持つブロックを組み合わせて、日常生活で「ちょっと便利な仕組み」を作れるIoTプログラミングツールです。ブロックごとに割り振られた機能をタブレットアプリ上で直感的に組み立てられるため、難しいプログラミング知識がなくても取り組めます。
たとえば「お天気アラーム」や「赤ちゃん見守りセンサー」といったアイデアを形にしたり、対応する家電を自作の仕組みでコントロールしたりも可能です。失敗と成功を繰り返す試行錯誤の中で、創造力や問題解決力が自然と育まれるでしょう。
Nintendo Labo

Nintendo Laboはダンボールを組み立ててコントローラーを使う独自の遊び方で知られていますが、実は「Toy-Conガレージ」といったビジュアルプログラミングモードも搭載されています。
Toy-Conガレージでは画面上で命令ブロックを接続することで、「画面をタッチしたらJoy-Conが振動する」や「ボタンを押したら音が鳴る」といった動きを簡単に設定できます。身近なダンボールや空き箱がデジタル制御でロボットや楽器に変身する仕組みは、アナログとデジタルの融合を学ぶきっかけにもなるでしょう。
なお、Nintendo Laboのキットは公式サイトなどで入手できますが、一部の段ボールシートに関しては在庫切れとなっています。気になる方は早めにチェックしておきましょう。
小学校高学年になったら本格的なプログラミング教材にもチャレンジ!
世界で活躍するプログラマーや開発者の多くが、初めてプログラミングに触れた時期として挙げるのが小学生時代です。自分のアイデアを形にできる喜びやモノが動いたときの達成感が、その後の成長やキャリアの礎になったとも言われています。お子さんがプログラミングに興味を持ったら、好奇心を大切にしてどんどん挑戦させてあげましょう。高学年向けのプログラミング教材なら、本格的な学びをとおして自信や可能性を広げるきっかけになります。
プログラミング始めるにあたって、ロボットプログラミングは子どもでも簡単に始めることが可能です。この記事では、おすすめの子ども向けロボットプログラミング教材をご紹介し、今後のプログラミング教育に役立てていただけたらと思います。
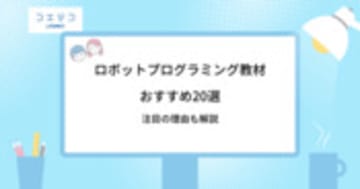

2026/01/02

2020年度、ついに小学校でプログラミング教育が必修化しました。コロナ禍の影響もあいまって、自宅からプログラミングが学べるオンラインスクールへの注目が集まっています。 この記事では子どもにおすすめのオンラインプログラミングスクールをまとめました。
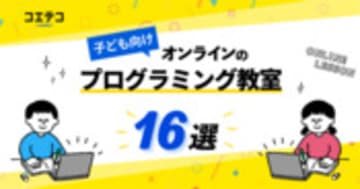

2026/02/03



Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
幼児~未就学児におすすめのプログラミング教材14選と無料アプリ3選
2020年の小学校授業必修化に向けて増えつつある、ご家庭用のプログラミング教材。たくさんあって何がなにやら分からない……という方のために、年代別のおすすめ教材をご紹介していきます!今回...
2025.11.17|プログラミング教室ガイド
-
日本は遅れてる?海外のプログラミング教育の現状!
日本では小学校のプログラミング教育が2020年から必修化されることになっており、中学校では2012年から「技術・家庭科」で「プログラムによる計測・制御」が必修の授業として行われています...
2025.06.24|さえ
-
プログラミングに強い私立中学校5選まとめ
2020年小学校でのプログラミング教育必修化に引き続き、中学でも順次プログラミング教育の比重が高まっていくと予想されています。ここでは、プログラミングの授業に力を入れている私立中学校を...
2025.04.18|コエテコ byGMO 編集部
-
子どものプログラミング学習におすすめのパソコン10選|予算やスペックなどの選び方をご紹介
2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されることを受けて、今のうちからお子さんにプログラミングに触れさせておこうと考えている親御さんは多いようです。 プログラミングをするた...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
小学生のプログラミング教材おすすめサービス9選【2026年最新版】
小学校でのプログラミング教育必修化を前に、家庭でも何かできることは?と考える方は多いですよね。この記事では未就学児や小学1年生、低学年でも楽しく学べるプログラミング教材や言語・アプリ・...
2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部