子どもに教えたいフェイクニュースの見分け方

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
しかし、インターネットの世界は信憑性が低いものや、中にはいわゆるフェイクニュースもあり、情報を選択するスキルが必要とされています。
今回の教育トピックでは特にフェイクニュースにフォーカスし、子どもに学んでほしいネットリテラシーのひとつとして「フェイクニュースの見分け方」を解説、またデジタルネイティブ世代の日常にもちょっぴり迫って参ります!
フェイクニュースとは
「フェイクニュース」とは、虚偽(fake)の情報でつくられたニュースのことで、 一般的にはインターネット上で発信、拡散される偽のニュースを指します。フェイ クニュースは、読んだ人に「そうに違いない」、「そうかもしれない」と思わせるような内容で人々の注目を集め、真実だと思い込んだ人が、SNS 上に拡散することで、 あっという間に世界中に広がる傾向があります。
引用:青少年のネット非行・被害対策情報/福井県安全環境部県民安全課
小学生もフェイクニュースを見ている
小学生のスマホ保有率は高まるいっぽうですし、家庭のタブレット端末や親のスマホでネットをチェックしている小学生はとても多いです。子どもがフェイクニュースに触れる機会は、たぶん親が思っている以上に多く、しかも低年齢化していると考えるべきでしょう。
上記のグラフは東京都の調査ですが、スマホを所有している小学生の実に16%がツイッターを利用しています。実際に小学生でもTwitterを見たり、フェイクニュースを見るだけでなく、場合によっては拡散している「張本人」にもなりかねない状況です。
16%はとても多い数とは言えませんが、利用しているのではなく「見ているだけ」の子どももいる、スマホではなくタブレットなどで閲覧していることも考えると、もっと多くの小学生がさまざまなSNSで情報を得ているのではないでしょうか。親が知らない間に子どもがフェイクニュースとわからずに見ている可能性は高いと言えます。
フェイクニュースはどれだけ検索されているのか
子どもだけに限定されませんが、日本でフェイクニュースを検索している人の数を見てみましょう。
日本でもたびたび「フェイクニュース」が検索されていることがわかります。
フェイクニュースは話題が出ると急激に検索数が伸びますから、上下はありますが、こうして見ると2016年にはほとんどなかったフェイクニュースの検索が少しずつ、確実に増えていますね。特に災害やパンデミック、あるいは大きな選挙など政治的な活動がある時に、フェイクニュースが頻発する傾向があります。
私たち大人も含めて、常に「これは本当のことなのか、誰かの個人的な意見なのか、意図的なウソなのか」と情報を見極めることが今や求められている時代です。
フェイクニュースとライオン脱走
平成28年の熊本地震のさいに、動物園のライオンが脱走したというフェイクニュースが駆け巡ったことは記憶に新しいところです。この投稿は1時間で2万件以上リツイートされて広がりました。画像もあわせて発信した男性は偽計業務妨害容疑で逮捕されています。アメリカのマサチューセッツ工科大学のチームは「フェイクニュースは真実よりも早く拡散する」とした調査結果を公表しており、フェイクニュースがリツイート(再投稿・拡散)される可能性は正しいニュースに比べて70%も高いとしています。
地震という不安定な背景の中、ライオン脱走というセンセーショナルな内容であり、画像つきで「なんとなく信用してしまう」側面があり、SNSによって瞬く間に拡散されたのでしょう。コロナ禍においては、トイレットペーパーがなくなるといったフェイクニュースの拡散が、実際にスーパーからトイレットペーパーがなくなるという現象を引き起こしました。
「たかが偽のニュース」と片付けられないものがあるのです。
参考:偽ニュース「真実よりも早く拡散」/朝日新聞Digital
フェイクニュースの見分け方

では、まず親も含めて、フェイクニュースの基本的な見分け方を見ていきましょう。
たくさんの専門家が方法を提示していますが、ここでは、とてもわかりやすいNHK for Scoolの「フェイクニュースを見抜くには」から抜粋します。また、ここにあげた3つは、政府が子ども向けに発信している情報通信白書forKidsでも解説されています。
フェイクニュースの見分け方3つのポイント
① 発信しているのは誰か
② SNSだけでなく他のメディアがどう報道しているか
③ 文章の表現に注意する
フェイクニュースの見分け方|①発信元を確認しよう
まずはその情報を誰が発信しているのかを確認します。テレビや新聞社のニュースでさえ「絶対に正しい」とは断言できませんが、少なくともどこからどの情報がもたらされているのかがわかります。情報の発信元が情報に対する責任をもっているわけですから、個人の情報よりは信憑性が高くなります。いっぽうで情報の発信元がよくわからない場合、SNSなどで友人の友人の友人が見たり聞いたり(したらしい)となると、もはや、情報元はあいまいで確認のしようがありません。こうした情報は「情報ではなく、誰かの意見なのかな?」「伝言ゲームみたいに回ってきたのかも?」とさまざまな方向から考えてみる必要がありますね。
フェイクニュースの見分け方|②他の情報を見てみよう
ひとつの情報だけで断定せずに、同じ情報をいろいろなメディアで確認してみましょう。たとえば、ライオンが脱走したニュースについてSNSでは一斉に拡散されましたが、その当時に新聞やテレビ局が「ライオンが脱走しました!」とメディアを通じてニュースを流してはいません。少し調べればわかることです。
真偽がよくわからない情報があったら、その情報について、いろいろな角度から調べてみましょう。もしかしたら別のメディアでも報道しているかもしれませんが、「どう報道しているか」内容をしっかり比べてみると「あれ、なんか、こっちでは違うこと書いている」「ここでは断言してない」「このニュースでは否定している」と違いがわかります。
フェイクニュースの見分け方|③文章の表現に注意してみよう
よくスポーツ新聞などで「○○が電撃移籍!?」と書いてありますが、この「!?」がくせ者で、実際には移籍すると決まったことを報じているのではありません。だから「!?」がついているんですね。雑誌や新聞などでも目を引くため、手にとってもらうために、ちょっとした表現を加えるのはよくあることです。同じようにネット上の情報でも「〜らしい」「〜と思われる」といったように断言していない場合には、疑ってかかったほうがよいでしょう。
友人から発信されるSNSの信憑性
さらにポイントとしてはSNSの特徴があります。まったく知らない相手であれば誰もが警戒心を持ちます。でも友だちならどうでしょうか。SNS等でつながっている友人が「○○だって!」と発信すれば、「○○なんだ」とついつい信用してしまいます。その友人もウソをついているつもりはなく、悪意はなくても、こうしてあっという間にフェイクニュースは広がってしまいます。
知り合いの言っていることだからと鵜呑みにしないことも大切です。
参考:フェイクニュースを見抜くには/NHKforSchool
情報通信白書forKids/総務省
「ファクトチェック」「ディープフェイク」とは
フェイクニュースの見分け方について調べていくと、2つの言葉がよく出てきます。- ファクトチェック
- ディープフェイク
ファクトチェックとは
ファクトチェックとは、社会に広がっている情報・ニュースや言説が事実に基づいているかどうかを調べ、そのプロセスを記事化して、正確な情報を人々と共有する営みです。一言でいえば、「真偽検証」です。
引用:認定NPO法人 ファクトチェック・イニシアティブ
ディープフェイクとは
ディープフェイクとは、本物と見分けがつきづらい偽物の動画のことです。一般的に見破ることが難しく、とても巧妙に作られています。子どもが見る機会は少ないかもしれませんが、たとえば有名人がまるで本当に話しているように見える動画もあります。でも実際にはそのように話しているのではなく、本物そっくり(あるいは本物の画像を利用して)に話しているように見せているわけです。今では、AIを駆使して、その人のクセや表情を学び、完璧に模倣することができます。だまされるな、と言われても、ここまでくると難しいですね……。
子どもにフェイクニュースについてどう教えるか

欧米諸国では早くから学校で情報リテラシーやメディアリテラシーについて授業で学んでいます。しかし、日本ではこうしたネットを介した「正しい情報の見分け方、情報の正しい使い方」を学ぶ機会はまだまだ少ないのが現実です。
ディープフェイクやファクトチェックという言葉について、小学生に説明してもなかなか理解できません。
家庭では、たとえばタブレットを見るときに一緒にのぞいて「これって本当のことなのかな」と問いかけるだけでも、子どもは疑ってみることを覚えます。調べ学習や夏休みの自由研究などで、ネットを使って何かを調べるときに、フェイクニュースも含めた「ネット上の情報」について、話してあげるのもいいですね。
また、前述したNHK for Schoolのフェイクニュースに関する動画はとてもわかりやすいので、親子で視聴してみてはいかがでしょうか。
あなたの家ではどう教えてる?フェイクニュースやネットの使い方
- フェイクニュースの話題がのぼったときに、わざとじゃなくても犯罪になってしまうんだよと話した(Nさん/子ども・小6)
- ネットに出ていることはいつも正しいとは限らないと繰り返し話している。トイレットペーパーがフェイクニュースで売り切れになってしまった時も子どもに細かく説明した(Aさん/子ども・小3)
- 学校でフェイクニュースの見分け方のような動画を観て、感想文を書く宿題が出ました。その時にチャンスだと思い、インターネットではまるで本当のことのように書いてあることや、何かを売るために書いてある記事がたくさんあるのだと説明しました。でも、本当に理解しているとは思えません…(Rさん/子ども・小5)
- 笑えるようなウソのニュースもフェイクニュースと言えるのでしょうか。親もよくわからないのに、教えられない。ただ、ネットに書いてることをそのまんま信用しないようにとだけは常々言っています(Kさん/子ども・小4)
- 娘が友だちから聞いたらしく「○○を食べるとコロナにかからないんだって!」と言うので、その友だちはどこから聞いたの?お医者さん?と問い返すと、「なんか他の子がネットに書いてあるの見たって」と言うので、そういう伝言ゲーム的なことを信じてはいけない、特に健康や病気については安易に信じてはいけないよ、と教えました(Uさん/子ども・小1と小6)
- スマホを持たせると、ニュースサイトなんかも子どもが興味を持っているものばかりがどんどん出てくるから、引き込まれていくようで、今の時代に「情報の取捨選択」を教えるのは難しいなぁと実感しています。とりあえず、繰り返し注意するしかないです(Nさん/子ども・小5と中1)
フェイクニュースやネットの嘘を知る「小学生向けの本」
フェイクニュースやネット上のルールについて書かれた、小学生向けの本を紹介します。他にも、いろいろな書籍が出ています。親が先に読んで、お子さんにすすめてみてはいかがでしょうか。本格的な物語でひきこまれる「嘘吹きネットワーク」

小学生高学年向けでしょうが、ちょっと内容は難しいところがあるかも、です。クラス委員の主人公が、SNSで拡散するデマをなんとかしようとする物語、SNSが炎上するシーンなどけっこうリアルで怖いです。正しさを求める主人公のセリフなどがちょっと苦手に感じるかもしれませんが、いろいろと考えるきっかけともなりそうです。
誰でもわかりやすい手引き書の1冊「ネットのルール」

こちらはもっとも入りやすい、ネットリテラシー入門書です。イラストが多く、小学生低学年でも読みやすくなっています。どれも簡潔にまとめてあり、フェイクニュース以前に「ネットを使うときはここに気をつけるんだよ!」的な内容なので、最初の1冊にピッタリです。
動画で検索し「自分が欲しい回答」をより分ける子ども達
さて、今回は少し私自身の体験を紹介したいと思います。わが家の次男は中学生です。その次男と、少し前にこんなことがありました。
新しいリュックを買うことになったので、「どんなのが欲しいの?」と聞くと、3つほどアウトドアやスポーツブランドをあげて、ざっくり検索して(ざっくり、とは息子の言葉そのままです)、3つのモデルに絞り込んで、今、それをリサーチ中だと言うわけです。
ほほぉ、と思って、私も言われたモデルで検索して実物をスマホで見ていると横から息子が「そーいうのオレ見てないから」と言うではありませんか。
動画だよ。
動画!?動画でリュックのモデルいれると出てくるわけ?そんな動画あるの?っていうか、普通、リュックの公式サイトで大きさとか値段チェックしてさ、それから検索して安いとこを探したり、おすすめしている記事を見たりしないの?
あー、そういうオススメのリュックなんたら、とかは見ない。だって、ほとんど宣伝じゃん!
ママもさ、仕事柄わかってんでしょ。ほら、ちょっと盛って書いたりしてない?
なんか論点ずれてんだけどさ。
とにかく文章の記事ってさ、どこまで本当なのかわからないんだもん。
でも動画はさ、バッグを見せて、ここが使いやすい、ここ見るとこんな感じになってて、自分が持つと金具があたってちょっと使いづらいんだよね、みたいにしゃべるでしょ。
本当にバッグを見せて話しているのをさ、いくつもみてると、人によって意見も違うけど、その中で自分も同じような使い方をする人なら、たぶん同じような感想を持つから、じゃ、コレは使えそうだなってわかるわけ。
もっと前から教えるべきだった情報リテラシー
デジタルネイティブ世代は、私が想像しているよりはるかに遠いところにいました。彼らは、自分に(あるいは自分だけに)とって正しい情報をより分けてはいるのです。そして、「ディープフェイク」という言葉が蘇りました。動画だから、画像だから、それはリアルとも限らないのです。この時に息子とフェイクニュースについての話題にも触れました。
子どもが見ているフェイクニュースは、ニュースというより冗談の延長線上にあったり、どちらかといえばネタであったりすることが多く、彼らの生活をおびやかすものではないことがほとんどです。だから「みんなフェイクってわかってるんだからフェイクニュースじゃないんだよね」と、のたまうわけです。
しかし、そんな遊びの延長線上にあるものはかなり危ういことを、彼は知らないのだと感じました。子どもは仲良し同士、仲間内だと言いますが、人間関係は何がきっかけでバランスを崩すか分からないし、時には良好だった関係が悪くなり、攻撃的になることもあるでしょう。
世間的にはフェイクニュースは大統領選挙や災害のようなケースで広まることとが多いのは事実です。
しかし身近なところで「偽の情報」を意図的に流して何かを、誰かを攻撃することもあり得ます。「フェイク」「デマ」の危険性について、今、振り返って考えると、やはりスマホを持たせた時点、あるいはタブレット等を頻繁に使うようになった小学校高学年の時に、いえ、もっと前から教えるべきだったのだと思いました。
デジタルネイティブ世代の子ども達は今

今の子どもたちは生まれた時からインターネットが当たり前にあるデジタルネイティブ世代です。
次男はリュックに限らず、なんでも動画で検索しています。そして足りない情報があると、動画以外の記事や情報を検索し、ちらと冒頭だけ見て、次から次へと別の記事に飛び移り、自分が欲しいと思う情報へと猛スピードでたどり着きます。いとも簡単に、山のような情報を彼は手に入れてしまいます。
わからない国語の問題も動画で解き方を検索し、もっともわかりやすい説明を選んで覚える子ども達。明日の天気、思い出せない曲名、最近売れてるカップラーメン何かな、どんな小さなことでも次の瞬間、サクサクとスマホをいじって回答を見つける子ども達……。
便利になったいっぽうで、彼らは常に「情報を取捨選択し続けなければならない」状況に身を置いているのだと改めて感じた出来事でした。
参考:デジタルネイティブとは?
始めておこう「ネットリテラシー」の学び
ここではごく基本的な「フェイクニュースの見分け方」しか載せていません。子ども達は私たち世代よりもはるかに多くのネット上の情報をもとに生活していくことになります。家庭でも折に触れて「インターネットの世界」について話をしたり、子どもがどう使っているか、どんなものを見ているのか、探るのではなく「昨日見たテレビ」と似た感覚で気軽に話し合えるといいのではないでしょうか。
情報モラル・ITリテラシーという言葉だけがひとり歩きしており、本当に子どもが年齢に応じた「ITツールやインターネットの使い方」を学んでいるとはどうしても思えません。学校だけに頼れない今は、家庭でも子どもに繰り返し、さまざまな方向から、ネットやSNSのルールや常識やマナーを教えること、それは教育というより躾のひとつとさえ言えるかもしれませんね。
参考:ネットリテラシーとは?低いでは済まされない?
自分が失敗した部分があることを踏まえた上で、皆さんにはぜひ、お子さんが小さいうちから、ITリテラシーについて教える機会を持ってほしいなと思います。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
デジタルネイティブとは?意味や特徴を徹底解説
生まれたときからインターネットが身近にある世代「デジタルネイティブ」は、コミュニケーションの方法や考え方がそれまでの世代と異なっていると言われます。この記事では「デジタルネイティブ」の...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
マイクラでモード変更するには?コマンドから便利テクニックまで解説
子どもから大人まで幅広い世代に愛されているMinecraft(マイクラ)。ゲームの魅力をさらに引き出すポイントのひとつが「モード変更」です。マイクラでモードを切り替えるには、どうしたら...
2025.01.15|コエテコ byGMO 編集部
-
小学校で学ぶプログラミング教育とは?背景や目的を詳しく解説
小学校でプログラミング教育が必修化されて以降、中学校や高校にも広がり、子どもたちがプログラミングに触れる機会は確実に増えています。一方で、保護者の中には「何を学んでいるのか」「将来にど...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
中学生向けプログラミング教室おすすめ12選!オンラインも徹底解説
習い事をするときに必要なのは目標を考えた選択でしょう。大学入試にも情報科目が追加されているところもあるため、中学生のうちにプログラミング学習はおすすめです。 この記事では、プログラミ...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
【幼児~小学生向け】プログラミングおもちゃおすすめ9選を年代別に紹介
子ども向けに工夫された、プログラミングを楽しく学ぶためのおもちゃを紹介。東京情報大学総合情報学部の教授であり、プログラミング教育者やサイエンスライターとしても活躍する、松下孝太郎さんが...
2025.05.26|コエテコ教育コラム








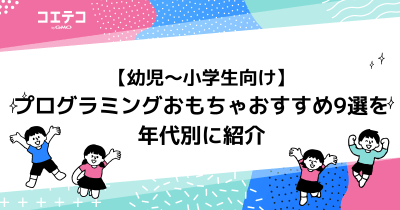
だったら、どうやって情報探してるわけ?