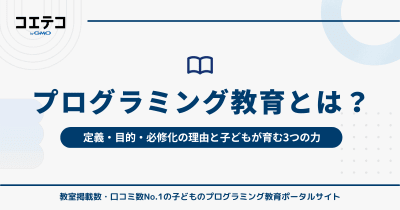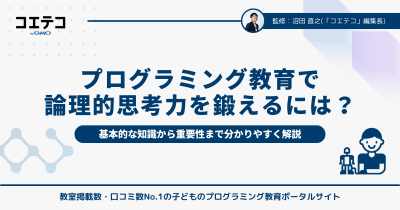Viscuit(ビスケット)とは?絵で動かす魔法のプログラミング言語で子どもの創造力を開花!

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
「子どもにプログラミングを学ばせたいけど、難しそう」そんな保護者の方におすすめです。また、Viscuitは全国の学校現場でも導入が進んでいます。
この記事では、Viscuitの独自システム「メガネ」の仕組みから他教材との違い、創造力と論理的思考を同時に育む教育効果まで、くわしく解説します。学校現場の実践事例や家庭学習のコツも紹介します。
Viscuit(ビスケット)の概要と主な特徴

Viscuit(ビスケット)とは何か?基本的な仕組み
Viscuitは、原田康徳博士によって開発されたビジュアルプログラミング言語です。これまでのプログラミング教材とは異なり、文字やコードを一切使わずに、自分で描いた絵を動かしてアニメーションやゲームを作れます。AI技術が急速に発達する中、単純なコーディングスキルよりも「創造的思考力」や「問題解決能力」がより重要になっています。
Viscuitは、技術的な複雑さに惑わされることなく、プログラミングの本質的な思考プロセスを体験できる貴重な学習ツールとして、教育現場で高く評価されています。
Viscuitの「3つの特徴」
- 文字入力を一切せず、絵を描くだけでプログラムが完成
- 遊び感覚で創造力を伸ばせる
- メガネ機能による独自の仕組み
プログラミングと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、Viscuitなら未就学児でも直感的にプログラミングの本質を体験できます。子どもプログラミング教材として、独創性と教育効果が注目されています。
Viscuitの「3つの原理」
Viscuitの開発・運営を行う合同会社デジタルポケットは、3つの原理を掲げています。Viscuitの3つの原理
- 驚きと喜びを最大化
- 発見を奪わない
- 誰も嫌いにさせない
この3つの原理は、Viscuitでの学習体験を設計する際の重要な指針となっています。単なる技術習得ではなく、子どもたちの内面的な成長を重視したアプローチが、Viscuitの教育哲学を象徴しています。
※Viscuitは、総務省による若年層に対するプログラミング教育の普及推進事業のひとつとして採用されています。また、文部科学省公式コンテンツ・教材事例として多数紹介されています。
Viscuit開発者の原田はかせとは?
Viscuitを開発したのは、原田康徳博士です。原田博士とは?
計算機科学者。ビスケット開発者。博士(工学)。1963年北海道生まれ。1992年北海道大学大学院博士後期課程修了後、NTT基礎研究所で23年間研究に従事。JSTさきがけ研究員、IPA未踏ソフトウェア創造事業プロジェクトマネージャを歴任。2015年NTT退職後、合同会社デジタルポケットを設立。
Viscuitカンファレンス2025レポート
2025年8月4日、東京女子体育大学で開催された「ビスケットカンファレンス2025」。「こんなときこそビスケット」をテーマに掲げた今回のカンファレンスでは、人工知能が急速に発達する現代において、プログラミング教育はどのような意味を持つのか、その中でビスケット(Viscuit)が果たすべき役割について議論が交わされました。


2025/09/09

「メガネ」システムの独自性とプログラミング学習効果
ビスケットの最大の特徴は、「メガネ」と呼ばれる独特なプログラミングツールです。このメガネは左右二つの輪がつながった形状で、プログラミングの複雑なルールを視覚的に分かりやすく表現します。メガネの基本的な使い方
| メガネの設定方法 | 結果 | 身につく概念 |
| 左右に同じ絵を少しずらして配置 | 絵が移動する | 座標と移動の仕組み |
| 左右に異なる絵を配置 | 絵が変化する | 条件と結果の関係 |
| 複数のメガネを組み合わせ | 複雑な動きを実現 | 順序立てた論理思考 |

たとえば、魚を前に動かしたいとき、上記のようにメガネの中に「魚」を配置します。メガネの左から右へ、つまり魚が前に進むことになります。
とてもシンプルな操作ですが、これで魚が画面上を泳ぐアニメーションが完成します。
具体的な作品例として、以下のようなものが初心者でも簡単に作れます。
- 花火が打ち上がる演出
- キャラクターが歩き回るゲーム
- 音楽に合わせて踊る図形
ビスケットの対象年齢と動作環境
対象年齢:4歳から大人までViscuitは年中・年長といった未就学児から始められて、実質的な上限年齢はありません。
大人の方が興味を持つケースも多く、家族みんなで一緒に楽しめる学習体験を提供しています。
動作環境と費用
- 必要な環境:インターネット接続とブラウザのみ
- 対応デバイス:パソコン、タブレット、スマートフォン
- 料金:完全無料(アカウント作成不要)
- インストール:不要(ブラウザでアクセスするだけ)
この圧倒的な手軽さこそが、Viscuitの大きな魅力です。
高価なソフトウェアを購入する必要も、複雑な初期設定に悩む必要もありません。思い立ったその瞬間から、すぐにプログラミングの世界に飛び込めます。また、デバイスを選ばないため、学校でも家庭でも同じ環境で学習を継続できます。
始め方の手順
1:公式サイト(viscuit.com)にアクセス2:「つくる」ボタンをクリック
3:キャンバスに絵を描く
4:メガネツールで動きを設定
5:実行ボタンで動作確認
特別なソフトウェアのインストールや有料登録は一切不要で、指一本でプログラムを作れる手軽さが魅力です。
Viscuit(ビスケット)と他のプログラミング教材との違い

他のプログラミング教材との比較
主要なプログラミング教材比較表| 教材名 | 対象年齢 | 操作方法 | 学習アプローチ | 特徴 |
| Viscuit(ビスケット) | 4歳〜 | 絵とメガネ | 直感的創作 | 文字不要 ユニークなシステム |
| Scratch(スクラッチ) | 8歳〜 | ブロック組み合わせ | 論理構造構築 | 豊富な機能 世界標準 |
| ScratchJr | 5歳〜 | 簡単ブロック | 基礎的論理思考 | タブレット特化 |
| プログラミングゼミ | 6歳〜 | ブロック | ゲーム形式学習 | 日本語対応 |
Viscuitならではの特徴
- 年齢の壁がない:4歳から大人まで同じツールで学習可能
- 創造性重視:論理的思考と創造力を同時に育成
- 言語の壁がない:文字を使わないため国際的に利用可能
- 直感的理解:複雑なプログラミング概念を視覚的に体験
文字を使わない直感的操作
これまでのプログラミング教材の多くは、ブロックを組み合わせたり論理構造を組み立てたりすることを基本としています。でも、Viscuitは文字や複雑なルールを一切使わず、絵と直感だけでプログラムを完成させる独特な設計を採用しています。
直感的操作による学習効果
- 覚えることが少ない:文字入力や複雑なコマンドが不要
- 試しやすい:失敗を恐れずに色々なアイデアを試せる
- 発想が自由:技術的制約から解放された自由な発想
- すぐ確認できる:設定した動きがすぐに確認できる
このアプローチにより、プログラミング学習のハードルを大幅に下げつつ、より創造的で自由度の高い学習体験を実現しています。
Viscuit(ビスケット)の教育効果とは

プログラミング的思考の習得
Viscuitでは、「メガネ」というユニークな仕組みが子どもたちのプログラミング的思考を自然に育みます。メガネの左右の輪に絵を配置し、動きの変化ルールを設定する過程で、原因と結果の関係性を直感的に理解できます。
プログラミング的思考の4要素とViscuitでの習得
1:分解:複雑な動きを単純なメガネの組み合わせに分ける
2:パターン認識:似た動きのメガネ設定を見つける
3:抽象化:具体的な絵から一般的な動きのルールを理解
4:アルゴリズム:意図した動きを実現するメガネの手順を考える
思い通りに動かない時、子どもたちは自然と「なぜだろう?」と考え始めます。メガネの設定を見直す試行錯誤が、問題を分析し解決策を見つける力を段階的に育ててくれます。
創造力と表現力の向上
Viscuitを使った創作活動は、子どもたちが頭の中のイメージを具体的な形にする貴重な体験となります。自分で描いた絵を「メガネ」で動かし、アニメーションやゲームなど色々な作品を制作する過程で、表現の幅は大きく広がります。

創造力育成の段階的プロセス
1:発想段階:「どんな動きにしようかな?」というアイデア創出
2:設計段階:「どのメガネでその動きを実現できるか?」という構想
3:実装段階:実際にメガネを設定して動きを作る
4:改善段階:思い通りにならない部分を修正・改良
感覚的に楽しみながら操作できる環境だからこそ、失敗を恐れずに挑戦し、創意工夫する力が自然と身についていきます。
問題解決力の育成

Viscuitでの学習では、子どもたちが思い通りの動きを実現しようと何度も挑戦する場面が生まれます。この「うまくいかない体験」こそが、失敗を前向きに捉える姿勢を育む貴重な機会となります。
問題解決力が身につく学習サイクル
- 問題発見:「思った通りに動かない」という気づき
- 原因分析:「メガネの設定のどこが違うのか?」という検証
- 解決策立案:「別の配置を試してみよう」という仮説設定
- 実行・検証:新しい設定で動作確認
- 振り返り:うまくいった理由・いかなかった理由の整理
簡単な操作性のおかげで、子どもたちはいろいろな設定を試せます。このプロセスを通じて、論理的に問題を考え、多様なアプローチを試す思考力が自然に身につきます。
年齢別・段階別の学習効果と特別支援教育での活用

それぞれの年齢段階で期待できる学習効果と、具体的な到達目標を紹介します。
年齢別の学習効果
4〜5歳(未就学児)- 因果関係の基礎理解(「こうすると、こうなる」)
- 色や形への興味向上
- 集中力の向上
6〜8歳(小学校低学年)
- 順序立てて考える力の育成
- 創造的な問題解決の体験
- デジタル表現スキルの基礎
9〜12歳(小学校高学年)
- 複雑なメガネの組み合わせによる高度な作品制作
- 他者との協働制作によるコミュニケーション力向上
- プログラミングの本格的な理解への橋渡し
特別支援教育での活用効果
Viscuitの視覚的な操作性は、特別支援教育の分野でも大きな力を発揮しています。- 発達障害のお子さま:視覚的理解が得意な特性を活かした学習
- 学習困難を抱えるお子さま:文字に頼らない自己表現の機会
- 読み書きが苦手なお子さま:文字入力不要で安心して取り組める環境
年齢や能力にかかわらず、同じツールを使ってそれぞれのペースで学べる点は、みんなが一緒に学べる教育の実現にも貢献しています。
Viscuit(ビスケット)の実践的な活用方法

家庭での効果的な取り組み方
学習環境の整備- おすすめデバイス:タブレットまたは大画面のパソコン
- 学習時間:初回15分から、集中力に応じて30〜45分まで延長
保護者の関わり方のコツ
- 一緒に始める
→最初は隣に座って一緒に絵を描く - 質問で思考を促す
→「どうしてこの絵を動かしたの?」と聞いてみる - 失敗を歓迎する
→「面白い動きになったね!」と前向きな反応をする - 作品鑑賞会
→完成した作品を家族で見る時間を作る - アイデア共有
→「今度はこんな動きにしてみたら?」と提案
効果測定の目安
- 1〜2週間:基本的なメガネ操作に慣れる
- 1ヶ月:自由に絵を動かせるようになる
- 3ヶ月:複雑な組み合わせで独創的な作品を制作
- 6ヶ月以降:他のプログラミング教材への移行も可能
Viscuitでの学習は、もちろんひとりひとり進度が異なります。じっくりゆっくりペースでも、どんどんガンガンペースでも、子どもの性格や意欲に合わせて進めていきましょう。
Viscuit(ビスケット)「学校現場での活用事例」
導入効果が確認された実践事例

横浜市立仏向小学校 特別支援学級での実践
- 対象:通級指導教室の児童
- 期間:1学期間(約3ヶ月)
- 成果:「できない」と感じていた児童が積極的に取り組む姿が見られた
- 測定結果:CABテストで児童全体の心的回転力が向上
こちらの事例では、「友達とのコミュニケーションが苦手な子が、4人用のゲームをプログラミングし作成して、様々な人に自分から声をかけ、一緒に楽しんでいた姿に感動した。」という教員からの感想が寄せられています。
『スモーステップで進む』『豊かで鮮やかな色彩』『自分で動かしているという感覚』が、さまざまな子どもたちにとっても、楽しいプログラミング学習となったようです。
参考:ビスケットによるプログラミング入門/総務省
一般的な授業での導入効果
- ICTスキル向上:教師のデジタル教材活用への意識改善
- 発見の場:これまで見えなかった児童の能力を発見
- 協働学習促進:「みんなでつくる」モードでの共同制作
教科を超えた活用例
- 図画工作:デジタルアートとしての創作活動
- 算数:座標や図形の移動を視覚的に理解
- 国語:ストーリー性のある作品制作で物語構成力を育成
Viscuit(ビスケット)を活用しているワークショップ・教室選びのポイント
講師の質を見極めるポイント- 指導経験:Viscuitの特性を理解した指導ができるか
- ファシリテーション能力:子どもの創造性を引き出せるか
- 年齢対応力:参加者の発達段階に応じた指導ができるか
教室・ワークショップの選び方チェックリスト
- 一人ひとりのペースに配慮した指導体制
- 創作中心で自由な発想を重視している
- 作品発表・共有の機会がある
- 体験会で実際の雰囲気を確認できる
これらの観点が重要な理由は、Viscuitの学習効果を最大化するためです。画一的な指導では、子どもたちの創造性や個性を伸ばすことができません。
特に「作品発表・共有の機会」は、子どもたちの学習意欲を高め、コミュニケーション能力の育成にも繋がる重要な要素です。体験会への参加は、教室の雰囲気や指導方針を直接確認できる貴重な機会なので、活用することをおすすめします。
料金相場と選択基準
- 体験ワークショップ:1,000〜3,000円/2時間
- 継続コース:月額5,000〜10,000円(月2〜4回)
- 選択基準:料金よりも指導の質と教育方針を重視
※料金は地域や時期により変動するため、あくまで目安として参考にしてください。最も大切なのは、子どもが楽しく学べる環境かどうかです。
Viscuitに関するFAQ(よくある質問)

Q: Viscuitは本当に完全無料ですか?
A: はい、Viscuitは完全無料で利用できます。アカウント作成も不要で、公式サイトにアクセスするだけですぐに始められます。
Q: 他のプログラミング言語を学ぶ前にViscuitをやる意味はありますか?
A: Viscuitでプログラミングの本質的な考え方(条件分岐、繰り返し、順次処理)を直感的に理解できるため、その後のScratchやPythonなどの学習がスムーズになります。
Q: 子どもが飽きてしまった場合の対処法は?
A: 新しいお題を提案したり、家族で作品鑑賞会を開いたりして、変化をつけることが効果的です。また、「みんなでつくる」モードで他の人の作品を見ることで刺激を受けることもあります。
まとめ
Viscuitは、絵を描くだけでプログラムが作れる魅力的なプログラミング教材です。4歳から始められる手軽さと、文字を使わない直感的な操作性により、子どもたちが自然にプログラミング的思考を身につけられます。Viscuit(ビスケット)の主な特徴
- ユニークな「メガネ」システムによる視覚的プログラミング
- 完全無料でアカウント作成不要
- 創造力と論理的思考力を同時に育成
- 特別支援教育でも高い効果を実証
これまでのプログラミング教材とは一線を画す創造性重視のアプローチにより、子どもたちの隠れた才能を引き出し、楽しみながら学習を進められる点が最大の魅力です。
プログラミング教育の入り口として、また創造的な表現活動として、Viscuitは現代の子どもたちにぴったりな学習ツールといえるでしょう。まずは公式サイトで実際に体験してみることをおすすめします。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
Viscuit(ビスケット)とは?無料でプログラミング学習ができる?
2020年4月より小学校でプログラミング教育が必修化します。この記事では「コンピュータは粘土だ!!」というポリシーで開発された、対象年齢4歳以上のビジュアルプログラミング言語Viscu...
2025.11.17|プログラミング教室ガイド
-
ボードゲームでプログラミング? | 論理的思考力が身につくボードゲームまとめ(おすすめです!)
プログラミング教育が必修化します。ねらいは「論理的思考力(プログラミング的思考)の育成」。この記事ではパソコンがなくてもプログラミング的思考が鍛えられる、子どもにおすすめのボードゲーム...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
プログラミング教育とは?定義・目的・必修化の理由と子どもが育む3つの力
プログラミング教育が必修化されて数年が経ちましたが、子どもたちがどのようなことを学び、将来にどうつながるのか、気になっていませんか。プログラミング教育は単なる技術の習得ではなく、論理的...
2025.10.02|大橋礼
-
プログラミング教育で論理的思考力を鍛える!子どもの未来を切り開く学びとは?
プログラミング教育の目的は「論理的思考力」を育てること。でも、「論理的思考力」ってそもそも何なのでしょうか?「相手を思いやる能力」でもある論理的思考力は、これからの時代に欠かせない力。...
2025.06.24|プログラミング教室ガイド
-
Scratchとは?基本的な使い方とプログラミングを始める方法を解説
子どもや初心者がプログラミングを学ぶ第一歩として、Scratch(スクラッチ)は最適です。ブロックを組み合わせるだけで簡単に動きを作り出せるので、楽しさを感じながら論理的思考力を養えま...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部