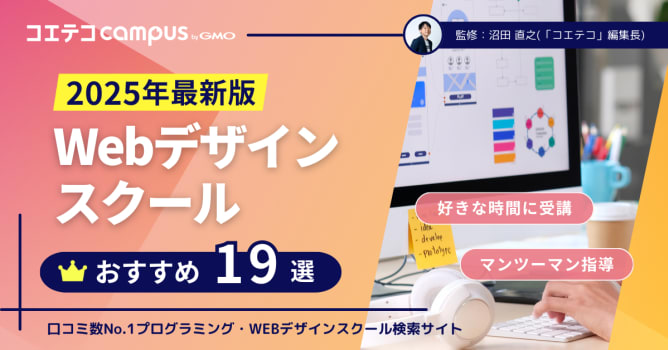お金の勉強は何から始めるべき?初心者向けにアプリも徹底解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
すでに小・中・高での教育が義務化されているほど、昨今その重要性が叫ばれている「金融教育」。言ってみれば「お金の勉強をしよう」ということなのですが、大切さを何となく理解していながらも「実際どんな勉強をしたらいいのかわからないんだよな…」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では「何から勉強すればお金の知識が身につくの?」という疑問を解消すべく、まず最初に取り組むべき内容や、おすすめの勉強方法について徹底解説していきます。
「お金に関するリテラシーを高めて、より良い生活を送りたい!」「怪しい情報に振り回されないよう、最低限の知識を持ちたい!」と考えている人は、ぜひ最後までご覧ください。
お金の勉強はまず何から始めるのが正解?
一口に「お金の勉強」と言っても、漠然としすぎて何から始めればいいのか分からなくなってしまうかと思います。そんな時は、金融系の資格である「FP(ファイナンシャルプランナー)」の試験科目を参考にするのがおすすめ。備えておきたいお金の知識を6項目に分類してくれているので、やるべきことを明確化しやすくなっています。
参考:おすすめのFP相談窓口
ライフプランニングと資金計画
ほぼ知識ゼロの状態から始めるのであれば、一つ目の「ライフプランニングと資金計画」に関連する内容から勉強してみるといいでしょう。その科目名からもわかる通り、安心できる将来設計に必要不可欠なライフプランニングの方法のほか、社会保険や公的年金、その他税金に関する内容も身につけることができます。国から提供される公的保険で受けられる内容をしっかりと理解するだけでも「不必要に民間保険に入る必要はないんだ」「年金だけでも将来毎月これくらいもらえるんだ」といったように、どんどん不安が解消されていくはずです。
もちろん、その他科目についても重要なお金の知識であることには変わりありません。ライフプランニングや公的保険について学び終わったら、自分の生活に関与しそうなもの・単純に勉強してみたいと興味があるものなどから、どんどん学習を進めていってみてください。
株式投資を始めたいけれど、どの銘柄を選ぶべきか迷っているという初心者には、AI株価予想アプリがおすすめです。AI株価予想アプリは、過去のデータや最新の市場トレンドを分析し、将来の株価を予測してくれます。高度なアルゴリズムを駆使したAIが、初心者でも簡単に投資の判断を下せるようサポートしてくれるため、効率的かつ効果的な資産運用が実現するでしょう。この記事では、AI株価予想アプリのおすすめ5選と...
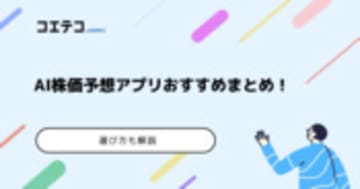

2026/01/22

リスク管理
お金の勉強をする時には、日常生活を営む上で避けることのできないリスクに対する知識を深めていくことも必須。リスクマネジメント・保険制度金融・生命保険・損害保険などの知識を深めることで、リスク管理に関する知見を身に付けていくことができるでしょう。
リスク管理ができるようになると、自身の大切な資産を低リスクで増やしたり、リスクの高い投資を避けられるようにもなります。
株式投資のシミュレーションアプリとは、アプリ上で仮想のデモトレードを行えるアプリです。シミュレーションアプリで資金を使わず株トレードを体験することで、株式投資のカンを掴みやすくなります。この記事では、株式投資初心者におすすめのシミュレーションアプリをピックアップしました。アプリを選ぶポイントやメリット・デメリットと併せてチェックしてみてください。
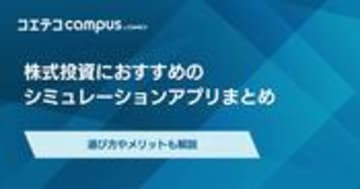

2026/01/02

金融資産運用
近年投資への注目が集まり、多くの人が興味・関心を抱いている金融資産運用。ただし、正しい知識を以って運用しなければ、大きな損害を被ることも。
お金を勉強する一貫として金融資産運用についての知識を深めるのであれば、マーケット環境の理解や金融資産運用の最新の動向把握から努めてみましょう。これまで見えていなかった資産運用市場の流れを掴めるでしょう。
さらにその上で預貯金金融類似商品・投資信託・株式・仮想通貨(暗号資産)など、興味のある金融資産運用について勉強してみてください。
この記事では、初心者でも安心して受講できるマネーセミナーを厳選してご紹介します。この記事を読むことで、自分に合ったセミナーを見つけ、効率よくお金の知識を身につけられるようになるでしょう。
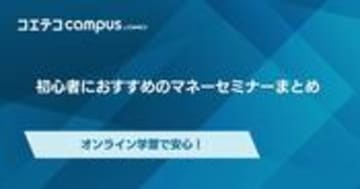

2026/01/12

AI株価予想アプリや株シミュレーションアプリなどもありますので、初めての方でも安心です。
タックスプランニング
タックスプランニングとは、『 タックス(tax):税金』『プランニング(planning):計画』を組み合わせた造語であり、将来の法人税等の発生に関する計画を行うことを意味します。将来に発生し得る納税額を予測することは、企業運営における「資金繰り」を予測する上で重要な意味を持ちます。
税金は複雑であり、学びにくい一面がありますが、税知識を深めることで個人での事業や不動産経営にも役立つでしょう。
株式投資のシミュレーションアプリとは、アプリ上で仮想のデモトレードを行えるアプリです。シミュレーションアプリで資金を使わず株トレードを体験することで、株式投資のカンを掴みやすくなります。この記事では、株式投資初心者におすすめのシミュレーションアプリをピックアップしました。アプリを選ぶポイントやメリット・デメリットと併せてチェックしてみてください。
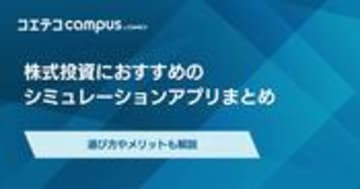

2026/01/02

不動産
不動産に関する知識も、お金とは切り離せない部分があります。取引・不動産に関する法令上の規制・不動産の取得、保有に係る税金・不動産の譲渡に係る税金・不動産の証券化など、不動産とお金が絡む場面・事案は多々あります。
参考:おすすめのネット証券
私生活における不動産保有においても役立つ知識を会得できるでしょう。
相続・事業承継
相続や事業承継は、相続税や贈与税などを学ぶカテゴリーであり、知識を深めておきたい人も多いのではないでしょうか。特に相続問題は、誰しもが必ず通る身近な問題です。仮に相続額が0円だとしても、申告が必要になるケースも多々あります。
正しい知識を持っていることで、いざという時にもスムーズに相続手続きを行うことができるでしょう。
また贈与税についても、「知らなかった!」では済まされない税知識を学ぶことできます。
人生の役立つ知識を得られるため、ぜひ学んでおきたい項目と言えるでしょう。
参考:おすすめのFP相談
初心者がお金の勉強をするうえで大切なのは目的を明確化すること
お金の勉強を行う際に最も重要にしてほしいポイントは「学ぶ目的を明確にすること」です。ここは人によって様々かと思いますが、例えば以下のようなものが挙げられるでしょう。- 将来の不安を軽減したい
- 金融トラブルから自分や家族を守りたい
- 老後の資金を確保したい
- 余裕のある生活を送りたい etc…
「なぜお金に関する知識を身につけたいのか」「お金について学んでその後どうしたいのか」を大まかにでも決めておかないと、当然何から勉強すればいいのか分からなくなってしまいますし、モチベーションが続かず、途中で投げ出してしまう可能性もあります。効率よく、かつ確実にお金の知識をつけていくためにも「なぜ学ぶのか」は自分の中ではっきりさせておくようにしたいところですね。
お金の勉強をして、NFTや暗号資産(仮想通貨)などで収益も上げることも可能なので、興味がある方は調べてみることをお勧めします。
参考:NFTマーケットプレイス
参考:仮想通貨取引所おすすめ
お金の勉強におすすめのサービス5選
これからお金の勉強を始めるなら、投資スクールやマネーセミナーなど各種サービスを活用するのもおすすめです。ここでは勉強におすすめのサービスを紹介します。ABCash

専任トレーナーによる週1回の1on1トレーニングやLINEでの相談、投資デビューの伴走など、学習から実践まで切れ目のない支援が特徴。家計の見直しや資産形成、NISA・iDeCoの活用、投資スタイルの確立など幅広いテーマに対応し、短期的には支出への意識改善、中期的には貯金や支出管理の習慣化、長期的には資産設計や自己肯定感の向上といった変化を実感できます。
日常のお金の整理から長期的な資産づくりまでプロが伴走することで、未経験でも安心して取り組める点が魅力。「わかったつもり」で終わらせず、人生を前に進めるための実践的な学びを提供してもらえるでしょう。
バフェッサ
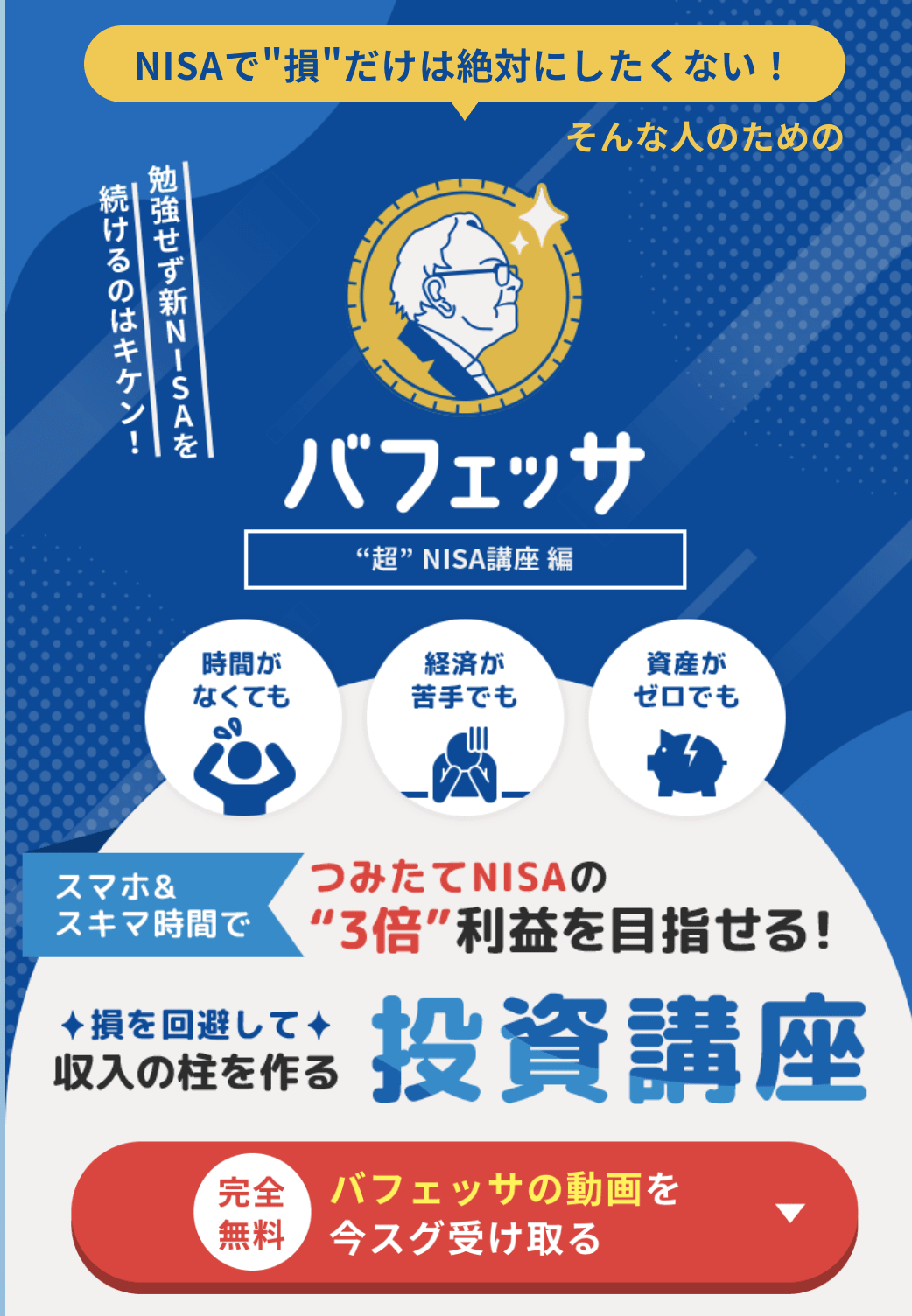 「バフェッサ」は、東京商工リサーチにおいて、生徒数、講義数、講師数の3部門において「日本一の投資オンラインスクール」と認定された投資スクールGFSを展開する株式会社GFS Educationが提供する投資講座です。
「バフェッサ」は、東京商工リサーチにおいて、生徒数、講義数、講師数の3部門において「日本一の投資オンラインスクール」と認定された投資スクールGFSを展開する株式会社GFS Educationが提供する投資講座です。本講座では、世界的な投資家ウォーレン・バフェット氏の投資戦略を基盤とし、日本の新NISA制度に最適化された投資手法を学ぶことができます。その内容としては、バフェット氏がなぜ投資だけで世界一の富豪になれたのかという根本的な理由から始まり、彼の投資哲学、投資における重要なルール、そして具体的な投資判断の考え方まで多岐に渡ります。
難しい専門用語は極力使わず、数字が苦手な人でも理解できるように工夫されているため、投資の知識が全くない方でも安心して学ぶことができるとのこと。
投資に興味はあるものの、費用面で投資の勉強に躊躇していた人や将来の経済的な不安を解消したいと考えている人、NISA制度を活用して資産形成を始めたい初心者は、ぜひ本講座を視聴し、将来に向けた資産形成に役立ててみてはいかがでしょうか。
moomoo

投資情報が充実しているのも特徴。売買のタイミングを見るときに役立つ大口投資家売買や、値動きの予測をチェックできるチャート予測、投資の神様とよばれるウォーレン・バフェットが最近売買した銘柄などで、投資に関する知識を深められます。
日本株取引手数料やNISA全商品取引手数料が0円なのもポイント。手数料が無料のため余計な費用をかけずに投資にチャレンジできます。
参考:moomoo証券の評判
松井証券
松井証券は、投資情報動画メディアの「マネーサテライト」を運営しています。
マネーサテライトは、楽しみながらお金・投資の勉強をしたい方向けのサービス。
アナリストによる相場の見通しや市況の解説番組、芸能人を起用した投資情報トーク番組など、さまざまなコンテンツが揃っています。
投資初心者から経験者まで、幅広い方が楽しめる内容になっているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。無料で閲覧できるのに、毎日更新されるという充実度も魅力です。
Coincheck

口座開設は最短5分で完了。暗号資産の購入も最短10秒でできるため、思い立ったらすぐに取引を開始できます。任意のタイミングでの取引はもちろん、積み立てができるのも特徴。月1万円から積み立てる長期投資なら、初めての暗号資産でも取り組みやすいでしょう。
気軽に実践することで、暗号資産についての知識が身に付きやすくなるサービスです。
お金の知識を身につけるおすすめの勉強方法
ここからは、お金の知識を身につけるための具体的な勉強方法について解説していきます。世の中にはいろいろな情報が公開されていますが、そのどれもが正しいとは限らないため、しっかりと取捨選択をしていくことが重要です。誤った知識を吸収してしまわないためにも、ぜひここで紹介する方法を参考にしてみてください。- 金融庁の学習教材を活用する(公式サイト・YouTube)
- FP(ファイナンシャルプランナー)の参考書・問題集に取り組む
金融庁の学習教材を活用する(公式サイト・YouTube)
小・中・高での金融教育義務化が始まって以降、金融庁ではさまざまな教材を無料で公開しています。中でも、公式サイト上で中学生・高校生や社会人に向けて提供されている「基礎から学べる金融ガイド」では、家計管理・生活設計の方法から、詐欺等のトラブルに巻き込まれないためのTips等についてまで、全40ページで詳細にまとめてあり非常に有用。迷ったらまずは金融庁の教材を読んでみることから始めるといいでしょう。また公式YouTubeチャンネルの方でも、金融トラブルの注意喚起や資産形成に向けたセミナー等が、動画でわかりやすく解説されています。テキストベースよりも動画・音声があった方がわかりやすいという人は、YouTubeを活用するのもおすすめです。
お金にまつわる資格の参考書・問題集に取り組む
先にも少し触れた通り、お金の勉強をする際にFP(ファイナンシャルプランナー)の試験内容を絡めるのは非常に効果的。市販されている参考書や問題集を購入して、一通り取り組んでみるだけで、必要なお金の知識があらかた身につくといっても過言ではありません。FPと言えば「お金の専門家」というイメージが強く「お金の勉強初心者の自分ではとてもついていけない…」とやる前から諦めてしまう人も多いかと思います。しかし、少なくとも1〜3級あるうちの一番入門である3級に至っては「人が生きていくうえで最低限知っておきたいお金の知識」がメインに出題されている、ということを頭に入れておきましょう。FPを生業としていなかったとしてもぜひ身につけたい内容が目白押しです。
実際にFPの試験を受けるかどうかは別にしても、参考書や問題集を活用して学習することには大きな意味があります。最初から体系的にカリキュラムが組まれているということもあり「どんな内容から始めたらいいかわからない」という人に特におすすめの方法です。
無料マネーセミナーに参加する
いきなりお金の勉強に対しお金を掛けることに抵抗を感じる人もいるでしょう。また「何から学び始めたら良いのか?」と迷う人も少なくありません。
そのような人は、無料のマネーセミナーや投資スクールに通うことを検討してみることも1つ。
家計管理や貯蓄をはじめ、保険、投資、税金対策など、様々なテーマを取り扱ってるため、いくつかの主題の違うテーマのセミナー参加してみてください。複数のセミナーに参加することで、学びたいお金の知識が明確になるでしょう。
この記事では、初心者でも安心して受講できるマネーセミナーを厳選してご紹介します。この記事を読むことで、自分に合ったセミナーを見つけ、効率よくお金の知識を身につけられるようになるでしょう。
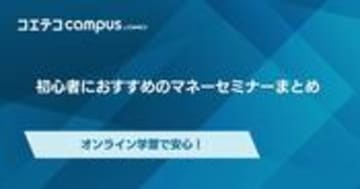

2026/01/12

お金の知識に関する本を読む
お金の知識に関する本を読んでみるのもおすすめです。どんな本を読むべきか迷う人は、自分の気になる分野や興味のあるジャンルの本を選ぶ良いでしょう。
それでも迷うようであれば、図書館などで読みやすい本を探してみるのもおすすめです。様々なお金にまつわる本を読んでみることで、自分の欲する情報がはっきりしてくるでしょう。
また活字に抵抗がある人は、漫画や雑誌など勉強に取り組みやすい媒体を選ぶのも1つ。
ある程度知識が深まってくれば、活字が多い本でも楽しく読み進めていけるようになるでしょう。
FP(ファイナンシャルプランナー)に相談する
FP(ファイナンシャル・プランナー)は、家計に関わる金融知識を備えており、一人ひとりの将来の夢の実現や、お金にまるわる悩み解決に向けてサポートする専門家です。そんなFPからの現状分析やプランニング、実行支援を受けることで、お金としっかり向き合えるようになるでしょう。
放置しがちだったお金の問題に対し、リアルな回答を受けることで、実体験を通じながらお金に関する知識を吸収していくことができるようになります。
FP相談窓口とは、FP(ファイナンシャルプランナー)が家庭ごとの「お金の悩み」について相談に乗ってくれるサービスです。経済的な悩み・将来の不安解消に有益ですが、「どのFP相談窓口がよいか分からない」という声も少なくありません。 本記事では、FP相談窓口を利用したい人に向け、おすすめのFP相談窓口や選び方をご紹介します。
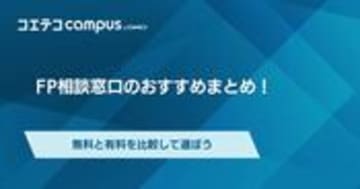

2026/01/26

お金の情報を発信しているSNSやYouTubeをチェックする
お金の情報を発信しているSNSやYouTubeをチェックすることもお金の知識を学ぶ上で有効です。SNSやYouTubeでは、お金に関する知識がない人でも理解できるよう、かみ砕いて解説してくれています。また動画であれば1講座あたり10分~30分程度のボリュームのため、スキマ時間にお金の知識を学べる点も魅力と言えるでしょう。
ただし、SNSやYouTubeで発信されている情報は全てが根拠ある情報だという保証はありません。
SNSやYouTubeの情報をベースに学習するのであれば、確かな情報発信元が配信している情報をチェックするようにしましょう。
金融リテラシーを向上できるアプリやゲームをする
金融リテラシー向上に繋がるゲームやアプリを活用するのも良いでしょう。金融リテラシーを向上できるアプリやゲームには、次のようなものがあります。
- 株のトレード練習ができるアプリ・ゲーム
- デモトレードでFX投資の練習できるアプリ
- 初心者でも簡単に仮想通貨の相場を学べる本格取引機能付いたアプリ
- AI株価予想アプリ など
子どもでも活用できるアプリやゲームもあるため、学びたいお金の知識や難易度に合わせてアプリ・ゲームを選んでみましょう。
参考:株シミュレーション
株式投資のシミュレーションアプリとは、アプリ上で仮想のデモトレードを行えるアプリです。シミュレーションアプリで資金を使わず株トレードを体験することで、株式投資のカンを掴みやすくなります。この記事では、株式投資初心者におすすめのシミュレーションアプリをピックアップしました。アプリを選ぶポイントやメリット・デメリットと併せてチェックしてみてください。
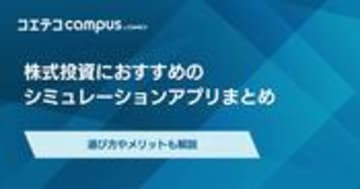

2026/01/02

投資や家計簿に挑戦する
家計簿をつけて家庭の会計を見直す、少額から投資を始めお金の流れを把握することなども、お金の知識を身に付ける上で有効だと言われています。このように知識をインプットするだけではなく、自分なりにアウトプットに取り組むことで、ただ本を読んだりセミナーに参加したりするよりもずっと理解が深まるでしょう。
特に家計簿は、思い立ったその日から始められます。まずは1ヶ月の収支把握から始めてみてはいかがでしょうか。
参考:おすすめのロボアドバイザー
お金の勉強をする上で取得がおすすめな資格
ここでは、お金の勉強をする上で取得をおすすめしたい資格を紹介します。参考:通信講座おすすめ
FP(ファイナンシャルプランナー)
お金に関する資格と言って思い浮かぶ資格と言えば、FP(ファイナンシャルプランナー)ではないでしょうか。FPの資格取得に向けて勉強する際は、「ライフプランニングと資金計画」「金融資産運用」「タックスプランニング」「リスク管理」「不動産」「相続・事業承継」の6つのカテゴリーを勉強しなければなりません。
関連記事:FP通信講座おすすめ3選!2級・3級資格の難易度も徹底解説
いずれも私達の生活に密着したお金の知識であり、資格の勉強を通じてライフプランと絡めたお金の設計を行えるようにもなるでしょう。
なお、FPの資格には国家資格である「FP技能士」と民間資格である「AFP」「CFP®」の2つがあります。
関連ページ:ユーキャンFP講座の評判
| 検定名 | FP(ファイナンシャルプランナー) |
| 資格種類 |
■国家資格 3級FP技能士 2級FP技能士 1級FP技能士 ■民間資格 CFP® AFP |
| 合格率 | 3級FP技能士:学科試験 74.78 %、実技試験 77.67% 2級FP技能士:学科試験 53.54%、実技試験 52.02% 1級FP技能士:96.2% CFP®:6.7% AFP :FP講座(AFP認定研修)を修了し、2級FP技能士に合格すれば取得可能 |
| 試験日 | 3級FP技能士:例年5月・9月・翌年1月 2級FP技能士:例年5月・9月・翌年1月 1級FP技能士:例年9月 CFP®:例年6月・11月 AFP:試験なし |
| 主催者 | 国家資格:NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(FP協会) 民間資格:一般社団法人金融財政事情研究会 |
簿記2級・3級
資格勉強で通じて得た知識をビジネスの場で活かしたいと考えるのであれば、簿記2級・3級がおすすめです。簿記は、企業の支出入を記録する手法であり、健全な経営活動に欠かせない工程です。
簿記2級・3級は、資格の勉強を通じて企業や事業のお金の流れを学ぶことができるでしょう。
関連記事:簿記2級の勉強方法
3級の合格率は50%ほどであり、主婦や学生の受検者も多くいます。
関連記事:簿記3級に独学で合格するための勉強法
お金の勉強を始めたいと考えるのであれば、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
| 検定名 | 日商簿記検定 |
| 資格種類 | 1級、2級、3級、簿記初級 |
| 合格率 | 2級:15~30% 3級:40~50% |
| 試験日 | 2級:例年6月・11月・翌年2月 3級:例年6月・11月・翌年2月 |
| 主催者 | 日本商工会議所 |
宅地建物取引士
宅地建物取引士は国家資格の1つであり、宅地建物の取引に関係する知識を学習できる資格です。2024年度の合格率は、18.6%と難易度の高い資格ではありますが、不動産業では事業所ごと5人あたり1人以上の宅建士を置かなければならないと定められています。
そのため、日々の生活を営む上で役立つお金の知識だけではなく、就職や転職活動に役立ちやすい資格とも言えます。
また自身の不動産管理にも役立つため、総合的に役立つお金の資格を取得したい人におすすめです。
参考:宅建通信講座・塾おすすめ比較ランキング3選
関連ページ:アガルート宅建講座の評判
| 検定名 | 宅地建物取引士 |
| 資格種類 | ー |
| 合格率 | 15%~18% |
| 試験日 | 例年10月の第3日曜日 |
| 主催者 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 |
マンション管理士
マンション管理士も国家資格の1つであり、賃貸物件の管理にまつわる知識を学べる資格です。関連記事:アガルートのマンション管理士試験・管理業務主任者試験対策講座
合格率は、10.1%と宅地建物取引士よりも難易度の高い資格ですが、社会的ステータスを高められる可能性のある資格です。キャリアチェンジやキャリアリメイクにも役立つという声も。
また宅地建物取引士や管理業務主任者といった他の資格とW保有することで、不動産業界の枠を超えて資格勉強で得た知識を活かせるでしょう。
| 検定名 | マンション管理士 |
| 資格種類 | ー |
| 合格率 | 8~11% |
| 試験日 | 例年11月 |
| 主催者 | 公益財団法人マンション管理センター |
年金アドバイザー3級
年金アドバイザーとは、銀行業務検定協会が実施している民間の資格の1つ。受講生の8割は金融業界に身を置く人であることから、専門性の高い資格と言えるでしょう。
なお本資格を保有することで、年金や公的保険に関する専門的知識を有していることを証明できます。
年金アドバイザーには、2級~4級までの階級が設けられており、1級は存在しません。
3級から受験に挑戦する人が多いようですが、4級と比較して難易度はグッと高まります。
しかし3級は基礎的な知識を問う設問と実践的な応用力を試される設問の両者が出題されます。そのためお金の知識を学ぶ上で必要な知識を網羅的に習得できるとして、非常に人気があります。
| 検定名 | 年金アドバイザー |
| 資格種類 | 2級・3級・4級 ※1級はなし |
| 合格率 | 2級:20.49% 3級:22.08% 4級:43.23% |
| 試験日 | 2級:例年3月 3級:例年3月、10月 4級:例年3月 |
| 主催者 | 銀行業務検定協会 |
お金の勉強は何歳から始める?
りそなグループが自社社員に対して行った金融教育に関するアンケートによると、『何歳からの金融教育が大切だと思いますか?』という質問に対して、回答者の多くが「小学生頃から」と回答しました。ある程度お金の概念を理解でき、お買い物など「自分でお金を使える年齢になる頃からお金の勉強を始めたほうが良い」と考える人が多いようです。

しかし老後・年金・保険など、適齢に勉強することでより有益な情報を得られることもあります。そのため、一口にお金の勉強と言っても年齢に合った勉強が大切と言えるでしょう。
そのため、大人になってからお金の勉強を始めても決して遅くはありません。年齢や状況に合ったお金の情報を得られるよう努めることも大切です。
参考:子どものお金の勉強アプリ
年代別でおすすめのお金の勉強
続いて、年代別でおすすめのお金の勉強を紹介します。4歳~10代前半
近年では、子どもたちの経済的自立を促すために金融リテラシーを高めることが必須だと言われるようになりました。そのため、幼稚園や小学生ごろからお金に関する教育を実施する保護者・教育機関も増えつつあります。幼稚園頃は、保護者との買い物体験を通じてお金の概念やお金の使い方を理解していく年齢です。
また小学生低学年頃は、お金の使い方の選択や貯蓄を学ぶと良いでしょう。またお金は無限にあるわけではなく、労働や投資などで増やしていかなければならない旨も学べるよう工夫してみましょう。
また小学生高学年になると、現金以外の支払い方法や、お金の貸し借り、投資なども少しずつ理解できるようになります。
金融庁のサイトでは、小学生向けのお金について学べるサイトが集約されています。
このようなサイトなども活用しながら、お子さまの興味・関心に合わせてお金の勉強に取り組んでみましょう。
日本ではあまり「お金の教育」に対して積極的ではありませんでした。しかし最近は金融教育の重要性が見直されています。 人生設計とマネープランが重要なことは明らかなものの、いったいどうやって小学生や中学生の子どもたちに教えればいいのでしょうか? 今回の教育トピックでは手軽に利用できるマネー教育アプリ・サイト・ゲームを紹介。親子で遊びながら、金融リテラシーを身につけていきましょう!
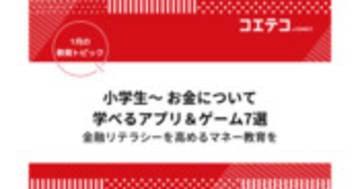

2026/01/27

10代・20代
お金の勉強を開始するのに、年齢の制限はありません。むしろ若い時からお金の勉強に取り組み、マネーリテラシーを高めておくことで、ビジネスや日々の生活に必要な知識を早くから習得できるでしょう。
中でも10代・20代であれば、「社会保険」や「公的年金」、「税金」など、日々の生活の中で触れることの多いお金の知識習得を目指しましょう。
この記事では、初心者でも安心して受講できるマネーセミナーを厳選してご紹介します。この記事を読むことで、自分に合ったセミナーを見つけ、効率よくお金の知識を身につけられるようになるでしょう。
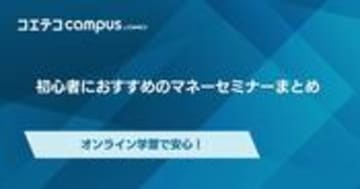

2026/01/12

30代・40代
30代・40代は、将来に向けて資産を形成していきたい時期。そのため、「保険」や「金融資産運用」について学び、保険加入や資産運用を検討していくのも良いでしょう。
またこの時期は、結婚・出産など家族構成やライフステージの変化が激しい時期。
家族構成やライフステージの変化を伴うごとに、ライフプラン設計や資金計画を見直してみるのもおすすめです。
マネーセミナーに参加してみたいけれど「どれを選べばよいかわからない」「怪しいセミナーに騙されないか不安」と感じるも多いでしょう。 今回は、初心者でも安心して参加できるおすすめのマネーセミナー3社を厳選し、オンライン・対面・無料・有料の違いから選び方のポイントまで詳しく解説します。 怪しいセミナーの見分け方や参加当日の流れも紹介。 ...


2026/01/26

50代〜
50代以降は、老後に関するお金の知識を学びましょう。特に「資産運用」や「年金」など、大半の人が関わる知識から重点的に学ぶと良いでしょう。
他にも「相続」や「医療・介護」に関するお金についても勉強しておくことで、後悔のないお金の運用・使い方を実現できるでしょう。
またお金の知識習得だけではなく、老後を安心して迎えられるよう、老後の資金計画についても考えておくようにしましょう。
お金の勉強をするメリット
ここでは「お金について勉強した方がいいとはわかっているけれど、中々その意味が見いだせない…」「どんないいことがあるの?」と考えている人に向けて、お金の勉強をする特に大きなメリットを3点ほどご紹介します。- 将来への漠然とした不安が解消される
- 不必要な出費を削減でき貯金につながる
- お金が絡むトラブルに騙されにくくなる
子どもの教育資金や自分達の老後資金への漠然とした不安が解消される
お金に関する知識が不足していると「このままでは将来お金が足りないかもしれない」「子どもの望む学校に進ませてあげられないかもしれない」といったような、確証のない漠然とした不安に悩まされてしまいがち。しかし、しっかりとお金の勉強をして知識を身につければ「いつ頃までのいくら必要だから、毎月〇〇円貯金すれば大丈夫」「万が一大きな病気にかかってしまったとしても、公的保険があるから何とかなる」といった形で、お金に関する悩みに対して自分なりの答えを導き出せるようになるのです。
将来に対する不確かな不安に頭を抱える必要がなくなるというのは、大切な人生をより有意義に過ごせるようになるという観点でも、大きなメリットと言えるでしょう。
不必要な出費を削減でき貯金につながる
正しいお金の知識を身につけると、自分に不必要な出費を見極める力がつきます。簡単な例で言えば保険。社会保険に「高額療養費制度※」があることや、万が一亡くなってしまった場合に公的年金から最低限の遺族年金が下りることなども理解していれば、必要以上に不安を感じて民間保険を増やす必要はない、ということが分かるはず。
※「高額療養費制度」とは出費が少なくなれば、それだけ多くのお金を貯蓄に回せるようになります。知識を身につけるだけで節約・貯金につながることを考えると、お金の勉強は非常にコスパがいいと言えるのではないでしょうか。
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度。
ex.)年収156万~約370万円世帯の場合、57,600円以上支払った分は払い戻しが受けられる
参照:厚生労働省保険局|高額療養費制度を利用される皆さまへ
社会保障や税金の知識を身につけることで節税につながる
お金の勉強をすることで、金融知識を活かし節税につなげることもできます。サラリーマンでも行える節税対策には、次ようなものがあります。
- ふるさと納税
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制
- 地震保険料控除
- 住宅借入金等特別控除
- NISA(少額投資非課税制度)
- iDeCo など
例えば、ふるさと納税の場合、控除上限額の範囲内であれば、寄付をした金額分が翌年の住民税額から控除されます。
このようにお金の勉強をしておくことで、 社会保障や税金の知識が身に付き、節税に対しても適切に対処できるようになるでしょう。
マネーセミナーに参加してみたいけれど「どれを選べばよいかわからない」「怪しいセミナーに騙されないか不安」と感じるも多いでしょう。 今回は、初心者でも安心して参加できるおすすめのマネーセミナー3社を厳選し、オンライン・対面・無料・有料の違いから選び方のポイントまで詳しく解説します。 怪しいセミナーの見分け方や参加当日の流れも紹介。 ...


2026/01/26

お金が絡むトラブルに騙されにくくなる
毎年1万件以上の詐欺(特殊詐欺)が認知されているほど、お金が絡んだ事件・事故は後を絶ちません。警察庁の資料によれば、令和4年度の特殊詐欺の認知件数は17,570件、被害額にして370.8億円とのこと。正しいお金の知識を備えておくことで、このようなお金に関するトラブルから自分を守ることができるというのも大きなメリットでしょう。
例えば「年利50%」といった謳い文句で勧誘してくる特殊詐欺。投資の神様と称される「ウォーレンバフェット氏」ですら、その生涯利回りは20%程度だったということを考えると、明らかに怪しいことがすぐにわかります。このように「こんな上手い話があるかな?」と疑いにかかれるようになるにも、最低限の知識は身につけておいた方が安心です。
FP相談窓口とは、FP(ファイナンシャルプランナー)が家庭ごとの「お金の悩み」について相談に乗ってくれるサービスです。経済的な悩み・将来の不安解消に有益ですが、「どのFP相談窓口がよいか分からない」という声も少なくありません。 本記事では、FP相談窓口を利用したい人に向け、おすすめのFP相談窓口や選び方をご紹介します。
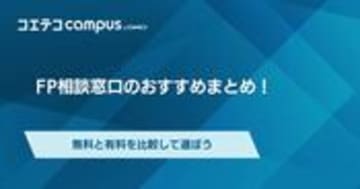

2026/01/26

資産運用・資産形成のポイントがわかることで貯金を増やせる
お金の勉強をすると、自然と資産運用・資産形成のポイントが分かるようになります。むやみに投資や資産運用に取り組むことが無くなるため、投資や資産運用にまつわるリスクを低減できるでしょう。またポイントを押さえた運用を実現することで、家庭の支出状況に合った方法でより効率的に貯金を増やしていくこともできるようになります。
無理に節約することなく、生活にゆとりを持ちながら貯金を増やせるようにもなるでしょう。
お金の勉強は何から始めたらいいのかまとめ
当記事では「お金の勉強をしなきゃとは思っているけれど、何から始めていいかさっぱり…」と悩んでいる人に向けて、おすすめのファーストステップや具体的な勉強方法についてまで、詳細に解説してきました。お金に関する知識は重要であるからこそ、間違った情報を記載した教材で学んでしまうことのないよう、細心の注意が必要です。
今回紹介したような、金融庁が直々に監修している資料や、厚生労働大臣に認められた国家資格であるFP(ファイナンシャルプランナー)のカリキュラムを参考にすれば、まず間違いはないでしょう。
正しいお金の知識は、将来の不安を解消してくれることはもちろん、特殊詐欺等のトラブルから身を守ってくれる強力な武器にもなります。金融教育の義務化が始まっている今、ぜひ面倒くさがることなく、自分のためにもお金の勉強に取り組んでみてください。
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
マネーセミナーおすすめ3選【2026年最新】怪しいのか無料サービスも比較
マネーセミナーに参加してみたいけれど「どれを選べばよいかわからない」「怪しいセミナーに騙されないか不安」と感じるも多いでしょう。 今回は、初心者でも安心して参加できるおすすめのマ...
2026.01.26|コエテコ byGMO 編集部
-
FP相談窓口おすすめ7選!無料と有料を比較【2026年最新版】
FP相談窓口とは、FP(ファイナンシャルプランナー)が家庭ごとの「お金の悩み」について相談に乗ってくれるサービスです。経済的な悩み・将来の不安解消に有益ですが、「どのFP相談窓口がよい...
2026.01.26|コエテコ byGMO 編集部
-
ネット証券会社おすすめランキング6選!新NISA口座も比較【2026年最新】
2025年1月から新NISAも始まり、投資による資産運用により一層注目が集まっています。しかし、投資を始めるための証券口座を開設しようにも、どこを選んだらいいのか迷ってしまう人は多いは...
2026.01.19|コエテコ byGMO 編集部
-
ETF銘柄おすすめ9選!日本・米国・海外・高配当それぞれ徹底解説
2024年から始まった新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能になり、より多くの金融商品を購入できるようになりました。この成長投資枠として話題になっているのが、ET...
2025.12.12|コエテコ byGMO 編集部
-
ネット銀行はやめた方がいい?ネットバンキングのデメリット・メリット比較
ネット銀行とは、インターネット上で取引できる銀行のこと。窓口に出向く必要がないので、いつどこでもスムーズな取引が可能です。その一方、ネット銀行には「デメリット」もあるので注意が必要。本...
2026.01.11|コエテコ byGMO 編集部