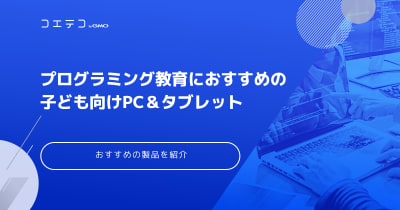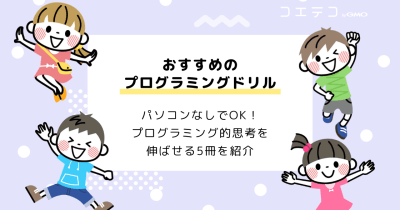プログラミングを習うのに必要な親のサポートは? | 知識がなくてもできること

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。また、詳しい最新情報については公式サイトをご確認ください。
そこでちょっと気になるのが「親はどんなことをすればいいの?」「サポートはどれくらい必要?」といった点です。たとえばプログラミングの知識がない親でもサポートできるのでしょうか? 家で予習復習する必要はあるのでしょうか?
今回はプログラミングを習うのに必要な親のサポートについて解説します。
プログラミングスクールに必要な親のサポート
プログラミングを習うときに必要な親のサポートは大きくわけて3つあります。(1)子どもを支える親のサポート
……子どもが楽しくプログラミングを学びつづけるためのサポートです。
- 親子の会話
- 教室・先生とのコミュニケーション
……実際に親が「やってあげたほうがよいこと」です。
- スクールへの送迎(オンラインでは必要なし→PCのセッティングなどが必要)
- 備品の管理
……プログラミングの学習内容に関して親がフォローすることです。
- 自宅でカリキュラムを復習したり宿題があるときの見守りやフォロー
親子で会話がもっとも大事!
プログラミングを学ぶうえでは「親子での会話」がもっとも重要で大切なサポートになるでしょう。プログラミングスクールに限りませんが、子どもが話そうとしたとき、話したいときに「ふんふん、それで?」と興味を持って聞くのは大切です。問いかけたほうが答えるタイプの子もいるので、子どもの性格に合わせて上手に話を引き出したいですね。
スクールからの帰り道や、オンライン学習を終えた後などはチャンスです。子どももエキサイトしていますから「今日ね、あのね」と話し出します。話すことで自然と「スクールで今日やったこと」を復習できます。
ここで子どもが迷ったり困ったりしている様子なら、プログラミング学習の内容がわからないのか、先生やお友だちとうまくいっていないのか問いかけをしながらポイントを把握しましょう。「ふぅん、今日やったこと保存するのを忘れちゃったの?」「帰りに気づいたけど先生に言えなかったのか〜」と落ち込んでいる理由を共有します。
次に解説する「教室・先生とのコミュニケーション」につなげていくのも親のサポートです。
先生とのコミュニケーションも必要
プログラミングスクールで子どもが「わからないみたい」だったり「教室で困っている様子」だったりしたら親のサポートが必要かもしれません。必要に応じて先生に「ここが困っている」「親がどのようにフォローしたらよいか」を聞いてみましょう。先生も忙しいでしょうから、送迎時にサクっとまとめて簡潔に話すのが大事ですね。子ども自身が先生に聞けるように、おうちでも「ここがわかりませんって先生に聞いてみたら?」と具体的な方法を教えてあげるのも大事です。
ただ、授業の内容によっては子どもが先生に「わからないことを説明するのが難しい」場面もあります。お子さんに付添い、まず子どもに説明をさせて親が言葉を補う方法でもいいかもしれません。
習い事は学校の授業とは違います。積極的に学ぶ姿勢と共に、わからないときや困ったときは遠慮せずに聞いてみましょう。これも親のサポートのひとつです。
けっこう大変なのがスクール送迎
最近は教室も増えていますが、それでも徒歩圏内で行けるプログラミングスクールがあるとは限りません。教室の内容にもよりますが、教材やロボットなど荷物が多いこともよくあります。たとえばパソコンを持ち込む場合もありますし、ロボット教室ではレゴ教材が山のようにあり、コストコのバッグを使用しなければいけないこともあります。教材は雨の日も真夏の日も持っていかなければいけませんし、他の習い事や兄弟姉妹の予定も合わせると、親の送迎は本当に大変です。
プログラミング教室は土日開催も多いので、夫婦で協力するなど「送迎の負担を減らす」工夫も必要です。
備品の管理は親がサポート
ほとんどの教室でプログラミングの内容を記録するためにひとりひとりUSBメモリを持っています。USBメモリはなくしやすいので、しっかり記名しておくのが大事。特に教室で配布される場合USBメモリは全員が同じですから、小さなシールを貼ったり、首からさげられるようにして紐の部分にキーホルダーをつけたり、ひと目で自分のものとわかるように工夫するといいでしょう。プログラミングスクールでは、自分のノートパソコンを持参するケースもあります。ロボット教室は教材も多いですし、高価なツールもあります。いずれにしても小学校低学年のうちはスクールで必要な道具については親子で一緒に管理する必要があります。
プログラミング学習に対する親のサポート

ではレッスンに対して親のサポートはどれくらい必要なのでしょうか。基本的にプログラミングでもロボット教室でも子どもがひとりで、あるいは教室で先生と一緒に進めていけるようになっているはずです。
教室でやったことを復習したり、同じプログラミングを作ったり、自宅で行うには最初のうちは親のサポートが不可欠です。小学校低学年やスクールに通いはじめの頃はそもそも子ども専用のパソコンはないことが多いでしょうから、まず家のパソコンの立ち上げ方や使い方の注意を教えなくてはなりません。
さらに必要なソフトやアプリをダウンロードするのも親が行います。子どもの年齢があがれば自分でもできるでしょうがパソコンに何かをダウンロードする時は親の許可が必要なことや見守ることも「サポートのひとつ」です。
さて、では問題のカリキュラムについてですが、スクールによって「課題(宿題)を出すところ」と「スクール内で完結するところ」があります。課題は出さないが「家でやりたい子は自由にここまで進めていいよ」というスクールもあります。
子どもの性質や親がどれだけ見守れるかなど家庭や子どもに合わせたスクール選びをすることも大事ですね。
親にプログラミング知識がない場合は?
結論から言えば親にプログラミングの知識がなくてもサポートはできます。カリキュラムは教えられないとしても「ここに書いてあるよ」などとアドバイスもできます。とはいえ、多少なりともプログラミングの知識があれば適切なアドバイスができるのは事実です。国語や算数を教える場合なら、(高学年くらいから難しくなるにせよ)参考書等を見て一緒に解くことはできるでしょう。
一方でプログラミングは本当にわからない保護者が大半です。基礎知識がまったくないのですから、子どもに「ここ、どうしたらいいの?」と聞かれても答えられないことが多いでしょう。
でも、わからないときは親も一緒に学べば大丈夫!
プログラミングスクールの教材は初心者や子どもでもわかりやすくできています。イラストや写真入りのテキストや教材は大人が見ても楽しいものです。「ここがわからないね〜」と親子で考え「次回先生に聞いてみようか」と話し合いましょう。そもそも教えるのは先生の役目親のサポートは子どもの意欲を高めることです。
親が泳げなくても子どもはスイミングスクールで先生から泳ぎ方を学んでクロールも平泳ぎもできるようになるでしょう。泳ぐコツを教えられなくても「今日がんばったね」と声かけするなど、親のサポートがあれば途中で挫折することなくスイミングを続けられます。サッカーのルールがわからなくても一緒に公園でボールを蹴ったり試合を観戦したり子どものサポートはできます。プログラミングスクールも他の習い事と同じです。
それぞれの方法でサポートしよう
親のサポートですが「どこまでやるか」は家庭によって考え方が違います。違っていいのです。子どもひとりひとりの個性も気質も違いますし、自立に重きを置く場合も寄り添う形でフォローするのでもそれぞれの家庭がもつ「考え」でいいでしょう。プログラミングやロボット教室では、子どもも親も初めて体験するような〝学び〟に遭遇します。それがワクワクドキドキをうむのですが、時には悩むこともあるかもしれません。見学や早めにお迎えにいったときに子どもの様子を見て
(よくわかっていないみたい)
(先生に聞いてみればいいのに!)
(アシスタントの先生、ウチの子に気づいて教えてくれないかな)
とモヤモヤしたり心配したりする親御さんは決して少なくありません。ましてや、どうやらプログラミングの知識があるらしいパパやママがちょこっと子どもにアドバイスする、帰り道に「あそこはこうすればいいんだよ」なんて教えてるのを目にすると、もし自分にプログラミングの知識があれば…と焦りを感じるかもしれません。
でも、子どもが自分でわからない点を聞くというのも大切な学習です。子どもには「先生!って声かけてみたら」「その場で言えなかったら、回っているもうひとりの先生を呼んでみたら」「わからないのは恥ずかしくないよ」と質問することが大事だと教えてあげましょう。
なおかつ担当の先生に「家でも子どもにわからなかったらちゃんと聞くことは言い聞かせていますが、なかなかできないようです。少しフォローして頂けると安心なんですが」とお伝えするといいですね。教室の方針にもよるでしょうが、たいていはこれで先生も何かの折りに注意を向けてくれます。
プログラミングでは知識はないよりあったほうが「教えやすい」のは事実ですが、ないからといって困ることはありません。それどころか子どもと同じように「わからないところからスタートする」ので子ども目線で一緒に考えることもできます。一緒に迷い悩み考えるのは親子のコミュニケーションが深まる良いチャンスでもありますね。
お子さんが楽しくプログラミングスクールに通えるよう「わが家流のサポート」をそれぞれのご家庭で考えてみてください!
すべての習い事で親のサポートは必要
実はプログラミング教室だから親のサポートが必要というわけではありません。習い事では常に何かしらの親の協力が必要です。大切なのは子どもが「おいてけぼり」にならないこと。興味を失い、教室に通う意欲を失ってしまわないようにすることです。それには、まず親が子どもの習っていることに一緒に興味を持つのが大事ではないでしょうか。
小学生くらいの子どもは、なんだかんだと言っても親がワクワクしているのを感じ取り「ママやパパも楽しそう」と思えば嬉しく思うものです。親が不安そうなら子どもも不安になりますし、子どもへの苛立ちを見せれば子どもは萎縮するか反発します。
一緒にプログラミングを習おう!というくらいの前向きな気持ちこそ、何よりのサポートになると思います。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
子どものプログラミング学習におすすめのパソコン10選|予算やスペックなどの選び方をご紹介
2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されることを受けて、今のうちからお子さんにプログラミングに触れさせておこうと考えている親御さんは多いようです。 プログラミングをするた...
2025.02.17|コエテコ byGMO 編集部
-
WRO(World Robot Olympiad)とは?小中高校生が挑戦できる国際ロボットプログラミング大会
2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されるにあたって、子ども向けのプログラミング教室への関心が高まりを受け、プログラミングを習い始めるお子さんが増えていますね。 プログ...
2024.12.20|プログラミング教室ガイド
-
子ども向けオンラインプログラミング教室おすすめ16選【2025年最新版】
2020年度、ついに小学校でプログラミング教育が必修化しました。コロナ禍の影響もあいまって、自宅からプログラミングが学べるオンラインスクールへの注目が集まっています。 この記事では子...
2025.02.06|コエテコ byGMO 編集部
-
プログラミング能力検定とは?難易度や対策を徹底解説
2020年4月からの小学校でのプログラミング教育必修化で注目の「プログラミング」の能力をはかる試験として注目の「プログラミング能力検定」を徹底解説。 気になる試験内容・難易度・受験料...
2024.11.06|コエテコ byGMO 編集部
-
子どものプログラミング学習におすすめのドリル5選!パソコンなしでOK
2020年度より小学校でプログラミングが必修になりました。「家にはパソコンもない」「プログラミングとかまったくわからない」と困惑する保護者の皆さんに、アンプラグド(コンピュータを使わな...
2024.11.06|コエテコ byGMO 編集部