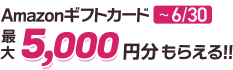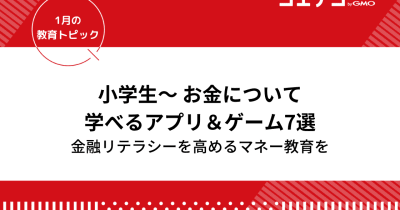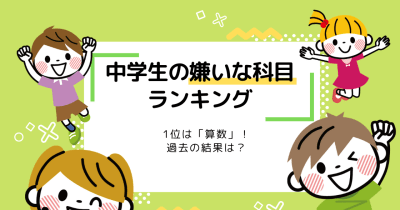一因には、日本人の金融リテラシーの低さが指摘されており、政府広報オンラインでは、金融リテラシーを高めることが子どもたちの経済的自立に必要な基礎科目だという考えが強調されています。この記事では、子どもの金融リテラシーや生活力を高めるお金の教育はどのようなものなのかについて、情報をまとめました。
引用:日本銀行調査統計局『資金循環の日米欧比較』(2023年8月)
子どもに必要な「お金の教育」とは?

例えば、子どもに身近なものとして、スーパーでおやつを買うときには、商品本体の価格と消費税の支払いが必要です。この例だけを見ても、「もの」と「お金」(貨幣)の価値を交換すること、税金というものの存在、それが何にどのように使われて自分の暮らしに関わっているのか、という「お金の教育」に繋げて考えることができます。
子どもはまず、「お金とは何か」「それが自分の暮らしにどうつながっているのか」など、生活に必要不可欠な部分から学ぶことが大切です。
政府広報オンラインが紹介している「小学生で必要とされるリテラシーの目安」では、例としておこづかい帳をつけることや、商品の選び方を知り、工夫して買い物ができるようにすること、貯蓄の意義を理解して計画的に貯蓄する習慣を身につけることなどが挙げられています。
子どもへのお金の教育はなぜ必要?

文科省の高校家庭科の指導資料にも、「生涯の経済計画とリスク管理」が含まれており、「お金」の知識は生活を確立させるために必要な項目として扱われています。
身近な金融商品の例には、各種の保険やローン、クレジットなどがあり、将来設計への影響は無視できないでしょう。
自分たちが使うお金・お小遣いはどこから出ていて、使うとどうなるのかを子どものときから学んで理解していくことは、ものの価値を判断して取捨選択する力や、リスクの高い金融商品を避ける力に繋がるといえます。
幼児の場合は「数や計算の概念」を身につける機会にもなる
幼児にとってのお金の教育は「金融」という側面だけでなく、「数や計算」の概念を身につける機会にもなります。例えば、硬貨を使うことで、1円玉が5個集まると5円玉と同じ価値になる、10個集まると10円玉と同じ価値になる、10円玉が5個集まれば50円玉と同じ価値になる、というように、数の概念に気づき、四則計算の基本になる5や10のまとまりを意識できるようになります。
子どもによっては、ドリルなどではまだ理解できない足し算や引き算でも、お買い物ごっこの支払いとおつりを通して計算すると答えがわかるケースがあります。
電子マネーが普及した現代では、子どもがお金のやりとりを目にする機会が減っています。まだ数の概念がわかっていない段階では、意識して現金での買い物のやりとりを見せたり、お使いをさせるなどの工夫も、お金の勉強に効果があるかもしれません。
ものの価値を判断して取捨選択する力を身につけられる
子どもに対しお金の教育を行うことで、子ども自身の価値判断基準を創り上げることができます。その結果、自身の価値基準をもとに取捨選択できるようになります。不要な買い物を防止できることはもちろん、そのものの価値を理解した上で相応の金額を支払うという行為に至ることができるようになるでしょう。
見えないお金を使い過ぎてしまうことを防ぐため
近年はクレジットカード決済やスマホ決済など、通貨や紙幣を触ることなく決算できる場面も増えました。そのため、「お金を使っている」という感覚を持ちにくいが故に、知らない間にお金を使い過ぎてしまうトラブルも珍しくありません。アプリ内課金やソーシャルゲーム内の課金などが問題になるケースも頻発しています。
お金の価値や流れ、さらには「使ったら無くなる」といった当たり前のことまで、お金の教育を受けることでお金の価値をしっかりと理解しながらお金を使えるようになるでしょう。
日本の「お金の教育」の現状は?
文科省による2012年の資料では、金融経済教育の取組に関して下記のように書かれています。「学校教育においては小・中・高等学校の社会科・公民科、家庭科などの教科を中心に、児童生徒の発達段階を踏まえ、消費者教育・ 金融経済教育に関する内容を指導すること」
具体的に小・中・高でそれぞれ何を学ぶかについては、下記の内容が書かれています。
・小学校
家庭科では身近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できるようにする
・中学校
社会科(公民)では、契約の重要性やそれを守ることの意義、個人の責任に気づかせる
・高等学校
家庭科では、クレジットカードの適切な利用や多重債務問題など、消費生活と生涯を見通した経済の計画について理解させる
課題もあります。2014年に日本証券業協会が運営する「金融経済教育を推進する研究会」が行った調査では、中学校・高等学校の教員の中でも、金融教育の知識や必要性の感じ方にはばらつきがあり、より拡充すべきとの意見書が提出されています。
お金の教育は何歳から始めると良い?
日本のお金の教育はまだ不十分と考えられていますが、他の国ではどのような教育が行われているのでしょうか。2015年に出版された北海道教育大学の鎌田浩子氏の論文によると、金融教育をいち早く取り入れたイギリスでは、3歳から11歳を対象として行う金融教育の教員用キットが無償で提供されています。
3~5歳ではお金の認識やお金の使い方を、5〜7歳ではお金の使い途の選択や貯蓄、お金をどう得るのかを、7〜9歳では現金以外の支払い、お金の貸し借りや預金のことなどを、段階的に学ぶカリキュラムが作成されています。
これらの情報を見ると、少なくとも3歳程度からお金の教育をすることは可能と考えられます。
子どもが家庭でできるお金の勉強の例

お金は日々の生活と切っても切れないもの。家庭での生活や遊びの中にも「お金の教育」の機会はたくさんあります。日々の買い物やおつかいは基本中の基本と言えますが、そのほかにもお金に関する知識や感覚を身につけられるゲームや、お小遣いの制度を工夫するといった例を紹介します。
お金について学べる知育アプリ・ゲーム
知育アプリやゲームを活用すれば、手軽に楽しくお金について学べるでしょう。知育アプリやゲームの中には、小学生低学年から楽しめるものや、本格的な資産運用や株式を体験できるアプリもあります。
子どもの興味・関心や理解度に合わせて活用してみてはいかがでしょうか。
中には、親子で遊びながらライフプランやマネープランを体感できるゲームもあります。親子でマネーリテラシーを醸造していくのも良いでしょう。
お金について学べる子ども向けの本
金融教育・金融リテラシーが注目される昨今においては、お金について学べる子ども向けの本も多く出版されています。お金について本を使いながら学ぶ際は、年齢や理解度などを加味して本を選ぶことがポイントです。
またお金は子どもにとって身近なものでありながら、学ぶとなるとハードルの高い教材です。
一口にお金の教育と言っても、投資・稼ぎ方・経済の仕組み・税・暗号資産など多様です。
まずはお子さまの興味・関心を喚起するテーマや題材を取り上げた本で一緒に学びを深めていきましょう。
ボードゲーム
「勉強」ではなく遊びながら学べるのがボードゲームの良いところです。テレビゲームや携帯アプリにもお金の教育に役立つものはありますが、手でお金を手にしながら、数えたり、使ったり、増やしたり、といった体験ができます。
ウェブサイト「マネープランニング」で、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の森本陽子さんが、お金の教育に役立つボードゲームとして紹介しているのは、「モノポリー」と「人生ゲーム」です。
「モノポリー」は20世紀初頭にアメリカ合衆国で生まれたボードゲームで、すごろくのコマを進めながら、不動産取引をして家やホテルを建設し資産を増やしていくゲームです。投資をはじめ、税金や給料、借金、破産、富の独占など、お金にまつわる様々なこと学ぶことができます。
「人生ゲーム」は日本版のモノポリーといえます。就職や転職、結婚など人生のイベントによってお金の収支が変わり、勝敗に影響する構造があります。お金に関連する仕組みが簡単なため、計算があまりできない未就学児でも楽しみやすいでしょう。
「倍返し」を取り入れたお小遣い制度
働く女性のための情報サイト「withオンライン」に公開されている、不動産投資コンサルタントを行う株式会社ADVANCEの村田幸紀代表のお小遣い制度を紹介します。それは「お小遣いの倍返し」。残ったお小遣いと同額のお金を翌月に「ごほうび」としてもらえる=残額が2倍になる制度です。例えば、今月のお小遣いとして1000円を子どもに渡します。翌月200円残っていたら、倍額の400円をお小遣いとは別に渡します。つまり、この場合のお小遣いは合計1400円になります。お金を使わずに残しておくことでメリットが得られる仕組みです。
この方法は、名古屋テレビ「メ~テレ」でも紹介されており、YouTubeの公式チャンネルでは、村田幸紀代表の説明や、実践した家庭の声を視聴することができます。
番組で紹介された子どもたちの話では、お小遣いを使い切らずに残したいと思うようになったことや、計画的に増やせることでお金を使うべきときに使えるようになったといった変化が起きたということでした。
金融庁が行っている取り組みを活用
金融庁が行っている取り組みを活用するのも1つ。子どもに人気のうんこドリルとタイアップした学習教材やクイズやゲームで楽しく金融のことを学べるサイト、日本銀行の歴史や建物内の様子を見れるバーチャル見学ツアーなど、親子で楽しめるコンテンツがたくさん集約されています。
自宅で気軽に遊び感覚で学ぶことができるため、お金の勉強を始める際にぜひ活用してみてください。
引用:金融庁
子どもの「お金の教育」におすすめの習い事
保護者にとっても、お金の教育を何からどのように教えたらいいのかは悩むところ。そんなときにおすすめしたいのは、子ども向けのお金の習い事です。子ども向け金融教育「フィネコキッズ」

創業者・青木ミサさんは、国内外の大手証券会社で約15年にわたり、市場分析や運用手法開発に携わってきた金融のスペシャリスト。
「お金って何?」「お金を使う」といった初心者向けの講座から、「投資の基礎知識」、「マイナス金利って何?」といった時事問題の解説講座など、複数の講座をオンラインの個別指導方式で提供しています。
子どもの年齢や興味・レベルに合わせて選択できるほか、親子での講座受講もできるのが魅力。親子で金融リテラシーを高めたい人におすすめです。
・FINECO KIDS(フィネコ・キッズ)
所在地:オンライン
対象:小学生から高校生
コース&料金:1講座5000円、2講座9000円(体験レッスン30分・2000円)